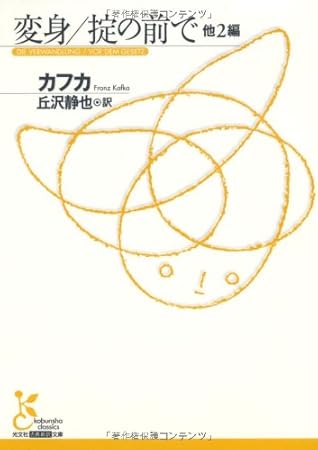■スポンサードリンク
変身変身変身変身変身変身変身変身変身
変身
変身
変身
変身
変身
変身
変身
変身
変身
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
変身の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.08pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全293件 121~140 7/15ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 朝起きると、急に毒虫になっていた。 設定が面白いと感じました。それに対する肉親の応対など、人間の本質を考えさせられました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 通勤時に読む用に購入しました。 コンパクトで持ち運びに便利です。 ネタバレは避けますが、やはり有名タイトルだけあり面白いです。冒頭で一気に引き込まれる感覚があります。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この本の想定は現代社会ではいつでも起こる可能性を考えると極めてまともなテーマを扱っているように思える。カミュの異邦人もそうだが、半世紀も経つと社会環境や人の考え方が大きく変わり、異次元の世界と思われたものが普通の社会に存在することに驚く。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 内容が難しいのかなと思ったのですが すらすらと読むことができました ラストの結末には悩まされましたね | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| とかく人間は相手にそう願います。カフカもその家族の思いと本当の自分らしさの間で苦悩、葛藤、もがいていたのではないでしょうか。官僚を望む父と作家になりたいカフカ、地下室の奥部屋で物書きをしながら誰にも会わず、食事を運んできてもらう生活が理想だったというカフカ。幼い頃の父の圧政がトラウマになったカフカ。相手に会わせ相手に与えてばかりいるうちに生きるエネルギーが枯渇してしまった。本当の自分に帰りたい「変身」願望。それを「変身」でシュミレーションした。「変身」の中で父から投げつけられた(背中にめり込んでしまった)リンゴは聖書のメタファーだと私は思う。「私の理想のあなたでいて欲しい」リンゴにはそんな父の願いが込められている。そして父はそれが自分のエゴとは気付かない。それは為政者に都合よく改ざんされたキリスト教思考、封建社会でもあり、それに染まった家族は疑問にすら感じない。常識、既成概念からの支配、呪縛、その中で血を流しながら苦悩するザムザ、本当の自分が悲鳴を上げる。カフカの妹は兄に作家執筆できる部屋を提供してくれたそうです。「変身」の中で妹が家具を取り除いてくれるシーン、どちらも兄を思ってしてくれた好意が皮肉にも家族と社会からの決定的な断絶となります。兄は人間ではなく言葉の通じない理解不能な虫であった。それが露見してしまった。その後のカフカの病気は必然にカフカ自身が引き寄せたようにも感じられます。カフカは自分の絶望をユーモアに包み「変身」を書きました。皆を楽しませるため、同時に、この「変身」を書く事で、世の中にリンゴ(聖書)を投げつけたのかも?しれません。世の中に問題提起してこの世を静かに去っていった。虫になった主人公が家族(妹)の幸せを願い死んでゆく姿に、不条理、絶望をユーモアに昇華したカフカの愛と強さを感じました。自分が犠牲になる事が自分の望んでいた家族の自立であったという皮肉。リンゴを背負ったザムザ、それはまるで十字架を背負ったキリストのようにも見えました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この作品を読んだのは今から約5年前、現代文の授業で読書感想文の提出を求められた時。 候補に挙げられていたいくつかの作品の中から、本が最も薄いから、という理由でこの「変身」を選んだ。 いざ本を開くも活字の群れは私の手には負えず、好き勝手うねっているようにすら見えた。 途方に暮れた私はamazonのこのページを訪れ、明達な先人達が残したレビューを拝借し、どうにか800字を書ききったのだ。 その感想文がなんと校内で優秀作に選ばれ、他の優秀作者との集合写真が校内新聞に掲載されることにまでなった。 そんな青春時代の愉快な思い出と、少しばかりの後ろめたさをふと思い出した秋の夜長。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本書には、『判決』『変身』『アカデミーで報告する』『掟の前で』の諸作が収録されている。 最も有名な『変身』は、100頁の中編だが、あとは短編である。 『変身』は、セールスマンのグレーゴルが、ある日目を覚ますと虫に変身したという話である。グレーゴル=個人、周囲の人々=世の中、と置き換えると、作者カフカに言おうとしていることは明白であろう。このような読み方が正しいかどうか分からないが。 ただし『変身』はやや冗長のように感じる。3分の2くらいに圧縮すれば、もっと引き締まったピリリとした小説になったのではないだろうか。 本書の中で秀逸なのは、人間に捕えられ人間社会で暮らすようになったサルがアカデミーで講演する『アカデミーで報告する』ではないだろうか。これも、サル=個人、人間社会=世の中と置き換えれば、カフカの言おうとしていることが見えてくる。人間社会についての風刺がきいているし、「自由ではなく出口がほしい」というサルの言には考えさせられるものがある。 なお本書は、文章があまりこなれていないように思う。これは訳者の丘沢氏が「オリジナルに忠実に」という翻訳態度を採っている以上、丘沢氏のせいというより、カフカ自身に帰すべき問題なのかもしれない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 存在は知っていたが手が出なかった本である。 淡々とした文が流れていくが、よく読めば一つの文章にいくつかの反対語、嬉の直後に訪れる悲、のような言葉が続いていくことに気づく。 矛盾を抱えながら物語は進み、最終的には家族愛、羞恥心、虚栄心、生死の望みすら超えて、すべてを飲み込んだものは虚脱感、疲労、あきらめであった。 そしてすべてを放棄した後に、非情にも新たな道をゆく家族。 病気や老衰についてまわる介助、前触れなく訪れてしまう悲運、人間が受け入れられる限界を超えたとき、すべてを放棄することで双方が楽になるということか、それがたとえ死であったとしても。 矛盾を読み解くには数回読み返す必要があると思われる。また時間をおいて読み返したい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 『城』と同時に購入しました。 まだ読んでおりませんが、とても楽しみです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 子供の読書感想文で使用しました。 すこし難しいけれど面白かったです! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 若い頃に読んだ作品で心にひっかかっていて、”もう一度読まねば”と考えていた中の一冊。 カフカの生涯に関し詳しい知識は持たないが、残されているカフカの写真を見ると、なんとも暗そうな表情に思える。カフカはこの作品を通じて一体何を伝えたかったのか?と改めて問いながら読んだ。 結局、今回の読み直しで頭に浮かんだテーマは月並みながら”疎外”という言葉であった。 朝起きてみたらどういうわけか虫になっていた主人公グレゴールは姿形はすっかり奇怪で醜悪になってしまったが、その心情にはまったく変わりはない。妹に対する心優しさを含めて家族への想いは変わらない。また支配人に使われるセールスマンとしての義務感にも変化はない。 しかるに家族を含めた周囲の人達のグレゴールを見る眼、そして対応はどんどん冷たくなってくる。そして最後グレゴールが死んだ後残された両親と妹は何もなかったかのように平穏な生活に戻る。 カフカの写真のイメージからも影響かもしれない。ただ”この世の生きにくさ”、’”人間関係のもろさ”、あるいは”むなしさ”をこのような簡潔な形で端的に描いた文学作品は確かに前代未聞だったのだろう。その強烈さがこの作品にはある。 しかるに一世代前と比べると今の日本では”疎外”あるいは”不条理”だとか”実存(主義)”などという言葉は余り聞かなくなってしまった、と感じている。 むしろ10数年前に米国に滞在していた際、娘の通っていたhigh schoolではliteratureの時間で結構カフカ、カミュ、サルトル等をexistentialism文学として読ませていたことを思いあわせると、西欧では思考訓練の一環あるいは思想上のテーマとして”疎外”という課題が引き継がれているのであろう。 今の日本では”疎外”といった深刻な捉え方は、やはり受けないのであろうか? | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| もう語りつくされている事だろうが、本作の毒虫というのは文字通り虫とは限らない。 精神病になってしまった、大怪我をして寝たきりになってしまった…など突如として訪れた 身内の不幸と、それに伴い家族にのしかかる二次被害的な負担の事を言っているともとれる。 グレーゴルも好きで毒虫になったわけではない、ましてやある日目が覚めたら毒虫になってしまうという 作中で最も理不尽で不幸な目に遭っている人物なのだ。しかし、家族はただ毒虫になったグレーゴルを 怖がるばかりで彼の心中を察そうともしない。食事を与えることぐらいしかしないのだ。 何をしようとしても悪い方向に勘違いされてしまい、挙句の果てには虐待まがいの行為までグレーゴルに働いてしまう。 そして自分達はこの毒虫のせいで苦しんでいる被害者だと言いのけてしまう有様。 彼ら家族を酷いと思うだろうが、現実誰かに問題や欠陥が発生して家の中が滅茶苦茶になってしまった時 ほとんどの家庭ではこういう結論に行き着くのだろう。毒虫になった本人の気持ちなど知りもしないで。 原因がはっきりしている分早い話がそれを取り除いてしまえばいいということになる。 既に虫になったグレーゴルに人権などないのだ。そして彼はあっけなく死に絶え、彼のいなくなった家庭は 明るい方向へと向きだす。仮にも家族の一員が死んだにも関わらずそんな事など微塵も気にしていない様子を 見せる家族のラストでこの作品は終わる。 介護、引きこもり、障害といった現代における家庭環境が抱える現代進行形の問題にも充分に呼応する名作。 今の時代、毒虫は日に日に増えていく一方である。そしてそれだけ家庭内で差別を受ける毒虫は後を絶たないのだろう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 不条理でありながらリアルなカフカの世界が鮮やかに描かれていてとても読みやすい訳でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 大学の息子の課題図書を探していました。すぐ手に入ったので、助かりました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 子供の頃から気にはなっていたけどどうしても読む気にはなれなかった著書をこの歳になって読んでみた。 男が“巨大な害虫(Ungeziefer)”に変身し、衰弱死するまでの描写がただ淡々と描かれているだけなので、自分の中に落とし込む為には少し時間がかかった。 まず読んだ直後の印象は、「何でこんな作品が何十年も名著として読み継がれているのか?」という疑問だった。 身も蓋もない極めてシンプルな経過であり、主人公の不条理に始まり不条理に終わっていくので、読了感は複雑である。大抵の人はそうなんじゃないかと思う。 はっきりしたヤマやオチは無く読み手任せなので、最初の印象から時間が経って、本作をどのように消化するかは、時代背景とか経験とか見る側の視点とかが大きく反映されると予想され、人によって大きく違うと思われる。 父の経営が破たんした時は一家にとって希望の存在であり、それが当たり前になった後も一家の大黒柱であった主人公。しかし、利益をもたらすものから百害しかないような存在に“変身”していしまった後の世間の反応は冷たい。というかそれ以前の問題だ。 そんな主人公に対する家族の驚愕や嫌悪との葛藤、最後のはっきりした決別へと至る感情の変遷は、判り易く、主人公・家族の両方の立場に容易に立たせてくれる。 また、自分が姿も味覚も習性も変わり、“毒虫”になった時、その取り返しもつかない深刻な現状への考えに至らず、昨日までのサラリーマンである自分の日常に対する不満を嘆きながらも、それまでのように仕事を続けようとするグレゴール。 しかし時が経ち、“変身”後の彼が快適に動けるようにと、家族が家具をすっかり取り除こうとした時の抵抗の姿から、かつての自分への執着が見え滑稽にも悲劇的にもとれる。しかし、家族を想い己の死に安堵する彼自身の内的部分に変わりはない。 一方、野垂れ死んでしまった兄とは対照的に、ラストは家族の美しい未来への希望の象徴して描かれている妹のグレーテの姿も印象的であり、主人公の変化によってもたらされたもう一つの“変身”のように感じられる。面白いことに、双方の本質は実際のところ何一つ変わっていないのにだ。 そうやって振り返ると本作は、家族のエゴとか介護問題とか社会の矛盾とか、大人になると色々なことを連想させる物語である。だからこそ、『そういうこと』を体験しない内に一度読んでおくと大人になってから発見があって面白いかも知れない。 そういう意味で、若者(子供)にもお勧めの本である。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| NHKの番組『100分de名著』などでも取り上げられ、現代の我々にも響く名著としてしばしば挙げられる本書。なんとなく、Audibleで見つけたので聴いてみることにしたのだが、最後の最後まで、私にはカフカの言いたかったことを理解することはできなかった。おそらくそれは、私自身がまだ若く、この物語に照らし合わせるべき経験を持ち合わせていないせいなのだろう。ただ、同時に、きっと彼は何か、自分の感じたやりきなさだとか悶々としたような感覚を、描こうとしていたのではないだろうか、そして我々にそれを突きつけてやりたかったのではないだろうか…そうも感じた。 全く得体の知れない強烈な感覚だけが残った。 或る日突然、気味の悪い虫に「変身」してしまう。 それは他者を傷つけ、不幸にし、自分は、彼らから身を隠すようにヒソヒソと生きる。 挙げ句の果てに、自分が死を持って皆の前から姿を消したことによってーと言ってもその死は彼らによってもたらされるのだがー彼らは幸せに暮らしていけるようになる。 「…はあ?」と言いたいくらい、ズドンとしたよく分からない何かを一方的に背負わされ、置き去りにされてしまったな、という感覚だ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この小説が書かれたのは第一次大戦後の敗戦で苦境にあえいでいたドイツ。 挙国一致で頑張らなければいけない時期だがみな倦怠感が漂っており、作中の人物のように働きたがらない人も大勢いた。 しかしいつの時代も家族のため、社会のため働くのが大人であり、そうでない者は社会不適合者とされる。 内面にどんな重い物を抱えていたとしても、他人からすればそう見る。まるで汚いものを見るかのように、毒虫を見るかのように。 作者は小説のタイトル絵を書くイラストレーターに、毒虫の絵だけは描かないでくれといった。 毒虫と思っているのは実は主人公だけであり、外の人間は働かない人間を蔑んでいたにすぎない。 しかしその毒虫に甘んじていると、やがて美味しいものも美味しく感じられなくなるくらい一般常識が狂い、 信頼していた身内からも見捨てられる。 現在のニートだらけの日本でこそ読みたい本だと思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種に出てきた台詞があるので読みたくなり購入しました。 ストーリーが面白いです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 中学生の時に大人に薦められて読んだ。 読めたけど、解らなかった。 当たり前だ。 社会人に為った今、染みる作品。 この作品が解る中高生。 少し恐い気がする。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 奇妙な小説です。 物事についての言及が不完全であるため、様々な解釈を巡らせることができます。 異常な出来事が淡々とした文章でかかれていて、独特の雰囲気があります。 有名な作品ですので一読することをおすすめします。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!