■スポンサードリンク
薔薇の名前
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
薔薇の名前の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.19pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全92件 1~20 1/5ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本自体は満足いくものだったが、輸送による本の角や隅のかすれが思った以上にひどい 以前はもう少し丁寧に梱包されていたと思うのだが… | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 作品は素晴らしい。ここで書くことではないでしょうが、私もコレクションとして限定カバーを手に入れたいので予約しました。届いたら紙袋包装で破れており、中身の書籍本体は折れ、全体的に擦れて傷がありました。高額なのと楽しみにしていただけにショックです。今回、作品のレビューを書くところで、配送の不満を作品評価に反映すべきではないと思って星は純粋な作品評価にしています。只、他にも同じ方が多かったようなので購入方法の参考と改善の足しになればと思い投稿します。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 14世紀のイタリアの修道院で連続殺人が起こり・・・というお話。 以下、訳者の河島さんのあとがきからの引用(ネタばれあり)。 「ところで推理小説はその構造上、周知のように、まず発端となる事件(たとえば死者)があって、何等かの決着(たとえば犯人の発見や逮捕)へと向かうのであるが、その間に、作者=探偵=読者にとっては、解決しなければならない関門(たとえば謎)が控えている。長篇『薔薇の名前』には、推理小説のための小道具や大道具が十分に揃っていて、この糸をたぐっていく読者は、たとえば、あの異形の建物のなかへ入りこみ、迷宮の謎を解いていく過程で、大きな知的喜びを味わうであろう。しかしやがて、それらの複雑な謎もみな解明され、一連の事件を決着へ向かう。その時点において、すなわち、山上の僧院が炎上して、まさにすべてが灰燼に帰さんとしているとき、その光景を前にしながら、ウィリアムはアドソに向かってつぎのように言う。その科白に、賢明なる読者は、ぜひ注意していただきたい。『一連の犯行を支えているかに見えた、『黙示録』の図式を追って、わたしは○○〇にまで辿り着いたが、それは偶然の一致にすぎなかった。すべての犯罪に一人の犯人がいるものと思い込んで、わたしは○○〇にまで辿り着いたのだが、それぞれの犯罪には結局、別の犯人がいるか、誰もいないことを、発見したのだった」敢えて、繰り返しておく。ウィリアムは犯罪には別の犯人がいるか、誰もいないことを発見した、と言っているのである。この科白は、尋常ではない。ウィリアムは(彼はもはやエーコであって、ホームズではない)その先に続けて言う。『邪悪な知能に長けた者の企みを追って、わたしは○○〇にまで辿り着いたが、そこには何の企みもなかった。あるいは、○○〇自身が初期の自分の企みに圧倒されてしまっていた。と言ってもよい。一連の原因の鎖が、原因から派生した原因の鎖が、相互に矛盾する原因の鎖が、つぎつぎにたぐられていくと、それらが勝手に独り歩きをして、初期の企みとは無縁な別個の諸関係を生み出してしまうのだった。わたしの知恵など、どこに居場所があろうか?」 〇になっているところは固有名詞で伏字にしました。この感想がこの作品の端的な要約になっていると思いました。 ジョージ・オーウェルの「一九八四年」にピンチョン先生が悲痛なラブストーリーとしても読める、と言ったり、レムの「ソラリス」もそういう部分があったりする事を鑑みて、この作品を読むと、 「ヨハネの黙示録」に見立てて犯罪が起こるは、マザーグースの童謡通りに犯罪が起こるサスペンス 「アフリカノ果テ」という文章を調べるのは、暗号解読 迷宮の文書館を調べるの所は、館ものの推理小説、その中を調べるのは洞窟探検の冒険小説 という風に、娯楽推理小説とも読める、とこう言いたい訳です。 実際は推理小説の枠組みを借りた神学問答で、その進学問答に、キリストの清貧、愛し合っている関係での性愛が許されるか、異端と正統の違いを組み込んだ作品に思えました。もの凄く個人的な感想を申せば、「黒死館が出てくる『虚無への供物』」という風に思いました(珍説ですが)。著者のエーコさんがイタリアの人で、イタリアがローマ法王庁とかあって、キリスト教の総本山とういう事で、キリスト教をある程度知っていないと判りずらい所もありますが、総じて面白く読めました。 個人的には、夫婦同志の性愛、子作りの為の性愛もあまりよくないというのが、夫婦間のセックスレスがよくないと言われたり、LGBTが普通になった二〇二五年終わり頃に読むと、隔世の感がありました。 題名に関しては、著者覚書で、「書名は読者の考えを方向づけるのではなく、それを混乱させねばならない」という事で、勝手に解釈しますと、薔薇が実際咲いて萎れますが、見た人の心には残り、信仰心を持っている人もいずれは死にますが、他に生きている人にその信仰心は継承される、という風に解釈しております。ケインの「郵便配達夫はいつも二度ベルを鳴らす」もケインの家にくる配達の人が二度ベルを鳴らす人だった、という単純な理由で付けられ、後付けでいろいろな解釈が生まれたという事で、本書もそれぞれが勝手に解釈していいらしいです。 今回の改訂版は、以前のエディションとどこがどういう風に代わったか比較してないので、判りませんが、知っている方がいらっしゃれば、ご教示して頂きたいです(自分でやれと言われそうですが)。前に読んだ際よりも面白かったので、☆は一つ増やしました。 昔のキリスト教の神学問答を推理小説の枠組みで再現した感じの作品。是非ご一読を。 蛇足ですが、この作品と直接の関係はないですが、「エドガルド・モルターラ誘拐事件 少年の数奇な運命とイタリア統一」というノンフィクションで、イタリアの宗教事情が判ります。 また、似た感じの作品で、ポトツキという人の「サラトガ手稿 完全版」、オルハン・パムク氏「私の名は赤」もお勧めしておきます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 作品内容に文句はないです。 文句なしに面白いです。 ですがアマゾンには文句言いたい。 なぜ箱でなく紙袋で配送したのでしょうか。しかもビニールで二冊固定してないせいで、暴れまくったのでしょうね、角は剥げ、折れ線ができてます。いつも、複数冊と時は箱で発送してもらってただけにショックでした。最近そんなツイートとか評価が少なくないのに、いい加減商品を大事に扱って欲しいです。 せっかくの完全版で初版なのに。 仕事中からワクワクしながら待ってたのに悲しいです。 アマゾン側の問題なので星は減らしませんが、版元のサイトからの購入を強く勧めます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 紙袋に素のまま入れて届きます。 気にする方は注意しましょう。帯と角がよれた状態でした。 版元のサイトでの購入をおすすめします。 なお作品内容は文句なしに面白いので、そちらもまたおすすめします。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ウンベルト・エーコの薔薇の名前は、史上最高のミステリー作品です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| かなりの読書家でも、『薔薇の名前』(ウンベルト・エーコ著、河島英昭訳、東京創元社、上・下)は読み終えるのに苦労したという声を何度か耳にしました。 この小説では、中世の北イタリアの山上の由緒ある修道院で起こった奇怪な連続殺人事件の謎に、当修道院を訪れたフランチェスコ会修道士、バスカヴィルのウィリアムと、その弟子のベネディクト会見習い修道士、メルクのアドソの師弟が挑む1327年11月末の7日間が描かれています。 鋭い頭脳の持ち主であるウィリアムは、謎解きの途中で、この事件の原因は修道士同士の争いや復讐ではなく、修道院の敷地内に建つ巨大な迷宮構造を有する文書館に秘蔵されてきた禁じられた一巻の書物が関係していることに気づきます。 諦めずに最終ページまで読み通すために、3つの補助線を引くことをお勧めします。 第1の補助線は、宗教の線です。ウンベルト・エーコが物語に重々しい雰囲気を与えようとして詳細に綴った当時の宗教界の事情をざっと理解したら、このことに必要以上に囚われないようにしましょう。 共にベネディクト会の流れを汲むフランチェスコ会(「小さき兄弟会」がその中核)とドミニコ会が正統か異端かという勢力争いをしていること、そして、これがフランチェスコ会の後ろ盾の神聖ローマ皇帝ルートヴィヒ4世と、ドミニコ会の親玉たる教皇ヨハネス22世の代理戦争でもあったことを知っておけば十分でしょう。 第2の補助線は、推理の線です。シャーロック・ホームズの大ファンだったエーコは、これでもか、これでもかというぐらい、次から次へと複雑な謎を仕掛け、ウィリアムに解かせているが、コアな推理小説ファン以外は、この部分ではあまり頭を使わずに、謎解きはウィリアムに任せておきましょう。 その代わり、最後の最後で明らかになる一番重要な謎には真正面から向き合ってください。この謎こそが、本書の肝だからです。そして、「笑い」について、改めて考えてみましょう。 第3の補助線は、学識の線です。エーコは自身初の小説である本作品に論理的かつ重層的な骨格を与えるべく、持てる学識の全てを注ぎ込んでいます。ウィリアムは、「オッカムの剃刀(かみそり)」で知られる実在した「オッカムのウィリアム」の親友ということになっています。この学識部分は、軽く、はい、はいと頷いておけばいいでしょう。 何しろ、語り手があちこちで、「この老いたる僧は、あまりにも横道へ足を踏み入れがちであるから」、「またしても私のペンは、横道に逸れて、語る必要のないことまで語ってしまった」、「どうやら、私の物語は冴えない脇道へ入りこんでしまった」と言っているくらいですから。 個人的に気になったのは、物語の末尾のアドソとウィリアムの、「・・・神が存在しないことを証明するのに等しいのではありませんか?」、「おまえの問に、然りと答えたならば、学僧である身としては、どうやっておのれの知識をこれから先も伝えていけるであろうか?」という、修道士らしからぬ会話です。 そして、死を目前にした語り手は、「ほどなくして、わが始まりの時と私は混ざり合うであろう。そしていまではもう私は信じていない、それがわが修道会の歴代の僧院長が説いてきた栄光の神であるとも、あるいはあのころ小さき兄弟会士たちが信じていたような栄光の神であるとも、いや、おそらくはそれが慈愛の神であるとさえも。<神トハタダ無ナノダ・・・>。私はすぐに、その広大無辺な、完全に平坦で果てしない、無の領域へ、入りこんでいくであろう。そこでは、真に敬虔な心が安らかに消滅していくのだ。私は神聖な闇のなかに、まったくの沈黙のうちに、捉えがたい一体感のうちに、深く深く沈んでいくであろう。そしてそのように沈みこんでいくいなかで、あらゆる同じものも、あらゆる異なるものも、失われていくであろう。そしてあの奈落のなかで、私の精神はおのれを失っていき、平等も不平等も、何もかも、わからなくなっていくであろう。そしてあらゆる差異は忘れ去られ、単純な基底に、何の異同も見分けられない荒涼とした沈黙のうちに、誰もがおのれの居場所さえ見出せない深い奥底に、私は達するであろう。形あるものはもとより、揺らめく映像さえない、無人に神聖な沈黙のうちに、私は落ちこむであろう」と、物語を結んでいます。 そこで、ChatGPT5に「ウンベルト・エーコは神の存在を信じていたのですか?」と聞いてみました。「ウンベルト・エーコ(Umberto Eco)は、厳密な意味では『神の存在を信じていた』わけではなく、伝統的な信仰者でも無神論者でもない、非常に独特な立場をとっていました。彼の考え方は、神学・記号論・哲学が複雑に絡み合ったもので、しばしば『不可知論的(アグノスティック)』と評されます。・・・(略)・・・まとめ:信仰というより思想 ▶幼少期は信仰的な環境 → しかし成人後は非信者、▶『神の存在』は証明不能としつつ、その『文化的役割』を重視、▶神学や記号論を通じて、神を『問い続ける』姿勢を維持、▶信じる/信じないではなく、『神をめぐる意味』を考察した思想家」という回答が即座に返ってきました。私の無神論に近いことを知り、エーコに親しみを感じるようになりました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較的若いときに読みました。 再読したいのですが、重いし、字が小さいし、高齢読書人には高いバリアーが聳えています。 ぜひ、読書バリアフリーに協力を。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較的若いときに読みました。 再読したいのですが、重いし、字が小さいし、高齢読書人には高いバリアーが聳えています。 ぜひ、読書バリアフリーに協力を。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| It was delivered as scheduled. The condition and quality is very good. | ||||
| ||||
|
| ||||
| The delivery was as scheduled. The condition and quality is very good. | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ちょっと分かりにくいところもあるけど!良い本‼️ | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 文庫を出して欲しい! 重い! ストーリーは少し難しいけど | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本書は中世からルネッサンスへと時代が移りつつある14世紀前半のヨーロッパが舞台となっている。 普遍的真理がイデアのように実在するという常識が揺らぎはじめ、普遍的真理/イデアと感じてきたものが実は「名前」のようなものであり、主観的概念に過ぎないという考え方(オッカムのウィリアムの唯名論)が広まりつつあった頃の「時代のゆらぎ」が描き出されている。 教皇庁は「真偽」や「善悪」が文脈によって変わりうることに多くの人が気づき始め、それが権力闘争に結びつくことを怖れる。そして、時代の流れに逆らって神の真理の一義性を守ろうとする。それが異端審問や魔女狩りの流行といった、時代に逆行する社会現象として顕在化する。 それに対して、主人公のバスカヴィルのウィリアムは、どの文脈が「真理」になるかをあらかじめ決めることはできず、事実に基づき仮説検証で決めるしかないという考え方を取る。この発想の転換が、後のヨーロッパの科学革命、産業革命へと繋がっていった。なぜヨーロッパで産業革命が起こったのか。その起源を覗き見ているような印象を受けた。 また、著者のウンベルト・エーコは記号論の学者でもある。記号に文脈が与えられた瞬間、自己と世界との関係が定まる。それが事実に裏づけられて安定するのか、幻影に終わるのか、あるいは笑いを生むのかは本人にも分からない。そんな記号と自己との関係が巧みに描き出されているようにも感じた。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 『薔薇の名前』を読むには予備知識が必要だとよく言われるが、そんなことは無いと思う。この小説を本当の意味で楽しむために必要なのは実のところ哲学的な論理の感覚ではないか。あえてもう一つあげるならこの時代の人たちがいかに真剣に神の存在を追い求めていたかを知ることだろう。 上巻の327〜329ページに集約されている。 平信徒たちは教会の御用学者たちの真実より切実な真実(真の神へと至る道)を直観で見抜いている。では個々人の直観が唯一の善であるとき、どのようにして学問は普遍的な規則を再構成できる(真実を大衆に敷衍するものが学問であるゆえ)域にまで到達できるだろうか。とウィリアムは疑問を投げかける。 ウィリアムが薫陶を受けた哲学者ベーコンは科学によって人々は導かれなければならないと説いている。 ベーコンの命題はある種の薬草を用いると熱が下がる、ある種のレンズを用いると視力が上がる、といった種類の、いわば条件(事物)について語っており、一方ウィリアムは自分は事物を語っているのではなくて事物の命題について語っていると言う。 つまり、そのベーコンの命題そのものについて命題を立てようとしている(立てないわけにはいかない)ということだ。さらに言うと、ある種の薬草を用いると熱が下がる、ある種のレンズを用いると視力が上がる、という規則はなぜそのような形で存在しているのか? ということになる。それを命題として成立させるには、「いるのか?」という疑問形ではなく、規則は普遍的であると言い切ってしまわなければならない。しかし、規則を普遍的なものとするや、事物によって与えられた秩序に、神でさえ虜になってしまっていることをも含んでしまう。しかし、神は世界を別のものへ変えることもできるはずだ。と、ウィリアム。 我々に置き換えてざっくり言うと物理法則を承知して日常を送っているが(ペンを離すと落ちるなど)神がなぜそのような物理法則で世界を作ったのかはわからないということだ。 ウィリアムは当然神を信じその絶対的なことをも信じているので神であればペンを離すと上に飛んでいくような世界も創造できたはずだ、というところだろう。 弟子のアドソは「では、あなたは行動し、なぜ行動するかは知っているが、自分が行動することを知っているとなぜ知っているのかは知らないとおっしゃるのですね」とウィリアムに言う。 最初の「では、あなたは行動し、なぜ行動するかは知っているが」とはベーコンのいう命題をウィリアムが承知していることを意味し、「自分が行動することを知っているとなぜ知っているのかは知らない」はウィリアムが自身の命題を立てられていないことを示している。 規則がそうなってる(レンズで視力が上がる)ことを知っているからメガネを作ってもらうという行動をするけれど、なぜそうなってるかを、神がなぜそうしたかをウィリアムは知らないということだ。 科学を普遍的なものとして行動したり、平信徒に教え広めてはいくものの、ウィリアムはそれに不安を感じているのだ。なぜならそれは普遍的な規則ではなく神がいつでも変えられる規則のはずであるから。科学においても博識な宗教家のジレンマを抱えているのである。 科学の規則が普遍的なものだと説けば神の力が弱まる、逆に神を絶対とすれば科学的な普遍性を説けなくなる。 さて、謎多き人物ホルヘは、真実を伝える書物に滑稽な装飾を施すのはもってのほかだという考えを持っている。 一方ウィリアムは最も歪められた事物を介してのみ神は示されると言う。 神の真理へ辿り着くことにおいて笑いは邪魔なものだとするホルヘと、笑いもまた必要だとするウィリアム。 ホルヘは喜劇を扱ったアリストテレスの『詩学 第二部』の存在を否定する。存在を知っているのにもかかわらず否定する。 自分にとって都合良く神のイメージを変え、それを守るため「学問・真実を歪め、隠そうとするもの」と、ウィリアムのように神のイメージが、そのことによってたとえ揺らごうとも「学問・真実を追求、究明しようとするもの」。 この対立構造がミクロからマクロまで物語全体を形作っている。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「記号論学者ウンベルト・エーコ」による歴史ミステリー。本書では、“教皇ヨハネス22世とフランチェスコ修道会の「清貧論争」をめぐる対立”という歴史小説に、「迷宮構造をもつ文書館を備えた、中世(後期)北イタリアの僧院で「ヨハネ黙示録」に従った連続殺人が」――というミステリーが組み込まれている。 教皇とフランチェスコ修道会の対立を仲裁しようと、ベネディクト修道会に属する僧院の院長アッボーネは、教皇庁の僧侶たちとフランチェスコ修道会を代表する修道士たちとの話し合いの場として、自らの僧院を使うことを提案した。しかし、客人たちが到着する前に、僧院で不審死をとげた若い修道士の遺体が発見される。困惑した院長は、いち早く到着したフランチェスコ修道会の修道士ウィリアムの怜悧な才に期待して、事件の調査を依頼するのだが――というストーリー。物語の舞台が山上に城塞のようにそびえ立つ僧院であるため、具体的なセリフを語る登場人物はキリスト教の僧侶だけという特殊な設定なのだが、“様々な思想や政治的な背景を持つ僧侶たちが一堂に会する”というフィクションのストーリーを展開することによって、中世後期のキリスト教会の精神的な荒廃と苦悩が鮮明に描き出されている。 本書でテーマの一つとなっている「清貧論争」は、教皇ヨハネス22世(在位1316~1334)が、フランチェスコ会(1209年にアッシジのフランチェスコによって設立されたカトリックの修道会。清貧と(民衆に対して積極的に語りかける)説教を中核とする)に敵対的な態度で臨んだ一連の出来事のことである。フランチェスコ会の中でも先鋭的な「厳格主義派」は、富裕になじんだ修道会の現状に批判的であり、聖フランチェスコの(清貧の)精神に帰るべきである、と説いた。それに対して、フランチェスコ会のコンベントゥアル派は、僧侶は(修道院の持つ広大な領地からの収入や信者たちの寄進(特に“商人の天国行きは難しい”と言われていたため、自らの死後に教会に多額の寄進をするように遺言する都市のブルジョワたちが多かった)などの)物を“所有”しているのではなく“使用”しているだけなのであるから修道院の財産までは問題視しなくてもよい、という教皇庁の見解に妥協的な態度をとった。ヨハネス22世は、当初はコンベントゥアル派を支持し、「厳格主義派」を「異端」として断罪したが、次第にコンベントゥアル派にも敵対的になった。と、いうのも(教皇の権力増進を苦々しく思っていた)ドイツ皇帝や貴族などの世俗の権力や一部のインテリが、“フランチェスコ会の「清貧」をめぐる議論は、教皇の権力と財力を抑制するために使える”と見なしたからである。このように、教皇とフランチェスコ会の反目が、世俗権力を巻き込んで紛糾していたさなかである1327年が、本書の舞台である。翌年の1328年には、フランチェスコ会の総長ミケーレ(本書に登場する)と教皇の話し合いは決裂し、教皇はフランチェスコ会に認めていた数々の特権を剥奪する。総長ミケーレは皇帝ルートヴィヒ4世のもとに亡命するが、フランチェスコ会自体はカトリック教会の中に残るのである。このような、教会内部や王侯貴族との争いは、教皇ヨハネス22世以前からあり、民衆にもその争いが飛び火するのは中世では珍しいことではない。本書の事件に尾を引く「ドルチーノ派」は、フランチェスコ会の「厳格主義派」の主張を巧みに取り入れたドルチーノという「とても頭の切れる若者」が説教で民衆(主に都市や農村の貧しい人々)の支持を得てイタリアで結成した団体であり、最終的には暴徒(近隣の領主の土地を襲ったりした)と化した「異端」として、教皇クレメンス5世(在位1305~1314)が呼びかけた「十字軍(異教徒との戦い、だけでなく「異端」の討伐にもこの語はたびたび使用された)」によって滅ぼされるのである。 本書の探偵役はフランチェスコ会の修道士であるバスカヴィルのウィリアムと、この事件の語り手でありウィリアムを「師」と仰ぐ「見習修道士」のアドソである。初老のウィリアムは以前は異端審問官(中世後期には、教皇の直属機関であり、宗教裁判の全般(取り調べから判決まで)を取り仕切る。宗教裁判は、容疑者の自白が採用され拷問が行われることも多々あったため、恐れられた)をしていた(「冷徹さにおいて高名を馳せていたが大いなる慈悲心に欠けた例がなかった」という評判だった)が、とうに辞めて「自然」研究や「機械類」に関心を示している人物である。青年のアドソは、年頃らしく多感で好奇心旺盛であり、気持ちではまだ僧侶になりきれていない。事件を追及するウィリアムと行動する過程で、修道僧たちの腐敗ぶりを知り、農村の「娘」に恋心を抱いてしまい、異端審問の理不尽さを目撃し、そのたびにアドソは精神的に動揺する。しかし、ウィリアムは“目指すべき聖職者のあり方”については指針を示してやることはできない(人間味あふれる大人の対応や忠告はしてくれるのだが)。異端審問官という教皇庁の組織を辞めフランチェスコ修道会の組織からも身を引いた態度をとる(フランチェスコ会の修道士としての義務は果たしているが)ウィリアムは、近代科学に通じる合理主義的な考え方をする人間であり、キリスト教に関しては“良心を担保するもの”という以上の態度はとれなくなっているのである。 ウィリアムとアドソが訪れた修道院は、そこの聖堂に彫刻された悪徳である「淫乱(色欲)」「大食(暴食)」「傲慢(尊大)」「貪欲」がはびこり腐敗しており、もう一方の教皇庁は(教皇と皇帝とフランチェスコ会との)権力闘争の場と化している。ウィリアムが闘うのは、修道院の連続殺人(自殺に追い込むことも含む)の裏で糸を引いている犯人と、今回の会合を台無しにし、ついでにフランチェスコ会にとっての不利な証拠(でっち上げであったとしても、それらしく見えるものならよい)を手に入れるという教皇からの密命を帯びた異端審問官ベルナール・ギー(ドミニコ会の修道士)の二人である。 とはいえ、ウィリアムとアドソに出来るのは、悪を打ち破ることではなく、犯人とベルナール・ギーの手口を明らかにし、“修道院の中での心理的な争点(知識(文書館)へのアクセスの特権化)”や“教皇庁での社会的な争点(異端審問を利用した権力闘争)”を浮かび上がらせることしかできないのである。しかし、そうではあっても本書の「最後の紙片」でその後の経緯(教皇ヨハネス22世の勝利と、皇帝ルートヴィヒ4世とフランチェスコ会総長ミケーレの敗北)を読むと、それぞれに己の信念を生きることができたウィリアムとアドソは、良心的な聖職者にとっては難しい時代にありながら見事な生涯を送ったのだと思える。 と、いうように、本書はあらすじをなぞるだけでも面白く読めるが、一方で言及される出来事・人名・語句だけでも中世の社会・宗教・文化などの百科のような本でもある。このようなエーコの仕組んだ中世の迷宮をさまよいながら読むのも、この本の楽しみであるだろう。そういう点で、『エーコ 『薔薇の名前』 迷宮をめぐる<はてしない物語>』という本も興味深かった。他にも解説本があるようなので、ぜひ読んでみたいと思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この有名な小説をやっと読むに至りましたが今で良かったです。もっと前なら今よりもっとちんぷんかんぷんだったろう。中世を舞台にした修道院での殺人事件の究明、という形ではありますが、世界史の本で暗黒時代、異端裁判、魔女裁判、ローマ教皇(この時期はアヴィニヨン)、と言った言葉だけで習ったことが、今自分も真にその中にいるかのように詳しく描写されて、本当に大変なすごい時代で、ここまでの価値観からよく、現在の人権とかそういう価値観にまでイタリア、変化できたなー、と思うほどの下層民が生きていくの大変な時代です。 また、原作者エーコ氏は記号論、言葉ということの権威という事ですが、書物についての色々なことが出てきます。14世紀はもうすでにアラビアでもヨーロッパでもたくさん思想的あるいは自然科学的書物が書かれており、そもそも紀元前からギリシャで今でも通用するような高尚な思考が論じられ書物になっていたわけですから(思えばそういうのがよく今でも読まれる形であるものだなー、と改めて感心してしまうわけですが)、それらを貴重な叡智として蔵書とするために延々と写本していたわけですよね! 今、ネットですぐ例えばアリストテレスの著作を誰でも購入することができると思うと、なんとなんと恵まれた時代なのでしょう!と感謝せずにはいられません・・・ とにかく中世ヨーロッパに知的興味を持つものには大変興味深い世界が展開されており、主人公たちの好感の持てるキャラクターのせいで、暗黒時代ではありますが何かしらの希望をもって読み進むことができます。 この本には様々な知的引用が取り入れられているらしくて、もっともっとヨーロッパやイタリアに詳しい人の参考書も読んで、深く勉強したくなる本です。エーコ氏が当時文壇的に?モラヴィアやパゾリーニと反する立場のようであったことなども、興味深くさらに勉強したいところです。イタリアという歴史深く知的な国の知的な歴史とその思想的変遷を、日本にいては積極的に勉強しなければ全然わかりえないと思うので、知的意欲をそそられる本だと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| とうとう読み終えた「薔薇の名前」。これまでも何度か読む機会はあったのだが。 最初は1983年ごろだろうか、職場の休息室で、週刊誌「Time」をひろげていて、そのbook reviewで、この作品の名前と概略を初めて知る。でも買わなかった。 次は、1987年ロンドンに住んでいた時に、chelseaで映画を見たとき。映画では英語がよくわからなかったのだが、なんとか概略だけはつかめたので、さっそく原著を購入。表紙のページには1987年3月と記されている。hatchardsで買ったような記憶がある。 ただ、頻発するラテン語や最初の部分の込み入った仕掛けのせいだろうか、読み始めて、すぐ自分の手におえる作品ではないと確認。当時は、last resortとしての翻訳もまだなかった記憶がある。その後は本棚での長い長い冬眠となる。時折取り出して、トイレでの時間つぶしに目を通してみるのだが、とてもじゃないが、読もうという気にはならなかった。 今回、英訳を主にして読んだのだが、日本語で読んでも問題なし。日本語の翻訳自体が大変な労作であることには疑いがない。さらには、もともとの本作品の由来自体が、ラテン語で書かれた作品がフランス語に訳され、それをエコ自身が口語のイタリア語に直したという二重三重のふるいをかけた設定になっているわけで、このどの訳を読もうが、それ自体にあまり意味はない仕掛けになっているのだ。 また、全編、引用並びに借用で成り立っている作品。引用・借用元を探し始めると、ページは進まない。この永遠の循環運動に入り込むこと自体には、それなりの面白さはあるのだろうが、終わりが来ないのだ。どの程度、この知的暇つぶしに付き合うのかは、読者しだいということになる。 ミステリーとして読むと失望する読者もいるだろう。いわゆるミステリーの紳士協定というかルールは徹底的に無視されて、ホームズ役のウィリアムの役回りも、断片としての謎の解読にとどまっており、全体を通してみるとピエロの役回りなのだ。ただ、断片としての謎の解読も、弟子アドソの何気ない直観に依拠することが多く、密室や迷路さらには暗号の謎の解読もいちおう説明はされているのだが、どうもわかり難い。僕にとっては、ウイリアムは名探偵というより、近代の啓蒙主義の直前で、立ち尽くす最後の中世人の姿。その当人の足場は中世と近代の双方に引き裂かれ始めている。 「ヨハネの黙示録」や「正統・異端論争」「異端審問」「教権と俗権」などの本書のモチーフだが、どれも事件そのものの解明には直接の関係はない。あくまでも、場の雰囲気を盛り上げるため、さらにはページを稼ぐための小道具なのだ。この小道具にどの程度共感というか感情移入が出来るかがカギとなる。 とはいえ雰囲気に接近するために、ネットでサーチをかけ始めると、泥沼に入り込んでしまう。どこかで割り切らないと。というわけで、読者を選ぶ作品であることは間違いない。ただこの日本語訳、いまだに文庫化されていないのだ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| "写字室の中は冷えきっていて、親指が痛む。この手記を残そうとはしているが、誰のためになるのかわからないし、何をめぐって書いているのかも、私にはもうわからない〈過ギニシ薔薇ハタダ名前ノミ、虚シキソノ名ガ今ニ残レリ〉。"1980年発表の本書はイタリアの記号論大家による映画化もされた世界的ベストセラーにして、7日間の重層的な擬似枠物語。 個人的には主宰する読書会の課題図書として、分厚さと情報量の多さから積読したままになっていた本書をようやく手にとりました。 さて、そんな本書は老僧アドソが【見習い修道士であったころの見聞を回想している】という形式を外枠に、イタリアのボッカチオ、10日物語『デカメロン』に代表される枠物語として内部には名うてのシャーロキアンでもあった著者によって、ネーミングから完全にホームズとワトソンを連想させられるバスカヴィルのウィリアム修道士と見習い修道士にして語り部役のアドソが修道院の連続殺人事件の謎を追いかける【7日間のミステリー小説】が収められているわけですが。 まず、とは言え"中世時代のミステリーでしょ?"と気軽な気持ちで読み始めて圧倒されてしまうのは、直接的な殺人事件の謎解きというよりは背景となる【ローマ・アヴィニョン軸の教皇とドイツ・神聖ローマ帝国による世俗的な権力を巡る争い】が作中の様々な立場を持つ登場人物たちの宗教、歴史、哲学など【膨大な情報量に溢れた会話としてあらわれている】部分で、正直に言うと上巻の時点で勉強不足な私は早くも挫折しそうになりました(下巻からスピードアップ?するので、何とか読み終えることはできましたが) 一方で、では難解な本か?と言われると(未鑑賞なのですが)映画ではウィリアムとアドソをそれぞれ、ショーン・コネリーとクリスチャン・スレーターが演じた姿を頭に浮かべながら、宗教論争をすっ飛ばして【閉じられた舞台(僧院)での本格ミステリー】としても十分にエンタメ作として感情移入して楽しめるわけで。 個人的には、それぞれに細密画家や古典翻訳、薬草やガラス係といった担当を持ち、僧院自体が文化サロン的役割を担っている所は京都在住の私は【天龍寺の五山文学界隈みたいなイメージを連想し】またウィリアム含め本を追い求める姿にはルネサンス黎明(れいめい)期のイタリアで写本を見つけ出し、それを正確に筆写するブックハンターの姿を描いた【『一四一七年、その一冊がすべてを変えた』(スティーヴン・グリーンブラット著)を直接的に思い出して】勝手に補完しながら楽しませていただきました。 重層的なレイヤーが込められた作品なので、読み手の眺め方によって、また年齢によっても感じ方が変わる本なので。何度か読み直すことになりそうな一冊。ミステリー好きはもちろん、中世や宗教論争といった文化や歴史に興味ある方にもオススメです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| "写字室の中は冷えきっていて、親指が痛む。この手記を残そうとはしているが、誰のためになるのかわからないし、何をめぐって書いているのかも、私にはもうわからない〈過ギニシ薔薇ハタダ名前ノミ、虚シキソノ名ガ今ニ残レリ〉。"1980年発表の本書はイタリアの記号論大家による映画化もされた世界的ベストセラーにして、7日間の重層的な擬似枠物語。 個人的には主宰する読書会の課題図書として、分厚さと情報量の多さから積読したままになっていた本書をようやく手にとりました。 さて、そんな本書は老僧アドソが【見習い修道士であったころの見聞を回想している】という形式を外枠に、イタリアのボッカチオ、10日物語『デカメロン』に代表される枠物語として内部には名うてのシャーロキアンでもあった著者によって、ネーミングから完全にホームズとワトソンを連想させられるバスカヴィルのウィリアム修道士と見習い修道士にして語り部役のアドソが修道院の連続殺人事件の謎を追いかける【7日間のミステリー小説】が収められているわけですが。 まず、とは言え"中世時代のミステリーでしょ?"と気軽な気持ちで読み始めて圧倒されてしまうのは、直接的な殺人事件の謎解きというよりは背景となる【ローマ・アヴィニョン軸の教皇とドイツ・神聖ローマ帝国による世俗的な権力を巡る争い】が作中の様々な立場を持つ登場人物たちの宗教、歴史、哲学など【膨大な情報量に溢れた会話としてあらわれている】部分で、正直に言うと上巻の時点で勉強不足な私は早くも挫折しそうになりました(下巻からスピードアップ?するので、何とか読み終えることはできましたが) 一方で、では難解な本か?と言われると(未鑑賞なのですが)映画ではウィリアムとアドソをそれぞれ、ショーン・コネリーとクリスチャン・スレーターが演じた姿を頭に浮かべながら、宗教論争をすっ飛ばして【閉じられた舞台(僧院)での本格ミステリー】としても十分にエンタメ作として感情移入して楽しめるわけで。 個人的には、それぞれに細密画家や古典翻訳、薬草やガラス係といった担当を持ち、僧院自体が文化サロン的役割を担っている所は京都在住の私は【天龍寺の五山文学界隈みたいなイメージを連想し】またウィリアム含め本を追い求める姿にはルネサンス黎明(れいめい)期のイタリアで写本を見つけ出し、それを正確に筆写するブックハンターの姿を描いた【『一四一七年、その一冊がすべてを変えた』(スティーヴン・グリーンブラット著)を直接的に思い出して】勝手に補完しながら楽しませていただきました。 重層的なレイヤーが込められた作品なので、読み手の眺め方によって、また年齢によっても感じ方が変わる本なので。何度か読み直すことになりそうな一冊。ミステリー好きはもちろん、中世や宗教論争といった文化や歴史に興味ある方にもオススメです。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!

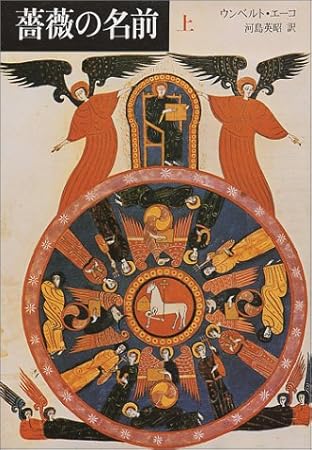



![薔薇の名前[完全版] 上 (海外文学セレクション)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51u3X3o71BL._SL500_._SL450_.jpg)
![薔薇の名前[完全版] 下 (海外文学セレクション)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51rmxbj67JL._SL500_._SL450_.jpg)
