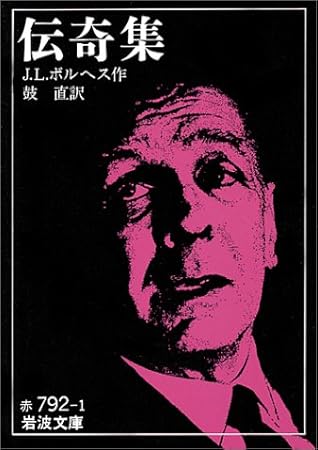■スポンサードリンク
(短編集)
伝奇集
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
伝奇集の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.12pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全41件 1~20 1/3ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ボルヘスの愛読者なら、必読の本。ボルヘス思想のエッセンスが集結した作品。国書刊行会で「バベルの図書館」のシリーズが出て、すべて読んだけれど、「バベルの図書館」という構想はこの作品集に収録された短編に由来するんだね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| きょうから寝るまえの読書は、ボルヘスの短篇集『伝奇集』にしよう。むかし、同志社国際高校に嘱託講師で行ってたときに、図書室で「エル・アレフ」や「汚辱の世界史」といっしょに入っていた集英社から出てたラテンアメリカの文学1『伝奇集』を借りて読んだ記憶がある。いま、目次を見て思い出せるのは、「円環の廃墟」のみだが、というのも、ジュディス・メリル編集の 『年刊SF傑作選6』や、河出文庫の『ラテンアメリカ怪談集』にも載ってて、何度も読み直してるからだけれど、ほかのも、おもしろいかな、どだろ。純文学もときどき挟み込まないと、脳みそがSF脳や怪奇ものの脳になってしまいそうなので。 ボルヘスの『伝奇集』は2部仕立てで、その第1部は「八岐の園」で、プロローグは8篇からなることを告げている。 1篇目は、「トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス」トレーンという架空の惑星の百科事典の話。 2篇目は、「アル・ムターシムを求めて」このタイトルの小説について書かれている。むかし読んで印象に強く残っていた言葉があった。「今日の書物が遠い昔のものに由来するのは名誉なことだと思われる。なぜならば、同時代の人間に負い目があるということは、(ジョンソンもいったとおり)何人にとっても好ましくないからだ。」(鼓 直訳)そういえば、この篇には、むかし、ぼくが書いた作品に引用した言葉もあった。「一月十日の」という言葉も引用した。二度、文面に出てくる。引用したのは、それが、ぼくの誕生日だからだ。 3篇目は、「『ドン・キホーテ』の著者、ピエール・メナール」メナールが書いた『ドン・キホーテ』の話。 4篇目は、「円環の廃墟」男は夢見ることでひとりの人間をつくりだした。ところが、男が火に囲まれて悟ったのは、自分もまた、誰かが夢見てつくられた人間であったということ。 5篇目は、「バビロニアのくじ」バビロニアではくじが絶対的であると言う。 6篇目は、「ハーバート・クレインの物語の検討」タイトル通りの作品である。原注にある、次の言葉が印章的である。「より興味を引くのは、「時間」の逆行を想像することである。その状態のなかでは、われわれは未来を記憶しているが、過去は知らないか、かすかに予感するだけである。」(鼓 直訳) 7篇目は、「バベルの図書館」無限の数の本を有する図書館。じっさいは有限の数の本を有する図書館。これも原注におもしろい記述が見られる。「いかなる本も同時に階段ではない。おそらく、その可能性を論じ、否定し、証明する本があり、構造が階段のそれに対応しているべつの本が存在するにちがいないが。」(鼓 直訳) 第1部のさいごの8篇目は、「八岐の園」時間を超克した本であり迷路でもある「八岐の園」という本があり、その本を書いた者の子孫が主人公であるが、原注を読むと、子孫ではなさそうである。主人公はスパイだった。殺された。 ボルヘスの『伝奇集』の第2部は、『工匠集』というもので、「プロローグ」を除いて、9篇が収められている。「プロローグ」では、その9篇について軽く述べている。 1篇目は、「記憶の人、フネス」フネスは驚異的な記憶力を持っていた。見たことだけではなく、読んだものや、頭の中に思い浮かんだことなんかもすべて記憶していた。 2篇目は、「刀の形」額から頬にかけて刀の傷の痕のある男の話。詩論に使えそうな言葉があった。「一人の人間のすることは、いってみれば万人のすることです。ですから、ある庭園で行われた反逆が全人類の恥となっても、おかしくはないわけです。また、一人のユダヤ人の磔刑が全人類を救っても、決しておかしくはないのです。ショーペンハウアーのいったとおりだと思いますよ。わたしはべつの人間たちであり、どの人間もすべての人間であって、シェイクスピアは、ある意味で、卑劣なジョン・ヴィンセント・ムーンなのです。」(鼓 直訳)主人公の男に、刀の傷のある男が、刀の傷を負った日のいきさつを語る。仲間を裏切ってつけられたのであると告げる。 3篇目は、「裏切り者と英雄のテーマ」アイルランドの一人の英雄がじつは裏切り者であったという話。その話を劇にして本にして、という話。劇は登場人物が全市の大集団である。 4篇目は、「円とコンパス」推理小説仕立ての物語。 5篇目は、「隠れた奇跡」ユダヤ人の作家がナチスに捕まって銃殺刑になる話。奇跡とは、作家が死のまえに神にあと一年ほしいと願った願いが銃殺される寸前に起こったことである。周囲の時間がとまっていたそのあいだに、作家は、自分の詩劇の詩を推敲していた。推敲が終わったときに時間がもとの瞬間に戻り、作家は銃殺されて死んだ。 6篇目は、「ユダについての三つの解釈」イエスを売った売り切り者としてのユダ。イエスの神性を増すためにイエスを裏切ったユダ。そして、イエスがユダになったのだとする説。 7篇目は、「結末」7年まえに弟を殺された黒人が、殺した相手と決闘して勝つという話。詩論に引用できるというか、実作でも応用して使えそうな言葉があった。「平原が何かを語りかけようとする夕暮れのひとときがある。だが、それは決して語らない。いや、おそらく無限に語りつづけているのに、われわれが理解できないのだ。」(鼓 直訳) 8篇目は、「フェニックス宗」印象に残った言葉を引用する。「ハズリットの限定されざるシェイクスピアのように、彼らが世の中のすべての人間に似ているという事実である。」(鼓 直訳)この物語は、あらゆる国においてフェニックス宗の教徒がいるが、彼らは自分たちがそういう名前の宗派であるとは思っていないということである。 第2部のさいごの9篇目は、「南部」居酒屋で決闘を挑まれた主人公。外に二人で出ていくところで終わる。この作品のなかに、詩論に使える言葉があった。「瞬間の永遠性」(鼓 直訳) | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 中途失明者であるボルヘスの世界の認識のあり方が、繰り返し記述されている。私は1994年に初読したがその時には理解できなかったことが読み取れるようになっていた。 「ドン・キホーテの著者ピエール・メナール」に登場するメナールとはボルヘス自身である。メナールはドン・キホーテそのものを書こうとする 「ミゲル・デ=セルバンテスのそれとー単語と単語が、行と行がー一致するようなページを産み出すことだった。」(59ページ) 晴眼者だった頃のボルヘスはドン・キホーテの作品の一部を容易に書き写すことができていたが、視覚が機能しなくなってしまっている作家のボルヘスにはドン・キホーテの作品の一部を書き写すことができなくなっている。しかし、それでも作家のボルヘスが万年筆を持って原稿用紙の上でペン先を動かしドン・キホーテの一部を記述することができていたとすれば奇跡である。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 少しこなれていない感じの訳文がかえって良いと感じる箇所もあり、読み比べるのが楽しいです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ボルヘス作の「ユダについての三つの解釈」を読みたくて、本書『伝奇集』を購入しました。 「ユダについての三つの解釈」は、たった9頁の短い「エッセー」(214頁)でした。 ユダについて、ニールス・ルーネベルクによる書『キリストかユダか』(1904年)、 および彼の主著『秘密の救世主』(1909年)に基づいて、ボルヘス流に解釈しています。 「下位の秩序は上位の秩序の鏡である」(216頁) 「ユダはある意味でイエスの写しである」(216頁) 「神言は人間に身を落とされた。神言の弟子であるユダも身を落として密告者となり」(216頁) イエス・キリストが人間になったとき、 キリストの弟子であるユダは、最低の人間、罪深き人間、裏切り者、密告者になったと、 ボルヘスは解釈しました。 「ユダが使徒の一人であったことや、天国の到来を告げ、病人を治し、癩病患者を清め、死者を蘇らせ、悪魔を追い払うためにえらばれた者であった」(217頁) 「救い主がこのように特別扱いされた男は、その行為についてわれわれの最良の解釈を受ける価値がある」(217頁) ここまでは、ボルヘス流の解釈に問題はありません。 「主の至福で十分だったからこそ、ユダは地獄を求めた」(218頁) ユダは「名誉、善、平和、天国を捨てた」(217頁) ここがボルヘス流解釈の問題点です。 地獄を求め、名誉、善、平和、天国を捨てるような人間なんていない と信じてきました。 悪い夢を見ている気分です。 ボルヘスの解釈は続きます。 「神は人類を救うために身を落として人間となられた、神によって行われた犠牲は完全であって、遺漏によって効果を失ったり弱められたりすることはないと推測し得る、とニールス・ルーネベルクは言う。神が耐えられたことを十字架上の夕べの苦悶に限定するのは不敬の沙汰である」(218頁) 神は人間の全ての汚辱と地獄に耐えた、とボルヘスは言っているのです。 「神は完全に人間となり、汚辱を経験せられた。人間となり、批難と地獄を経験せられた。われわれを救うためには、当惑すべき歴史の網目を織りあげる運命の任意のものをえらぶことができた。アレクサンドロスか、ピタゴラスか、ルーリック(7)か、イエスになることができた。ところが最悪の運命をえらび取った。ユダになられたのである」(219頁) 人間となった神は、イエスになることをえらばず、ユダになられた。 保守的少数派のボルヘスらしい解釈です。 なお、この「ルーリック(7)」という人物は知らなかったので、訳注を読んでみました。 驚きました。ルーリックは、ロシア王朝の創始者なのでした。 「ルーリック(7)」 「九世紀のなかばの神話的なヴァイキングの王で、1598年までロシアを治めた王朝の創始者。内紛を鎮めるようノヴゴロドの住民に要請されて、スカンディナヴィアから赴いたと考えられている」(259頁) ヴァイキングの血が流れる人間について、もっと知りたい。 地獄を求め、名誉、善、平和、天国を捨てるような人たちについても。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本書は「世にも奇妙な」物語のようで、舞台は覗き込まれている「何か」、そして、 覗き込まれているものは何か<ゲームなるもの>をしている。 ——偶然の投入/シンメトリー・恣意的なルール・単調/逆行・分岐—— 回数は無限「亀との競争」/時間が無限に細分できればそれでたりるのだ ——くじびきは怪奇的な出来事・事件であるようにも見えてくる。 「余の八岐の園」と隠退迷路からの余の回数は、 極のくじびき回数とのシンメトリー(=断末魔)につながっているようで、 ・(~)が虚妄であることを証明するには、ただ一塊の「反復」で充分である ・「チェスが解答である謎かけの場合、唯一の禁句は何だと思いますか」 「(~)ということばでしょう」 ・ある語をつねに省略し、不適切な暗喩や分かり切った迂言法にたよるというのが(~) ・(~)を意味することばさえつかわれていない ・ここから例の小説の矛盾は生まれるのです ・見つけると失うという動詞は循環論法の誤りをともなっている/教祖・イコン (実質・即自・同一性の消滅/形相化) 殉教への誘惑に駆られながらの晩年のボルヘスさんとは対照的、といったものが本書の印象であり、 ニーチェやショーペンハウアーのそれを思わせるような内容ではあった。 ------------------------------------------------------------------------------------ 八岐の園(プロローグ) トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス アル・ムターシムを求めて 『ドン・キホーテ』の著者、ピエール・メナール 円環の廃墟 バビロンのくじ ハーバート・クエインの作品の検討 バベルの図書館 工匠集(プロローグ) 記憶の人フネス 刀の形 裏切り者と英雄のテーマ 死とコンパス 隠れた奇跡 ユダについての3つの解釈 結末 フェニックス宗 南部 ------------------------------------------------------------------------------------ (_物語) ・その多くの本が不安定な本が他の本に変わるという危険にさらされていて 錯乱した(~)のように一切を肯定し、否定し、混同する(~) ・図書館は、その厳密な中心が恣意的な(~)その円周は到達の不可能な球体である ------------------------------------------------------------------------------------ ・<反復>のアンソロジー ・<瞬間>のアンソロジー ・(~)われわれはわれわれの存在自体に虚構性がある ------------------------------------------------------------------------------------ (_円環の廃墟) ・地上の円環は遊戯の鏡である「」 ・時間が虚妄であることを証明するには、ただ一塊の「反復」で充分である ・すでに彼はあらゆる人間と同じように、盲人、啞者、痴愚、記憶喪失者だった (「余の八岐(やまた)の園」隠退迷路) ・「チェスが解答である謎かけの場合、唯一の禁句は何だと思いますか。」 「(~)ということばでしょう」 ・ある語をつねに省略し、不適切な暗喩や分かり切った迂言法にたよるというのが(~) ・(~)を意味することばさえつかわれていない ・ここから例の小説の矛盾は生まれるのです ・余はさまざまな未来—余の八岐 (_移) ・あらゆるゲームの本質的な特徴、シンメトリー、恣意的なルール、単調さなどを復権させた ・偶然の投入/逆行・分岐/くじびき/出来事・事件 ・くじびきの階数は無限である/「亀との競争」/時間が無限に細分できればそれでたりるのだ ・時間ということば(135) ・砂、ミスラ的 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 知り合いに進められて購入しました。 情景が全く想像できないけど、説明不足なだけな気がする。 「もしかしてこういうことか?」って思ったら、すごくしょうもない気分になりました。 内容について別の解釈を持ってる方や正解を知ってるひととは違う可能性はかなり高いと思います。 ただ自分にはこのタイプは合いませんでした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 現実世界と異世界を自由に行き来し、この世であってこの世でない世界が広がる。ボルヘスが読める人になりたい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 私には難しかったです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| いつもバッグに入れているのですぐボロボロになります。5回目の購入です。それ位愛読しています。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読んでみました | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| . ボルヘスという作家は、「読書家に憑く」という性格を持っているようだ。 その極端なまでに「肉質」を欠いた抽象性は、ふわふわとした「世俗的な夢」や「物語性」といった「生活世界の肉」を削ぎ落として、ストイックに錬成された重金属製のオブジェのごときものである。 「書物」「迷宮」「図書館」「螺旋」「宇宙」「幾何」「象徴」「薔薇」「神学」「異端」「探偵小説」あるいは「無法者」。それらは、私たちの有する雑味の多い「日常生活」とはまったく異質であり、縁遠いものと感じられるからこそ、私たちはそこに魅せられる。 「書物」だってそうだ。それは「書物」であって、「本」という言い方は、適切ではない。まして「書籍」などという野暮な言い方では、「書物」というものの孕む「無限性」は、とうてい暗示し得ない。 「無法者」もまた、純化された存在であって、「犯罪者」などではない。「犯罪者」は、生活の中における逸脱者だが、「無法者」とはそもそも「生活」という概念を欠く、「人間」ではない何かであり、だからこそボルヘスも、それに憧れることができたのだ。畢竟「無法者」とは、抽象的な存在である。 同様に、私たちはボルヘスの「小説」を読んでいるのではなく、ボルヘスの暗示する「小説」を夢想することに喜びを感じているのだ。その秘儀に参与できる「選ばれたメンバー」としての「読書家」であることに、無上の喜びを覚える。 ボルヘスは、私たち「読書家」を、「書物」の彼方の世界へと導く、盲目の司祭なのだ。 じっさい、彼のキャラクターは、ウンベルト・エーコの原作小説を映画化したジャン=ジャック・アノー監督の『薔薇の名前』に登場する、フェオドール・シャリアピン・ジュニアが演ずるところの「盲目の修道院図書館長・ブルゴスのホルヘ」をはるかに凌駕して、魅力的だ。 もしも『伝奇集』の作者が、エーコのような「気の良さそうなおじさん」だったら、ボルヘスの魅力は、間違いなく半減するだろう。ボルヘスが作品を書いたのではなく、作品がボルヘスをボルヘスにしたという言い方も、あながち転倒したレトリックだとは言えないのではないだろうか。 ボルヘスという作家の作品が「難解」だという読者は多い。だが、その「難解」という言葉が「面白くない」ということを意味して発せられたものなのだとしたら、その読者は「ボルヘスの読者」ではない。ボルヘスとは「難解な書物」であり、その「難解さ」は、苦痛ではなく、喜びなのだ。 名探偵が「難解な謎」に舌なめずりするように、「ボルヘスの読者」は「ボルヘスという迷宮」に喜んで踏み込み、踏み迷い、そしてぞくぞくとした快感に背筋を震わせながら「道に迷っちまったじゃねえか!」と、小さく歓声をあげるのだ。 言うまでなく、「迷宮」は迷うためにあるのであり、迷わない迷宮は迷宮ではない。また、迷宮を首尾よく脱出してしまったら、そこにはもう「生活」世界しか待っていないのである。当然、私たちは、そこで回れ右をして、もう一度、迷宮へと戻っていくはずだ。 そして、ボルヘスの迷宮とは、踏み込むたびに姿を変える、何度でも迷える迷宮なのである。 . | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 篠田一士『伝奇集、エル・アルフ、汚辱の世界史』 ボルヘス、集英社「世界の文学」、1978 学生時代に夢中になって周囲にも勧めてみたが、だれも共感してくれずドン引きされた。とうの昔に絶版、忘却の彼方に去ったことすら誰も覚えていないと思っていたら、文庫やらなにやら一杯出てる。日本人というやつも案外話が分かるのかも。 若いころはご時世のせいでマルエン・レーニンに非ざれば人に非ずで、ルカーチだデュクタオだ星埜惇だと手を出して、サルトル・カミユに入れ込んだりした。理屈は全部飛んで、残ったのは小説とマンガ。無人島にもっていくのはドストエフスキーとボルヘスになった。 ボルヘスは笑える。ドストエフスキーも笑えるが、『白痴』みたいにたまにちょっぴりだ。ボルヘスは終始神妙な面持ちでボケまくるバスター・キートンみたいなもので堪らん。 全然、作品の感想がないじゃないかって?ボルヘスは「最初から作品の解説を書けばいい」ようなことを書いていた。「解説」の説明と感想を書くわけ? ふと見ると、訳者が違う。鼓直氏は『ブロディーの報告書』くらいしか持っていない。ここ20年ほど「晴チャリ雨ネット」化して、本とマンガがネタ切れ気味。買ってみるか。 追記…ひとまず持っていなさそうなのを4つ、古書で注文した。ブーム再来か? | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| それほど厚い本でもないし、多少難解でも読めると思ったけれども、途中で挫折してしまった。 物語の意味がわからないだけでなく、そもそも文の意味がわかりづらい。日本語訳の問題なのか、元々の原文のせいなのか不明だが、訳者自身による巻末解説の文章を読むと、訳者の日本語文もわかりづらい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 私はじっくり時間をかけて読みました。 正直、前半の「八岐の園」は、最初からとっつきにくい。読みにくい。 でも、せいぜい短編なので、やっかいな哲学書に挑んでしまった時よりも救いがあります(笑) 有名な本のため、読書好きを「内心で」自称している身としては避けてはとおれないと思い、我慢して読みました。 一読してワケがわからない作品については、ネットに感想を書かれている方々の文章に助けてもらい、なんとか読了。 で、後半の比較的読みやすい「工匠集」を含めての感想は「読んで良かった。」でした。 ごく短いプロットが次々と提示されて、自分がSFや推理作家だったらネタの宝庫だと思う内容でした。 「八岐の園」の各短編ついても、咀嚼して(もしくは分からないまま受け入れて)いくうちに、余計な説明をそぎ落とした素っ気ない文体が「読みにくい」から「かっこいい」に自分の中で変りました。 独特な文体に慣れてくると味わいがあってとても良いです。 再読すると思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| "図書館は無限であり周期的である。どの方向でもよい、永遠の旅人がそこを横切ったとすると、彼は数世紀後に、おなじ書物が無秩序さでくり返し現れることを確認するだろう"1940年代発表の短編集である本書は、ラテンアメリカ文学の先駆けとして、あるいは【短い物語で根源的なテーマを描く】著者の魅力が詰まっています。 個人的には、或るトークイベントで本書に収録されている『バベルの図書館』の話になって、恥ずかしながら未読であった事から、ちんぷんかんぷんであった事(笑)また5月は図書館振興の月と、ソーシャルキャンペーン『#図書館に感謝 』を企画している立場として、読んでおかねば!と本書を手にとりました。 まず『バベルの図書館』に関しては『五つの書棚が六角の各壁に振りあてられ、書棚のひとつひとつにおなじ体裁の三十二冊の本がおさまっている。それぞれの本は四百十ページからなる』閉鎖的な図書館を舞台に世界や宇宙、永遠といった幾つもの読み方ができるのに驚きを超えて圧倒されました。(実際に映画『薔薇の名前』やポアンカレ予想、白熱教室にVRと多くの影響を知り、こちらも勉強になりました) また本書では『バベルの図書館』以外にもプロローグをのぞいて17の物語が収録されていますが。こちらはこちらで、図書館員と無法者、メスとナイフ、病院と酒場といった、一見対照的なシンメトリーさが伝わってきて(特に『南部』)それぞれに面白く。中では『円環の物語』夢そのものに没入させられる様な幻想的な神話性は私的に好みでした。 図書館好き、文学好きな誰かに。また『長大な作品を物するのは、数分間で語りつくせる着想を五百ページにわたって展開するのは、労のみ多くて功少ない狂気の沙汰である』そんな短編好きな誰かにオススメ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 思いの外難解で、まだ読破出来ていませんが挑戦しています。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 『伝奇集』(ホルヘ・ルイス・ボルヘス著、鼓直訳、岩波文庫)に収録されている『バベルの図書館』を読んだのですが、正直言って、迷宮に迷い込んだかのように頭がくらくらしてしまいました。 「書棚、謎めいた書物、旅人のための疲れることのない階段、腰おろす司書のための便所などの、優雅な基本財産をそなえた宇宙は、ある神の造られたものでしかありえないだろう。聖なるものと人間的なものをへだてる距離を知るためには、わたしの誤りを犯しがちな手が本の表紙に書きちらす、これらの震える粗雑な記号と、本のなかの有機的な文字とを比較すればたりる。後者は正確で、繊細で、鮮やかな黒で、まねのできないほど均斉がとれている」。 「ある天才的な司書が図書館の基本的な法則を発見した。この思想家のいうには、いかに多種多様であっても、すべての本は行間、ピリオド、コンマ、アルファベットの25字という、おなじ要素からなっていた。また彼は、すべての旅行者が確認するに至ったある事実を指摘した。広大な図書館に、おなじ本は2冊ない。彼はこの反論の余地のない前提から、図書館は全体的なもので、その書棚は二十数個の記号のあらゆる可能な組み合わせ――その数はきわめて厖大であるが無限ではない――を、換言すれば、あるゆる言語で表現可能なもののいっさいをふくんでいると推論した。いっさいとは、未来の詳細な歴史、熾天使らの自伝、図書館の信頼すべきカタログ、何千何万もの虚偽のカタログ、これらのカタログの虚偽性の証明、真実のカタログの虚偽性の証明、バシリデスのグノーシス派の福音書、この福音書の注解、この福音書の注解の注解、あなたの死の真実の記述、それぞれの本のあらゆる言語への翻訳、それぞれの本のあらゆる本のなかへの挿入、などである。図書館があらゆる本を所蔵していることが公表されたとき最初に生まれた感情は、途方もない歓びであった」。 「その種の冒険のために、わたしも生涯を浪費してしまった。宇宙のある本棚に全体的な本が存在するという話は、わたしには嘘だとは思えないのだ」。 「おそらく、老齢と不安で判断が狂っているかもしれないが、しかしわたしは、人類――唯一無二の人類――は絶滅寸前の状態にあり、図書館――明るい、孤独な、無限の、まったく不動の、貴重な本にあふれた、無用の、不壊の、そして秘密の図書館――だけが永久に残るのだと思う」。 図書館大好き人間の私が戸惑っているのを見て、ボルヘスは、してやったりと得意顔をしていることでしょう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この本を買ったのは3,4年ほど前なのですが、未だに魅了され続けています。暇があったら読み返してしまいますし、そのたびに発見があります。 解説も野暮になるくらいの優れた(それも、長編を煮つめたような濃い)短編が詰まっています。 「トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス」「バビロニアのくじ」など、大好きですけど、確かに、解釈が困難な作品もあります。 一方、「刀の形」「死とコンパス」などは――この短編の本質ではないのかもしれませんが――、ボルヘスの作家としての実力の確かさ、器用さを示していて、短編としてもとても優れていると思います。 難しいというのは、作中、「リデル・ハートの『ヨーロッパ大戦史』」「フロイト流のコメディ」「カルカッタのマチュア市場の鼻もまがるような悪臭」「ウィリアム・ジェイムズの同時代人であるメナール」「四文字語(テトラグラマトン)」など、ボルヘスの膨大な知識量と発想の跳躍によってそんな特異な名詞がポンポンと出てきてしまうので、 外国の知識人の基礎的教養レベルが必要とされるのかなと思いますが、まぁ修飾語の一種だと思い、個人的にはなんとかついていけました。 翻訳が批判されているようですが――いかんせん他の人の翻訳を読んだことがないので比較もできないんですけど――、 ボルヘスの冷静で皮肉っぽい、流れるような語り口が日本語を通して伝わってきたので、細かい誤訳などはあると思いますが、とても好きです | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 難解なのは作品の内容そのもののせい、あるいは注釈をあえて多くつけるそのスタイルにもあるのかもしれないが、 翻訳の仕方に問題があるのではないかと思う。 直訳チックな翻訳で、何を言っているのかよくわからない部分が多い。 それでも内容そのものは面白く、独特の作風にぐいぐい引き込まれていく。 ※ 最初は、注釈はあえて全部無視して一旦最後まで読んでしまうことをおすすめします。 解説と行ったり来たりすると集中力も切れますし、重要なのは注釈ではなく本文なので… | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!