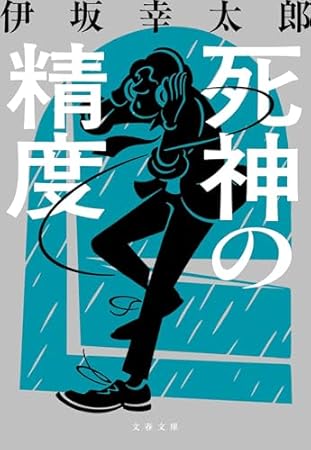■スポンサードリンク
(短編集)
死神の精度
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
死神の精度の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.23pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全50件 41~50 3/3ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 長編なんだろうな〜と思って買ってみたら短編集! 正直、??がつく話もありますが全体的な流れは凄くいいです 最後の話を読んで、「やられた」って思いました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 『短編集のふりをした長編小説』と作家自らが紹介しているが、各編の関連性に留意して書いているのは最後の『老女と死神』のみで、後の4編についてはまったく関連性が認められない。作家のコメントとは裏腹に、おそらく単行本化を念頭において書いたのは最終編のみであろう。 なぜかある会社から派遣されてくる死神君は、仕事の最中はいつも雨にたたられ、人間界のミュージックが大好き。人間ではないので睡眠もとらず、ヤクザに殴られても痛さを感じないという設定。プロットというよりも、むしろ『デスノート』の死神を思わせる<なんちゃって感>を味わった方が楽しめる小説だ。 標的にした人物の死を「可とするか「不可」とするか?その基準はあいまいで定かではなく、あくまでも死神とターゲットとのちょっとずっこけ気味の交流?が読みどころとなっている。これといったミステリーもないため、最終編にたどりつくためにはある程度の忍耐力を必要とするかもしれない。「可」か「不可」といわれれば「可」かなぁ? | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 死神たちは音楽に快楽を覚えるという設定。ほとんど無感動な死神たちにとって人間界で仕事をする唯一の楽しみが「CDショップで試聴すること」だ。これに対比して本文中で語られる「図書館に集まる天使」とは、言うまでもなくヴィム・ヴェンダースの映画「ベルリン天使の詩」の天使たちのことだ。世界の始まりから存在したヴェンダースの天使たちは、人間たちを無感動に見続けていた。本書の死神も少なくとも何千年も前から人間を見続けていると書かれており似たような設定だ。しかしヴェンダースの天使が人間とコンタクトを取れないのと違い、死神はまさに人間になって行動するという部分が大きく異なる。 天使が人間になるには天使であることを捨てなければならない。その替わりに有限の命と、痛み、悲しみとともに、震えるような喜びと愛という感情を手に入れる。それに比して死神は、人間になっても痛みも苦しみも(音楽以外には)感動もない。この設定は天使よりもむしろ特異ではあるが残念ながら私の心に響くようなものではなかった。 もとより軽い娯楽小説であり、深刻に考えるべき作品ではないのかもしれないが、あまりにも人間の死を淡々と描いているところに、爽やかさではなく、かえって異様な感じを受ける。素直に考えれば、不死である死神の言葉で語られるストーリーであるからこそ、人間の死が無感動に描かれているのだと言えるだろう。しかし穿った見方をすれば、死神が関与しているとされる「不慮の突然死」というものは死を意識する間も無く訪れるものであり、人間というものは、実は死神たちと同様に死というものに対して著しく無感動に生きているのだ、ということへの批判なのかもしれない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 主人公は死神の連作短編集。 事故死や不慮の死というのは、死神が7日間の調査の元に「可」or「不可」と決定するもの、ということにこの物語ではなっている。 死神が死神であるという物語の本筋にはそれほど目新しいものは無いのだけど、死神の浮世離れた(当たり前だけど)セリフが面白い。 <例> 「人間の作ったもので最高なのはミュージック、最悪なのは渋滞」 「年貢の納め時だぜ」→死神「年貢制度は今でもあるのか?」 同じ作者の他の作品『重力ピエロ』の登場人物の「春」が出演してるというのも、この作者にはまってる人にはうれしい演出でしょう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 荻原青年に「見送り」の判断が下されれば、星5つ(たとえ、体内がボロボロになっても、事件の後遺症で体が不自由になったり車椅子を使わなければならなくなったりしても、片思いの女性と二度と会えなくなったとしても、生き続ける設定にして欲しかったという私自身の感情を省いても、3つです)。確かに、オーソドックスな展開の中に意表をついた新鮮さがある、という伊坂ワールドの手法は、この章でも健在ですし、余命少ない人生を病死以外のことで終わらせる方法は興味深いものがあります。ですが、同じテーマを扱っていると思われる渡辺淳一の「無影燈」(「白い影」の原作)やマーティン・マクドナーの「ピローマン」のような深みがないのも本当です。共感や感情移入しづらい千葉に、「あの世逝き」の判断を下すに至った過程や葛藤、荻原君の真意を知った後に彼を襲ったであろう後悔や苦悶がどれくらい続いたのかを求めるのは間違っているかもしれませんが、この章では描いて欲しかったですね(経緯や葛藤は、第一章で用いられてますが、そちらは「見送り」なので)。 あと、荻原君の病名が●(オーソドックスもオーソドックスすぎる難病)という設定も新鮮さを薄めてしまっている気がします。千葉が、人間とはズレた感覚の持ち主なのだというブラックユーモアを狙ったのでしょうが、安易ですよね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 初めて伊坂幸太郎さんの作品を読みました。 まず死神の精度という少し変わった題名にすごく興味がありました。 人生観とか死生観とかが語られているのかなと思っていましたが、読んでみると、わりとあっさり、たんたんとした短編集でした。 死神の千葉。彼が一週間で人間を可か見送りか判断する。 とてもクールな考えの死神。 人が生きるか死ぬかはそんなに大きな問題な訳ではないらしい。 一番最後のお話が好きだったかな。前から順々に読んで行くと、バラバラに見えていた短編集につながりが見えてくる。それがおもしろかった。 でももう少し感動とか。考えさせられること。とかが読書。にはほしいなとおもいました。 手軽に読める本だとおもいます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 一編一編がほどよい長さのオムニバス、軽快なテンポの文章と会話、 「死」をテーマにしながら重さを残さない締め方などで、 サクサクと気持ちよく読める一冊です。 最初の2話までは正直ピンと来ませんでしたが 死神の設定を巧みにトリックに取り入れた3話以降から引き込まれました。 後半の話ほど作者も筆が乗っているのが良くわかります。 しかしその軽さ・洒脱さのために、物足りなさを感じさせてしまうことも事実です。 どの話も「ちょっといい話」止まりで、それ以上のものがない。 こういった内容のオムニバスなら、せめてあと3話ほど追加した状態で、 軽さをボリュームで補って欲しかったところです。 また、死神=千葉氏の人物造形も、風変わりと言えば聞こえはいいですが、 あまりに設定が漫画チックで狙いすぎの感があります。 何百年も生きている(らしい?)わりにはあまりに稚拙な部分で物知らずだったり、 何よりも、"可"or"見送り"の基準がさっぱり分かりません。 読んでいて「どうしてこの人が"見送り"なのに、この人は"可"なの?」 と首を傾げた人は少なくないはず。 死は理不尽な物と言われてしまえばそれまでですが、千葉氏の場合、 なまじ人間の理屈が通じるような描き方をされているため、 どうにも釈然としないものが読後に残ってしまいます。 より練られた続編を期待しつつ星三つで。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Accuracy of Death 、なんて魅力的なタイトルでしょう。帯のヒトコト(なんて言うんですか?ごめんなさい知りません)にも非常に惹かれました。正直、一話一話楽しく読めました。恋愛で死神(短編の一つ)、と最終話が気に入りましたが、、、ただ、全体的に童話っぽいですね。詰めが甘いところがところどころに見受けられました。読みやすいことは確かですし、おもしろいこともたしかです。でも帯にだまされたかな、って感じもします。すみません。電車の中で通勤時に読むにはいいかもしれません。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| とても読みやすくさくさく読める短編集、どの物語も死神である「千葉」と八日後に「可」か「見送り」と生死判断される対象者の物語。その物語らは「コンプレックス」「推理殺人事件」「ヤクザ」「恋愛」とそれぞれにカテゴライズできる。これがいいも悪いもテンポよく展開をつくりあげて、読み手に飽きをこさせない感じである。がしかし「死神」というシュールな題材を使っておきながら、内容はバラエティドラマのようなどこかで見たことあるよな話。死神というテーマと表紙のイメージからくるシリアスな印象をもって読んでいった僕には少々軽かったような気がした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 生も死もさだめ。だがその一端を死神に握られているとしたら?本人にとっては重大事でも、死神にとっては単なる仕事に過ぎない。本当は怖いことなのだけれど、感情をはさむことなく淡々と仕事をこなす死神の姿はどこか滑稽でもある。6つの中で印象に残ったのは「死神対老女」だった。自分の死を真正面から見据えようとする老女。そのおだやかで澄んだ心はちょっと切なかった。そして、死神は死なないでずっと時の中に存在し、いろいろな人と関わっているのだと、あらためて思った。老女は・・・。それは読んでからのお楽しみ♪ | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!