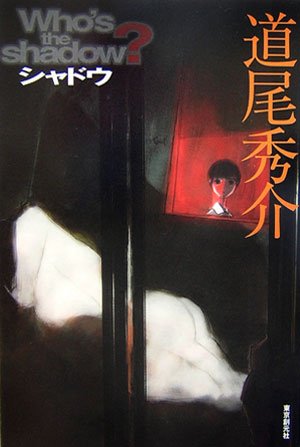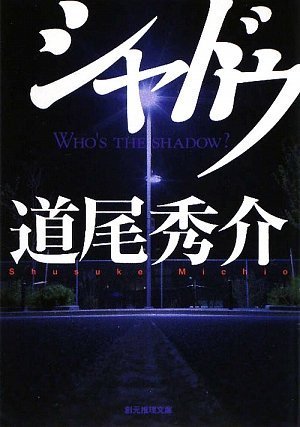■スポンサードリンク
シャドウ
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
シャドウの評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点3.64pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全92件 61~80 4/5ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 非常に、道尾秀介さんらしい作品。 読んでいくうちにいくつかの伏線があることに気づき、テトリスみたいにどんどんつみあげて、最後は全部消えちゃうような。 物語は、2人の子供と2人の父親(でも実際にはほぼ3人)で進んでいく。 登場人物もあまり多くないいs、小説を読みなれている人なら、結末はAパターンかBパターンかCパターンだな、と予想することができるでしょう。 そして多分どれか1つは当てはまる。 人によってはとってつけたような表現が鼻に付くところもあるだろう。 道尾秀介さんの作品は好きだけど、いささかドラマチック仕立てなのを感じるからね。それは若さゆえにだと思うんですけど(実際私と3つしか変わらないし)。 けど最終的にポンポンと当てはまっていくピースが心地言いし、けしてバットエンドではないので最後いやーな感じは残りません。 読みやすいところは確かだし、退屈ではないのは確か。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読み始めたらなかなか中断できない作品の1つは間違いなくミステリでしょう。いろんなパターンがありますので、一概に「こういう話がミステリの大道だ」とはいえません。本書はそのミステリを主に2つの<家族>にスポットライトをあてて描いています。「人間の深層心理に迫る」ことを得意とする作者のいわば原点の作品を読んだ気がしました。精神医学の知識を取り込んだ作風にしている点も新鮮でした。何気ない話かなと最初は思っていたのですが、やはり道尾秀介の作品はそうではない。登場人物は多くないのに、彼(彼女)らの関係やその距離感の微妙なゆえが物語に心地よいアクセントを与えています。本題「シャドウ」の意味も最後でお分かりになるでしょう。それもまた単純明快というわけではないようです。 道尾秀介さんの作品には、なかなか「際どい」と思える題材が取り込まれています。それは『龍神の雨』や『光媒の花』などにもあるものでした。小説は、現実から完全に乖離した「浮き離れの作品」ではなく、「ありそうでなかなかない」など、現実と空想のバランスが大事になってくるように思います。あまりに当たり前の話では退屈でしょうし、逆にありえない話を延々と書かれてもまたそれは退屈でしょう。本書の内容はそういう意味では、その狭間をゆくバランス性ある内容ではないでしょうか。精神医学の知識が盛り込まれていても、それは一般読者に必ずしも縁遠いものではありません。どんどん突き進んで読んでいける作品です。お薦めです。 主人公の一人である小学生5年の男の子の発想というか、精神の逞しさには少し驚きました。本当に今の小学生なのかと何度かと問いかけました。彼の作品ではいっぱしの大人というよりは、わりと年齢的に低い人物が主人公になっているものが多いのかもしれません。「小学生でここまで頭が回る?」という印象ですが、このことが本書の価値を減じる要素ではありません。スリリングなタイトルである本書「シャドウ」をお楽しみください。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「ひまわりの咲かない夏」系のサイコミステリ。主人公、鳳介は自分の母親の葬儀であった母の友人、恵にあったときフラッシュバックしたエロテックな記憶。そして、恵の死の夢を見た次の日、恵みが自殺する。その自殺の真相は? ストーリーは登場人物の一人称視点で語られ、妻、母の死という大きなストレスの中で不安定な精神状態が各人物の発言を曖昧な物とし、犯人を恵の夫、自分の父親などに疑心の目を向けさせるように話が進められ、どんでん返しの幕切れや父親の手記による陰謀の告白などで物語の解決が語られる。テクニカルにはよくできていると思うが、統合失調症の解釈に間違いがあり、それを論拠にストーリーが構築されているため、嘘くささとわざとらしさだけが鼻につく作品になってしまっている。このような作品を書く場合、バックグラウンドの医学的知識を十分にもってから望まなければ、週刊誌の記事のようないいかげんな物になってしまう。もう少し勉強してもらいたいものだ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 何しろ冒頭から火葬場ときたもので、前半はとにかく思い屈してしまう展開だ。まだ小学生の凰介と亜紀にまといつく暗然たる空気には幾度となく押し潰されそうになった。 風向きが徐々に謎解きへと変じてゆく後半はだから、反動的にスムーズに読めた。よしんば作者が意識してこういう書き方をしたのならば、これはかなりのくせ者だといわねばなるまい。まったくもって油断がならない。 トリックの面では、「背の眼」では弱かった伏線を張る技巧が格段に進歩しているのに感心させられる。洋一郎をめぐる二重の騙しのギミックが傑作である。途中まではなかなか話の核心がみえてこず、やきもきさせられたが、無理のない伏線の回収と凰介一家・亜紀一家共に大団円の締めくくりで大満足。俊英という、この作者のうたい文句は確かに伊達じゃない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 道尾氏の作品を初めて読みましたが、なかなか感心できる出来でした。 精神疾患を扱っていることもあり、若干ホラーテイストなところが 味があって良いですね。 誰かが異常な行動をとっているのは分かるけども、はっきり分からない ままストーリーが進み、ラストで明かされる事実によって、爽やかな カタルシスを得られます。 ストーリー運びのテクニックがあり、且つ読みやすい文章で、一気読み 可能です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ミステリーにオカルトを持ち込むのは個人的にはアンフェアだと思っている.回収しきれなくなった伏線を無理やり解決するために用いられる手法,ある種のデウス・エクス・マキナ的展開はファンタジーに近いものであり,そうなってしまった時点で一般的な読者の科学的推論は日の目を見られず,ある種の徒労を感じてしまうであろうからだ. 以前に同作家の著書「向日葵の咲かない夏」を読み,物語に引き付ける文章の巧さと同時に,ラストでの説明には失望させられた.それに対し本作は物語に破綻がなく,巧く纏まっている.また,物語の流れは「向日葵の咲かない夏」同等かそれ以上であるため,完成度の高いミステリー作品といえるだろう. | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 道尾俊介さんの作品を、色々読んでると何となくパターンが解った気になっていたが、この作品の 結末は、予想出来なかった。 パターンが解った気になっていた自分が、少しは恥ずかしかった。 もっと、道尾俊介さんの作品を読んでみたくなった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「向日葵ー」を読み終え、「シャドウ」を読みかけなのですが、引き込まれ過ぎて一日で読み切ってしまうのが勿体ないくらいです。 好きな作家さんの一人ですね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 毎晩眠る前に読みました。 文章自体に変な癖がなく、私は読みやすかったし内容に集中できるのでとてもよかったです。 読み進めていく過程で、何度も主人公に「気を付けてっ〜!」と心の中で叫んでしまう面白さがあります。 登場人物がそれぞれどんな人格を持っているのか。また、それぞれにどんな気持を抱いているのかがしっかりと伝わってくるところが、ミステリー要素をさらに面白くさせていると感じました。 買ってよかったと思える一冊であると同時に良くも悪くも「引っかかるもの」が無かったような読後感。☆-1にしました。 変な引っ掛かりが無い分、忙しい時期の気分転換や、気晴らしをしたいときのミステリーとしてオススメの一冊です! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 第7回本格ミステリ大賞受賞作。 仲の良い2組の家族に降りかかる悲劇が、それぞれの小5の子供を中心に描かれる。 思わせぶりな記述、逆にあっさりした記述に、結末を推し量りながら読み進んだが、退屈せずに意外な結末まで辿り着いた。ビッグサプライズというまでの結末ではないが・・・。 小学生の子供の目線での話といえば、同じ著者の「向日葵の咲かない夏」には落胆させられただけに一抹の危惧があったが、杞憂に終わった。しかし、小学生の子供を軸にすえるというのは、仕掛け上は都合の良いこともあろうが、どうしても大人びたところと無邪気なところのアンバランスが気になる。 反面、本作においては、発生する事件というのが暗いものなのだけれど、ラストの子供達の会話が救いにもなっているのでマイナスばかりでもないけれど。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 最近話題の作家さんだということで (しかも同い年!)読んでみました。 表紙に見られるようなホラー色を漂わせながら ストーリーはどんどん進んでいきます。 読みやすいです。 そして物語の中盤で「シャドウ」の意味が 説明され、タイトルの「誰がシャドウだ?」 に大いに興味をそそられ、 さらに読み続けてしまいます。 最終的に二転三転するストーリーには 「なるほど、これが人気の理由かぁ」 と納得しました。 でも★が5つにならないのは どうしても物語に 深みが感じられない気がするからです。 ミステリだから、それが重要じゃないことは 当然わかるのですが・・・ 読みやすい分、読後感が軽く感じられます。 これは好みの問題でしょうか? | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 日常生活における違和感が徐々に膨らみ、謎と恐怖が限界点まで到達した時、独自の世界が拡がると言った作風が道尾氏の特徴だと思う。本作はこの期待を裏切っている。 本作の主人公は小学生の鳳介一家と、鳳介の幼馴染の同窓生の亜紀一家。互いの父親、母親どうしも同一医大の同窓生と言う設定。鳳介の母の咲枝が病死、亜紀の母の恵は自殺する。自殺の原因は、夫の徹が恵の浮気を執拗に疑い続けたため。亜紀も実子ではないと思い込んでいる。それを漏れ聞いたのか亜紀は家を飛び出し、交通事故に遭うが、実は自殺未遂らしい。亜紀は性的虐待の体験もある。登場人物達に幻視症状・精神崩壊がある以外は、ここまでは仄めかしの多い単なる家庭劇である。これでツイストを利かせるのは流石に難しいだろう。 結末まで読んでも異界を覗く事は出来なかった。「シャドウ」と言う感覚は誰にでもあるもので、取り立てて題名(テーマ)にする程の事とは思えない。これ以外にもワザと精神医学の専門用語を多用しているのも感心出来ない。そして、まるで宗旨変えしたかのような作風。宮沢賢治の「よだかの星」をモチーフにして、"生きて行く希望"を描いた伊坂幸太郎氏を思わせる作品で、道尾氏らしさが感じられない。戦慄と驚愕を期待した道尾ファンにとっては拍子抜けの作品だろう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 父親同士、母親同士が同級生という2組の家族の子供同士である凰介と亜紀。この2人もまた同級生というつながりの深い中、双方の母親の死にともないその裏に隠されていた悲しい過去が明らかになるストーリー。 読み始めから、見えてくる光景、出来事の裏に、何か恐ろしいものが隠されているような気がし、背筋がぞわっとしながらもグイグイと引き込まれて行きました。 また、特に凰介に関し、子供とは思えない理解力がある反面、亜紀に対する呼び方に迷ったり、父親に対する、「何があっても絶対」と言えるような愛情など子供らしい面もあるなど、大変丁寧に描写している印象がありました。 ラストを見てどう思ったか、読んでいる過程でこのラストは想像しうるものだったかは、この小説の場合ここで書いてしまっては、読む過程の楽しみが半減してしまうと思われますのでやめておきますが、ただ一言言えるのは、「著者の話の運び方は上手かった」ということですね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 相変わらずのストーリーテラーぶりは読者をグイグイ引き込ませる。ただしどんでん返しがある程度予想できるものであり、エンディングももっとダークにしても良かったのではと思う。 しかし、この作者の作品はいずれも救いが無いものが多い。しかしそれが実に良い。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 主人公の少年が、それぞれに深刻な問題を抱えた父親と幼なじみの少女にたいし、 どのように向きあい、答えを見出だしていくかを描く成長物語の側面もあるミステリ。 父親の問題と幼なじみの問題は、関連をにおわせながら同時進行していきますが、 作者の巧妙なミスディレクションにより、読者は、その二つの間に本当はどのような 繋がりがあるかを容易には見通せないつくりとなっています。 また、大学病院の精神科が舞台となり、三人称多視点の叙述形式が選 ばれていることも、読者に真相を即断することを躊躇わす要因となります。 幻覚を見たり、精神的に不安定であるため、信用できる視点人物かどうか 判然としない精神科の関係者、そして、どこに仕掛けられているか予測で きない、意図的な〈書き落とし〉による叙述トリック――。 読者は、事件の全体像を把握できない宙吊り状態のまま、結末まで、 作者の卓越したストーリーテリングに翻弄されていくことになります。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較的早い段階で、キーマンが誰か分かってしまったので、 結末も想像ができてしまいました。 ただ、それが想像以上に込み入っていて、 良くできているなという印象です。 残念だったのは、偶然が重なりすぎているような気がするのと、 小学5年生の男の子がこれから一生背負うには、 重すぎる出来事ではなかったかと言うことです。 ストーリーとしては面白かったけれども、 子どもの親としては、後味が悪かったです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| WHo's the SHADOW ? −−シャドウは、誰か? そんな副題の作品、 第7回本格ミステリ大賞受賞作です。 小学5年生の凰介は母親を癌で亡くします。 ほどなく、幼なじみの亜紀の母親が自殺、 亜紀自身も事故に遭ってしまいます。 さらに、二人の父親の言動に不可解な点が生じて・・・。 とにかく、読みやすい。 ストーリー展開も小気味よく、 ページを繰る手が止まらなくなります。 そして、この作者得意の後半の二転三転。 シャドウとは何か。シャドウとは誰なのか。 結末に向けて物語は一気に加速します。 どんでん返しの衝撃度は、 それほど強くないけれど、 ラストに至るまでの物語展開が、 凰介の精神的苦悩と成長を描いています。 単なるミステリでは終わることなく、 小説として清々しさを感じさせるところが、 注目の作家と言われる所以だと思いました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「カラスの親指」でこの作者を知ったので、どうしても比べてしまいます。 はっきり言っていまひとつです。 巧さにゆえに複雑なあやとりのように込み入ってしまった伏線のために 物語は最後まで内面的な膨らみに欠けます。 がんじがらめになっちゃった感じです。 それをブチブチっと断ち切るように回収するラストは ちょっといただけません。 なんだかんだ言ってするすると読めましたから 「カラスの親指」に至る過程として許せますが こちらを先に読まれた方には敢えてお薦めしませんね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 懇意にしている水城家とは母親、父親同士がそれぞれ古くからの知り合いで、 子どもたちも同じ学校に通う同級生だった。 ところが、凰介の母親は癌で逝き、それを追うように水城家の母親・恵が自殺をする。 その混乱の中、水城家の一人娘・亜紀が交通事故に遭ってしまう。 そして両方の父親たちも変調をきたすが―― 父親の買ってくる不気味な『叫び』という絵画といい、 凰介の脳裏に残る不可解な情景といい、何か得体の知れない恐怖をにじませている。 この話をいったいどういう風に終わらせるのだろう、 オカルト的な結末になってしまうのでは、という邪推もしたが、 ラストではあらゆる伏線を拾って読む者を納得させる。 読んでいる段階では全く想像もつかないような展開だが、 それでも種明かしをされれば理路整然とした論理が横たわっていて、唸らざるを得ない。 不自然さを感じさせない、あらゆることろに散りばめられた伏線、 精神医学に基づいた論理的推理、最後に明かされる驚愕の真実。 本当に、ミステリーが上手い。迷わず5点としたい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 最後までハラハラしながら読みました。真相に辿り着くキーは一つのみ(だと思います)。 精神医学や心理学を用いつつ、登場人物ごとに視点を切り替えて推理を進めていきます。心理学関係の用語に「バイアス」という言葉があります。この『シャドウ』は巧みなトリックと文章構成をもって、上手く読者に「バイアス」を植えつけてくれます。 本当にころころと話を二転三転させてくれますが、正直、終章の最後を読むまで上記の「キー」が引っ掛かっていました。そしてエピローグの前まで読み終わったとき、思わずニヤリと笑ってしまいました。ふふ、面白い。倫理的にどうなのよ、というのもありますが、現在のとある問題に一石を投げかけている意味もあるかと思います。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!