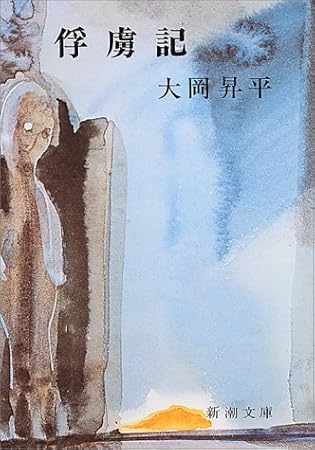■スポンサードリンク
俘虜記
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
俘虜記の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.24pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全27件 21~27 2/2ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| もうすぐ来る8月が敗戦の月であることを意識して本書を読んだ。 本書の白眉は著者が自分で自分に「お前は今でも俘虜ではないか」と問いかける一文だ。 本作は 舞台設定こそ 俘虜収容所だ。しかし戦後六十余年を過ぎた二十一世紀の現在に 読んでいて迫ってくるものは本作に描かれる人間の姿が少しも古臭くない点にある。いや 読んでいて自分の周囲と自分自身の姿が喝破されている気がして いささか苦しい思い すら感じた。 本作は帰国直前で筆が置かれている。帰国後の著者は描かれていない。但し 本作を 書いているのは 「帰国後の」著者であり その彼自身が「お前は今でも俘虜ではないか」 と書いた点が重い。 本作は戦争を描いたものではない。戦争は 書いた材料に過ぎない。書いた事は 徹底して「人間とはどういうものか」に尽きる。その厳しい目は書いている著者 自身にも突き刺さっている。自分を突き刺す文体が このように冷静で淡々と しているのも初めて見た。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 著者は大戦末期の昭和19年にフィリピン・ミンドロ島の戦地へ送られるが 米軍の俘虜となり、収容所で約一年間過ごすことになる。 本書はその収容所での体験記が大部分を占めるが、 そこでは我々がイメージする収容所の過酷さや悲惨さは殆んど無い。 俘虜達は、十分過ぎる量の食事を与えられたために次第に肥えていき、 喫煙しないものにも配給される煙草を賭博に用いたり、 干しブドウから酒を密造したり、米軍の物資を盗んで貯め込んだりしている。 そういった俘虜達の強かさや堕落した姿がシニカルに描かれており、 これはあとがきによれば俘虜収容所の事実をかりて、占領下の社会を諷刺するという意図もあったようである。 著者はフランス文学翻訳家でもあり(著者翻訳によるスタンダール作品に接した人もいると思う) その語学力を買われて収容所では通訳となり肉体労働を免除されたりしている。 また、著者が春本(チャタレイ夫人の恋人を下敷きにしたりした)を書いて 収容所内での流行作家になったエピソードなども非常に興味深い。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「野火」は教科書で知って、アメリカ在住時に全文を読んだ。この「俘虜記」は、いっそうシニカルだ。特に、序盤の俘虜になるまでに、草むらから目の前まで接近した若い米国兵を大岡氏が撃たなかった心理描写は、今なお名作の誉れが高い。私は「俘虜記」は主にヨーロッパ旅行中に読んだが、異国に居る自己を見つめなおす気分が、大岡氏の心理描写に実にぴったり来て、飛行機の中でグングン読み耽ってしまった。 俘虜である自分たち自身についても批判的で、厳しくドライな気分が行間から読み取れるが、日本軍指導部の批判は実に手厳しく、愚弄、と大岡氏に一刀両断されている。対戦国の米国の民主主義には、実に好意的だ。終戦近くに30歳過ぎて参戦した大岡氏は、それほど日本の軍隊に心から失望し、自由の国アメリカの寛容に心酔していたのだろうか? 私は本作に続き、大岡氏の後年の作「ながい旅」を読んで、大岡氏の心情が分かる気がした。「俘虜記」は戦後まもない作品で、解説にもあるが、進駐軍に遠慮もあったらしい。「ながい旅」でも、最高執行部の愚弄さは繰り返しつつも、戦犯裁判で部下をかばい続け毅然として米国の無差別空爆を立証し、誇り高く巣鴨刑務所に散った岡田中将(司令官)に深い共感をもった文章を綴られている。 大岡氏は、愚弄な作戦を痛烈に批判した。その中で、超然とした誇り高い人間性に深い共感をもって後世の私に伝えてくれた。こうした、大岡氏の置かれた時代も知った上で、なおかつ本作のシニカルで鋭い感性に溢れた人間観察の文章は、ときに爽快であり、ときに今の時代にも通じることを言われており、極めて示唆的である。俘虜となってからの文章が長いが、一気に読み進めてしまう、永遠の名著といえる | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 私の父はソ連の収容所に2年間抑留されていましたが、カスピ海沿岸のグラスノボツク(今ではトルクメニスタン国)だったので気候も温暖で、所謂シベリア抑留者の悲惨さは経験しなかったと言っていました。本書はフィリピンの収容所が舞台で、民主主義国家米軍の下だったこともあり俘虜の待遇はソ連軍よりもよかったようです。例えば米軍と同じ服、一日2700カロリーの食糧が与えられ、干し葡萄からワインも密造していました。父もここまで楽はしていなかったでしょう。 そんなこんなで興味深く読めたのですが、読後、著者はいったい何を一番伝えたかったのだろうという気がしてなりません。俘虜生活の実態?戦争の馬鹿馬鹿しさ?それをとめられなかった国民のだらしなさ?軍隊の不条理?米軍の寛大さ(イラクを見る限り今のがひどい)?それとも通訳として米軍と俘虜の間に入った辛さでしょうか。ところどころに顔を出す、著者のシニカルな視線はそれらいずれをも感じさせています。でも、数多ある戦記ものから本書を際立たせているのは、俘虜という状態が彼らに与えたものが、解放後もなお彼らを支配しているのではないかという指摘だと思います。そのものというのは明示されていませんが、次の一節にヒントがあるのかもしれません。 「我々にとって戦場には別に新しいものはなかったが、収容所にはたしかに新しいものがあった。第一周囲には柵があり中にはPXがあった。戦場から我々には何も残らなかったが、俘虜生活からは確かに残ったものがある。そのものは時々私に囁く。「お前は今でも俘虜ではないか」と。」 10年後再読したい本の一冊です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 私はこの作品をノンフィクションと思い込んで読み始め、カバーに記されている解説により、読み終えた後になって初めて、著者の従軍体験に基づく連作小説であると言うことを知ったのである。しかし、今でも私にとってはノンフィクションであり、どこが虚構に当たるのか、全くわからない。少なくともこの作品を小説とするなら、ジャーナリストの書いた記事でも小説に分類されてしまうものが多々存在することになると思う。 部隊から外れ一人戦場を彷徨っていた著者が、林のへりに倒れ込んでいた時に米兵が現れる。米兵は著者に気付かないのだが、著者は銃の安全装置を外すも結局射たないのである。この「なぜ射たなかったか」についての省察に数ページ費やされていることが、唯一のノンフィクションらしからぬ箇所であろうか。 タイトルから察せられるように、書かれていることの大部分は俘虜収容所内のことである。そして「阿諛」と言う言葉が何度も出てくるが、これが日本人の集団秩序の維持に重要な役割を果たしていることもわかる。戦場と言う極限状況下、収容所内で新たな秩序が形成されていく過程、米兵との対比などを通して、日本人と言うものを見つめ直すことの出来る好著である。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 作者の大岡昇平は京大仏文科卒でスタンダールの研究家でもある。その彼が捕虜になって西洋のヒューマニズムを自分自身で認識したという大きなインパクトがこの作品の最重要項目。敵の捕虜を自分たちと同じ扱いをするという、この作品中の出来事を、京大西洋史の卒業生にしてルネッサンス史の研究者でもある会田雄次の捕虜体験記『アーロン収容所』と読み比べてほしい。そこには西洋のヒューマニズムの限界が、衝撃的な事実でもって描かれているから。アメリカ人とイギリス人と、国は違っているが、敵国の捕虜に対してかくも異なった態度が取れるものか。個人的な違いか、状況の違いか、それとも没落に向かう国と繁栄が約束された国の違いか。二つを読み比べて考えてほしい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 思えば「戦争小説」というものをほとんど読んだことはなかった。それは余り興味がなかったのと同時に、戦争という極限状態に参加し、その最前線で描かれるドラマへ、なにも共感を得られないだろうと諦めに近い感情をもってしまうからだった。空襲が背景にあった小説は幾つか読んだし、爆撃に打ちのめされて行き、街にうごめく人間の退廃的な姿への描写へは、深く心を奪われて来た。俘虜記がどうやら「いちれん」の戦争小説とは違うらしい、と言う読書人ならみんな知っているような批評を目にして、読んでみることにした。 冒頭の「捉まるまで」を読み、その余りにも緻密で分析的な文体へ、まったく新鮮な感覚を覚えた(どうやらこれも発売当時からの評判らしいが)。今までに読んだ小説とは明らかに違った文体で、どちらかと言えばノフィクションや思想書的な感じだ。さらにもっと「乾いた」印象を感じさせる文体で、どんどん引き込まれていく。推理小説的な運びなのだろうか。 フィリピンのミンドロ島でアメリカの捕虜となった一日本兵の手記の形式を取ったこの小説は、徹底して記録的である余り、僕にはその冷静さは十分に演出的ですらあった。むしろノンフィクションとはかけ離れたドラマ性を感じた。現実が「フィクション」よりも「ドラマチック」であると言うのとはまた違う、分析的な眼差しが、その微動だにしない姿勢が貫徹された流れに、とても「芸術的」な感動を覚えたのだ。 著者の太平洋戦争「従軍体験」に基づく「連作小説」という構成から、分厚いし文字も小さく、ただでさえ読むスピードが遅くなりがちな文庫本なのだが、文体へ惹かれる余り、どうしても丁寧に拾おうとし、さらに遅くなる。思想書を読む場合に感じる難解さとは違う、慎重な姿勢になるのだ。読み進む内に感じる感激は、十分に疲労を及ぼし、また慣れ親しむ。だから終盤には早く読み終わりたいのと、この文体から離れる寂しさとで、やや複雑な感情すら抱くのだった。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!