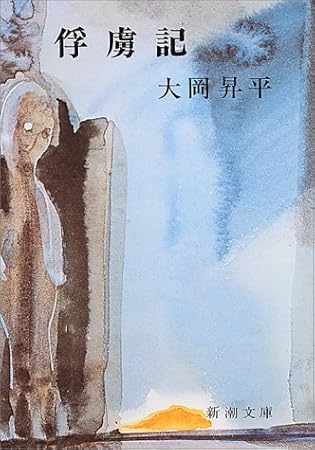■スポンサードリンク
俘虜記
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
俘虜記の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.24pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全27件 1~20 1/2ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 私の叔父は、レイテ戦において19歳で戦死しました。勿論、家族のもとにお骨は帰ってきませんでした。それを踏まえてこの著作を読むと戦時中の生き様がみられます。人間として葛藤もあり、生きる為に敵を殺さねばならない。究極の状況で私だったらどう、生きるのだろうか。ふと、そんな思いになりました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省によると、フィリピン戦での旧日本軍の戦死者は約51万8000人である。 戦闘で亡くなったのは少数でほとんどが戦病死(餓死がほとんど)であった。 フィリピンで生き残った日本兵は約12万7000人。 この数字を見ると本書の著者大岡昇平さんは幸運だったと思う。 なかば意識なく一人野に晒されアメリカ兵に援けられたのは奇跡的だった。 氏が『俘虜記』を執筆したのは45年12月帰還後の翌年46年4月末から5月にかけてであるから、まだ鮮明な記憶にあるときであり、自身の経験したことや俘虜仲間たちを観察した細部もリアルで辛辣な批評も定かなものであろう。 氏が米軍の俘虜になるまでの記述は悲惨なものであり、九死に一生を得たことは間違いない。 が、その後、氏が体験したアメリカ軍の待遇は、評者が数年前に読んだ会田雄次著『アーロン収容所』や古山高麗雄著の戦争文学三部作『断作戦』、『龍陵会戦』、『フーコン戦記』と『兵隊蟻が歩いた』、そのほか山本七平著『一下級将校の見た帝国陸軍』などと比べると、氏が俘虜として体験したことは随分恵まれていたようだ。 氏が京大出のインテリで英語を話すことが出来るから通訳としてアメリカ軍に用いられ、他の俘虜より恵まれた境遇だった。 通訳としての特権でアメリカの雑誌や探偵小説を読み「探偵小説を読む奴も馬鹿だが、書く奴はなお馬鹿である」と吐いて捨てている。(P309) この件を読み、評者は、「ちょっと待てよ!」と呟いた。 氏が、推理小説の愛読者であったことを知っていたからです。 1978年に『事件』という推理小説で日本推理作家協会賞を受賞したし、何冊かのミステリ小説も翻訳していたからです。(俘虜中に読んだのは、パルプマガジン掲載の駄作だったのだろう) 本土がB29で毎夜のように爆撃を受けているときに、食うものにも困らず、死の恐怖もない世界で暮らす疚しさも氏は吐露しています。 日本政府がポッダム宣言を受託せず、米空軍が毎夜爆撃を続けていることをアメリカの新聞で知り、「私は憤慨してしまった。名目の国体のために、満州で無意味に死なねばならない兵士と、本国で無意味に家を焼かれる同胞のために苛立ったのは、再び私の生物的感情であった。天皇制の経済的基礎とか、人間天皇の笑顔とかいう高邁な問題は私にはわからないが、俘虜の生物学的感情から推せば、八月十一日から十四日まで四日間に、無意味で死んだ人達の霊にかけても、天皇の存在は有害である。」と怒りをもって書いています。(P350~351) 評者はこの『俘虜記』を、この「」内の件だけでも本書を読む価値があると思いました。 終戦前日の1945年8月14日から翌日にかけ、全国10カ所以上で空襲があり、2300人以上が犠牲になった事実がこの件を証明しています。 無差別空爆を命令したアメリカ軍のカーティス・ルメイ将軍へ戦後(1943年)航空自衛隊指導の功績という名目で日本政府は勲章を授与しています。 「勲章呈する奴も馬鹿だが、受け取る奴も馬鹿だ!」言いたくなりました。 氏は、俘虜収容所で探偵小説を書いて本にして莨一本で俘虜たちに貸したり、演芸会の艶笑劇を書いたり、炊事係の十七歳の給仕係兵士の吉田と冗談を言いながら干し葡萄の密造酒を飲み交わした末、泥酔し、本気で喧嘩をしたりして俘虜の無聊を過ごします。(P410) 京大出のインテリの『俘虜記』を「事実は小説より奇なり」の思いを深くしながら読んでしまいました。 評者は、先に読んだ『アーロン収容所』の記憶から、イギリス軍俘虜収容所とアメリカ軍俘虜収容所との彼我の差待遇に驚きながら本書を読み終えたのです。 <蛇足の追記> その1:「捉まるまで」という章は、先に読んだ『靴の話』にも重複して掲載されていました。 その2:29年ぶり日本に帰還した小野田寛郎予備陸軍少尉は、大岡昇平さんが駐屯したミンドロ島の北西にあるルバング島でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 中古感が無くて、良いと思いました。有難う御座いました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ちょっと長すぎる嫌いがあるが、時間をかけてもう一度読もうと思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 満足です | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 文学者の従軍と捕虜生活の記録。 肉体が兵器としての役割をなさなくなった時代に、軍刀と小銃(それも行き渡らなかった)をもって、飢えの中での生命維持だけが目的となった兵士。 その後、人権思想に基づいたアメリカ軍捕虜収容所で豊かな食糧と衣服と清潔な生活環境を与えられて怠惰で不自由な生活を送った30代半ばの文学青年の省察。 内面の軌跡を克明に記録しているところがすばらしい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 京都帝大仏文科を卒業して、サラリーマンとなり、35歳で召集されて、フィリピンで暗号手として従軍中に敗戦を迎え、米軍捕虜としてレイテ島の捕虜収容所で過ごした11カ月間の生活を冷静な目で、克明に、しかもユーモア豊かに描いた体験記。収容所生活の実情や、虜囚というものの心理、時間とともに変わっていくその変化、捕虜仲間との交流や駆け引き、米兵との交流、捕虜に対する米軍の処遇や、捕虜というものに対する日本軍と米軍の観念の相違など、読んでいて面白いとともに、大いに啓発されるものがある。 これは小説ではなく、実話である。読んでいて飽きない。戦争を知っている世代にも、戦争を知らない世代にも、ぜひ読んで頂きたい本だと思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| その後の歴史を見ればわかる通り、レイテ島の収容所で繰り広げられた光景は、占領下の日本本土での情景を先取りしていた。アメリカ軍はまるで解放軍さながらである。理不尽な暴力の支配する日本軍という組織からの解放、あるいは出鱈目な作戦による飢餓、餓死への恐怖からの解放。虐げられた状況に置かれていた日本軍兵士の眼にアメリカ軍は救世主のように映ったかもしれない。だから敗北の屈辱感などない。阿諛追従も平気である。必然的に憎悪の視線は小隊内のかつての指揮官などに向かう。これまで散々イジメてくれやがって、という気分なのだ。いかにあの戦争に正義がなかったか。正義があれば憎悪の眼が身内に向くはずがない。大岡昇平が意図したかどうかはわからないが、その構図が『俘虜記』ではくっきりと浮かび上がっている。そしてそれはレイテ島の収容所から占領下の日本社会へと引き継がれ、現在もなお日本人を捉え続けている。大岡昇平が自らに問うた「まだ俘虜なのだろうか」という問いは、今でも日本人を捉え続けているのである。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 表紙が違うのが来ました 多分アマゾンで載せている表紙は単行本のだとおもいます 気を付けてね 内容は同じだよ | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 戦争云々だけでなく、極限状況に追い込まれる人や組織がどうなるか、リアルに伝わります。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 昭和20年1月25日、フィリピン、ミンドロ島南方山中で米軍の俘虜となり物語は始まる。それに遡る昭和19年12月15日、島の西南端サンホセに米軍が上陸した事により、彼の所属する部隊は山中に入り持久態勢を取るが、大半がマラリアに罹患して多数が死に、彼も重症となって病臥中に米軍の襲撃に遭い、部隊とはぐれて一人で山中を彷徨した。彼は手榴弾で自決を試みるも不発で果たせず、人事不省で倒れているところを捕えられた。途中目の前に米兵が現れた時、彼は撃てる態勢にありながらも引鉄を引かなかった。その時彼は35歳の応召兵であった。 彼は英語がある程度話せた事により、他の俘虜達と大きく一線を劃していた。ブララカオ、サンホセと収容所の病棟を転々とする中、米軍の軍医や兵士達と交流して、日本の軍隊には無い彼等の寛容さに接する。やがて平癒してくると、タクロバンの大規模な俘虜収容所に空輸され(昭和20年3月中旬)、約700名の日本人俘虜達と暮らし始める。彼は米軍の医師から与えられた英文の書籍を終日読んで時を過ごし、必要以上に他の俘虜と接しなかった。 収容所の中は日本の軍隊其の儘に、権力者(役のある者や配膳係など)が弱き者を抑圧する社会であった。将校は別に収監されていた為、権力者の座に就いたのは、奇妙な事により先に俘虜となった者達であった。彼の克明な観察による収容所内の描写は以下の様である。 『俘虜は全く手がつけられない怠け者である。私の受け持ったテントは内科の中でも軽病者を集めた病棟で、多く栄養不良から来る脚気か、山中の悪食による下痢であったが、軍医の薦める一日二回の水浴も、十分間の日光浴も、彼等にはすべて面倒臭いのである。彼等は終日熱いテントに寝そべって食べものの話をするのを好む。』 自らも俘虜でありながら、多様な俘虜の様子を見つめる静謐な目と、それを伝える精緻な人物描写は、滅んだ軍隊の末路である彼等の頽廃的な社会を、寧ろ滑稽さと親しみを以って我々に印象付ける。我々のなんとなく想像する俘虜達が俘虜となる運命を受け入れる心情についても、その結果堕落した皇軍将兵の結末を交えて、以下の様に考察している。 『当時の日本人の如く、恥じつつ文明国の俘虜の特権を享受するという状況は、多分もう繰り返され得ないからである。一度俘虜の味を覚えた日本人は、戦いが不利になれば猶予なく武器を捨てるであろう。彼等はかつてその真の意味を反省せず身命を抛った如く、俘虜の身分が彼等に何を課しつつあるかを知らず、ただその甘味に酔ってしまった。今後彼等は相手を選ばないであろう。日本人を傭兵として使うことは誰にも薦められない。』 そしてその環境と、充分過ぎる待遇に馴れた俘虜達は、堕ちる所迄堕落し、怠惰と遊蕩の限りを尽くした。労役に出れば米軍の糧食資材を盗み隠匿貯蔵し、配給の干し葡萄から密造酒を造り、支給される煙草を賭け物にして、博奕に耽溺した。また男色まがいの痴話喧嘩も横行し、日本人といううものの一側面を見る思いがする。 『我々は兵士ではなかったが、後にはたしかに俘虜であった。しかも清潔な住居と被服と2700カロリーの給与とPXを享受する一流の俘虜であった。或る者は今なおあの頃を「天国」と呼び「わが生涯の最良の年」といっている。』 レイテの収容所の俘虜達にポツダム宣言受諾が知らされたのは、8月10日の事であった。11月17日になって彼等は復員の途に着いた。復員船は日本海海戦の折、バルチック艦隊を発見通報した老朽船「信濃丸」であった。文中には様々な戦中の兵士の体験談や告白が随所に載せられ、また残虐行為を淡々とこなした話なども載せられるが、末期の日本軍の堕落の行き着くところを示す衝撃的な俘虜の証言を、最後に留め置いておきたい。此れが皇軍将兵の成れの果ての末路である。 『彼はセブの山中で初めて女を知っていた。部隊と行動を共にした従軍看護婦が、兵達を慰安した。一人の将校に独占されていた婦長が、進んでいい出したのだそうである。彼女達は職業的慰安婦ほどひどい条件ではないが、一日に一人ずつ兵を相手にすることを強制された。山中の士気の維持が口実であった。応じなければ食糧が与えられないのである。』 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 文筆家なら読むべき書物のリストで見つけて読んでみたが、期待以上であった。深く考えさせられる。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 僕は主観でしか行動しない。だから著者が作中嫌った阿諛の才能も持ち合わせていない。他者にご機嫌とるために太鼓持つのは大嫌いだ。自分で考えて判断する。僕がいちばん大事にしてきた生き方の作法である。しかし、俘虜記を読み終えて、この主観ほどあてにならないものはないと僕は反省した。主観は国家やたまたま居合わせた隣人や、そして己自身から、いとも容易くコントロールされてしまうものなのだ。特に己自身からコントロールされること、つまり、僕は僕のエゴイズムの呪縛からは逃れなれないような気がした。そのことにハッと気付かされた。 だから、反省したい。僕は、これからの人生で、仕事や人との関わりに身を置きながら、主観を磨く努力をしなければならない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「生きて虜囚の辱(はずかしめ)を受けず」と叩き込まれた兵士達が、虜囚となるや否や予想外の高待遇にスポイルされ、遂には演芸大会まで催すに至る顛末を描いた異色作。 そこには、戦記物にありがちな、ヒロイズムや鋼鉄の意志などどこにも無い。 どんなに軍事教育を施され、厳格な戦陣訓で洗脳されようとも、いったん戦闘能力を失い快適な環境を提供されれば、もうそんな大儀はどうでもよくなるという、何とも人間臭い一面が垣間見えて興味深い。 これを戦後日本社会の縮図とみる文芸批評は的を射ており、本書で描かれた収容所生活は、日本人の変わり身の早さ(よく言えば高い順応力)、一方から他方へと一気に遷移できる両極端性を示唆している。 よく言われるように、戦後の高度経済成長も、こういう国民性があってこそなのであろう。 しかしながら、俘虜達は内心忸怩たる思いでいたのも事実であり、自分達が飽食している間、内地の親類縁者は飢えと空襲にさらされ、また終戦後いったいどのツラ下げて帰還するのだ、といった事で悩み続けてもいたのである。 内地の人間からすれば、愚行・堕落ともとれる収容所内での生活でも、彼らは虚しさを感じ、密かに苦しみぬいていたのである。 何ともやるせない話だ。 敗戦判明直後、主人公が泣きながら耽っていたときの回想が、今でも脳裏に蘇る・・・ 「偉大であった明治の先人たちの仕事を、三代目が台無しにしてしまったのである」 「私は人生の道半ばで祖国の滅亡に遭わなければならない身の不幸をしみじみと感じた」 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 人が生死をかけた戦争の極限状況から、捕虜として捕らえられ、目的を失ったまま食べ物を十分に与えられ、柵の中で生きていく事。個人の本性が、これでもか!と冷静に観察され、綴られる。日本人は、いかに自分で物事を考えるのが下手か、がよくわかります。こんな民族性は、戦争なんかしてはダメですね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 太平洋戦争末期、南方で俘虜となった日本軍兵士たちの歪んだ心理状態をつぶさに書いている。 大岡昇平の著書を読んだことがなかったので、彼の作品の中からこの「俘虜記」を選んでみた。暗号手として任務についていた由である。とにかく大岡氏の学識の豊富さには驚いた。特に外国文学には精通しているようだ。当時一般の兵士で、英語が読め話せるということはかなりのインテリと言っていいだろう。軍隊ではこういう人物が訳の分からない上官からイジメを受けやすいそうだ。俘虜になってからは別だが。 私の叔父は海軍の航空機の整備兵だったと聞いている。あまり詳しいことはわからないが、やはりガダルカナル方面へ向かう途中、米軍機の爆撃にあって撃沈され帰らぬ人となったという。菩提寺には彼の出征当時の写真が収められており、お盆などお参りに行くたびその写真を見て手を合わせたものだ。だから当時兵隊さんたちは戦場でどんな生活をし、どんなことを考えていたのか知りたいと思っていた。大岡氏はこの作品の中で極めて冷静に周りの俘虜たちを観察し記録している。小説というよりは記録文学である。 奇しくもちょうど今、NPTの国際会議が開かれ紛糾している。全体会議の合意が出来ないらしい。核保有国と非保有国との足並みが揃わないのだ。日本は唯一の被爆国として、世界のリーダーたちが被爆地を訪問することを明記するよう提案したが、中国の反対で実現しなかった。私はやむを得ないような気もする。 大岡氏はこの中で面白いことを言っている。原爆投下の報に接した大岡が驚いたのは、原子爆弾という新しい兵器の登場であり、しかもそれがあまりにも破壊的であったからだと書いている。しかし反面「戦争の悲惨は人間が不本意ながら死なねばならぬという一言に尽き、その死に方は問題ではない。」とも言っている。 私も概ね同様に考える。確かに原爆により亡くなった広島、長崎の人々は大変気の毒だが、例えば東京大空襲で亡くなった東京市民とはどんな違いがあるのだろう。亡くなった人にしてみれば、大岡の言うように死に方は問題ではないのかもしれない。 核兵器は無くして欲しい代物だが、現実問題として可能なのだろうか。これまでのように広島、長崎に固執した感情論は世界ではもはや通用しないのではないのか。悲しいが中国には日本は戦争の被害国ではないと言われる始末だ。 もう一つどうしても記しておきたい。それは、もし飢えたら人肉を喰うかという問題である。ある一人の上官がそんな提案をしたそうだが、結局大岡の部隊は幸い最後までそんなシチュエーションにはならなかった。だから大岡はそんなことはなかっただろうと思っている。 しかし最近でも山中に墜落した旅客機の生き残った乗客たちが、亡くなった他の乗客の肉を喰って飢えを凌いだという噂があった。また昔の中国では人喰い風習が実際にあったらしく、これについては魯迅も書いているし、有名な小説水滸伝には度々人を喰う場面が登場する。博学な大岡はそんなこと百も承知だろうが、人喰いなんて想像もしたくなかったのに違いない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| これが小説ということなのだが、どこまでが小説で、どの程度実際の体験に基づいているのか、判断がつかない。 本書はフィリピン敗残兵の捕虜としての生活を描くことで、近代化の後に敗戦した日本の国民がどの様に振る舞い、どの様に生きていくかを描いた著作である。 これを読むと、近代日本陸軍に蔓延っていた悪弊も、日本という国が生産力において到底勝ち得ない国家を相手に戦争を始めたことにしても、さらにいえば現代の労働環境に今も引き継がれている追蹤と卑屈と嫉妬と派閥主義と手段が目的化する非合理性や何もかも、日本という国が貧しかったためであるように思えてならない。 貧しかったから特定の氏族を神格化すると同時に家格の序列の順に負担を強いることで貧弱な地域経済を成り立たせざるをえず、貧しかったから特権に比した社会的責任を果たさせる余裕が社会になく、貧しかったから最貧層の反抗を許さない倫理を導入し、貧しかったから他人のおこぼれに預かろうと追蹤に勤しむ行為を否定できない。 貧しかったから侵略を志し、貧しかったから暴行を慎むだけの機知を得ることができず、貧しかったから近代稀に見る非戦闘員の大量虐殺を敵味方共に引き起こし、貧しかったから民族滅亡の危機になお面子に拘り戦後経済に必要不可欠な資本と労働力を失う愚を侵した。 現代日本も何も変わっていないのではないだろうか。 貧しいからこそ私たちは何が私たちに必要なのかわからず、政治的に大きな声の出せる詐欺師じみた連中に騙されているにすぎないのではないないだろうか。 私が本書を読んだ感想が正しいか、間違っているか、私にはわからない。 ただ、日本人には著者が描いた側面が確かに認められることを確認するのみである。 日本国民であるのなら、是非とも一度読むべき一冊だろう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 『俘虜記』の受けとめ方はいろいろあるだろうが、私にとっては、323ページ(新潮文庫の場合)につきる。アメリカにいたころ、セントルイスの図書館で、終戦前後のアメリカの新聞を調べてみたことがある。『Japs Surrender』 というバカデカイ見出しで日本の降伏を告げる新聞があったが、それは、いいとしても、その日付が1945年8月11日になっていた。『あれっ、日本の終戦記念日は、8月15日だから、降伏は、15日ではなかったのか?』と思った。 『俘虜記』でも、同じような状況が描かれる。レイテ島タクロバンの捕虜収容所に収監されていた大岡昇平は、10日の夜、アメリカ兵たちが、喜びを爆発させて騒ぎ回っているのを見て、戦争の終結を察知する。アメリカが、本国でも戦争現場でも、この時点で、戦争は終わったといったん解釈したことは間違いないだろう。それでは、なぜ、戦争はなお続いたのか。記録によれば、8月14日から8月15日未明にかけてアメリカ軍は日本の都市に対していわゆる「最後の空爆」を敢行したが、それは7市にわたり、少なくとも2,300人以上が死亡したという。 日本は、10日にポッダム宣言を受諾する旨を連合軍側に伝えたが、どうやら、これを日本の降伏受け入れと解釈し、アメリカは、この情報を関係部署に流したようだ。ところが、この受諾には、一つの条件がつけられていて、その条件のほうは、一緒に流されなかったか、流されても重要視されなかったかしたもので、『日本降伏』の情報が先走ってしまった。問題の条件とは、『天皇の身の安全と天皇家の存続を保証する』ということで、それを保証してくれれば、降伏するというものだったらしい(ところで、いろんな本が、この件を述べるにあたって、『国体の護持のため』という言葉を使っているが、言葉の正しい使い方では、『天皇の命乞いのため』と言うべきであろう)。 戦争は終わったと喜んでいたアメリカ軍は、改めて、この条件のことを知り、この期に及んで、まだごねるのかと余計に頭にきて、徹底的な攻撃を加えてきたのだろうか。ただ、確実に言えることは、この条件がなければ、戦争は10日に終わったという一事である。大岡昇平は、323ページに書く。 『8月11日から14日までの4日間に、無意味に死んだ人達の霊にかけても、天皇の存在は有害である』 また、大岡は、芸術院会員を辞退した理由として、『捕虜になった自分が、天皇陛下の前に出て、賞状を貰うのは、あまりにも畏れ多い』と言っていたが、そんなことがあるものか。もし、天皇の前に出て、頭を下げて賞状を貰おうものなら、あの世に行って、戦友たちに顔向けが出来ないと思ったからなのだ。現に、天皇と顔を会わせないで貰える賞は全部もらっている。 大岡昇平は、1988年、12月25日に死亡したが、葬儀、告別式は、本人が絶対に行なってはならぬという遺志を家族に言い渡していたため、行なわれなかった。それからほぼ二週間後の1989年の1月7日に昭和天皇が死去するわけであるが、こっちのほうは、大々的な葬式の準備が、大岡がまだ存命であったころから大ぴらに進められていた。大岡の遺志は、それを意識したものでもあったろうが、何と言っても、レイテ島の山地で、葬式どころか、野ざらしに放置され、朽ち果てていった戦友たちのことが頭にあったのだろう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本書は第二次大戦末期にフィリピン戦線に送られて捕虜になった大岡の捕虜収容所での体験が中心であるが、捕虜になるまでの出兵時から復員後に家になるまでのエピソードは納められていない。こちらは「ある補充兵の戦い」として別の本に纏められており、本書の最初の方が一部重複しているものの、内容的には補完しあう関係にあるので、そちらもオススメである。 彼が過ごした収容所は比較的物資や待遇に恵まれたもので、奇妙に平穏な集団生活の中で、米軍に忠義を尽くし日本兵に冷たく当たり始める元衛生兵、最初に捕虜になったために逆に捕虜のリーダー格となった怪しい人物達、暇つぶしの演芸大会や博打を仕切りだす自然発生的なヤクザ集団、男色の蔓延、など、様々な日本人達の素顔が顕になっていく過程を淡々と描いていて読み応えがある。将校とデキた従軍看護婦長が部下の看護婦を慰安婦化させたエピソードなども生々しい。戦争・平和論としてよりは日本人論として読めるので、説教臭さや人道物語の押し売りを懸念して手に取ってない方にはぜひ読んでほしい。 さて、大岡は高校時代に小林秀雄にフランス語を習っていたことがきっかけで、若い頃に中原中也や河上徹太郎など華麗な文学人脈との交流を体験した人である。そんな彼が収容所の中で戯作作家として評判になったエピソードが面白かったが、僕が泣けたのは仲良くなったドイツ人捕虜に「現代日本最高の詩人」として中原中也の詩を英訳して教えるくだりだ。大岡は大学卒業後、文学者ではなく会社員の道を一旦選んだ人で、メジャーな文学活動を開始するのは復員後である。若き日の華麗な文学的交流を戦場で偲ぶようなことがやっぱりこの人の中にはあったのかもしれない。また、傑作「野火」で描かれる幾つかのエピソードが収容所で出会った兵士達の実体験に取材していることが明らかにされている点も興味深い。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 戦時中の人々はストイックにいきていたのでしょうか、本作を読むとそんなことないことが解ります。全体主義が行き渡り、画一的な世界や心情が広がっていたか、というとそうではないのですね。当たり前ですね、いろいろな人がいますから当然、いろいろな行動があるはずです。いろいろな人がいるから、当然いろいろな思いがあるはずです。 いままで描かれている戦時中の話よりももっと現実的で、安心しました。ということは現代社会で問題になっている「あの国」もきっと、報道には現れない側面を持っているんだな、と直感的に思います。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!