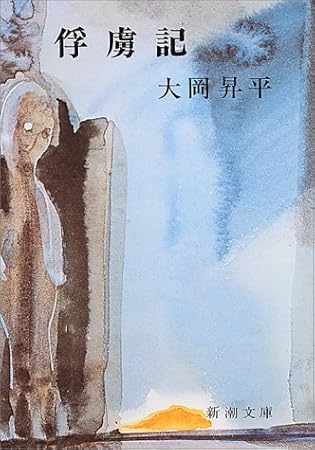■スポンサードリンク
俘虜記
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
俘虜記の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.24pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全4件 1~4 1/1ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| やはり分冊しても良いので、フォントを大きくしてほしい。読みずらい。読者は高齢者が多いはず。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この戦陣訓は捕虜から日本軍の戦略、戦術を漏洩させないための防御策であった。 食糧、武器、弾薬が途絶すれば日本軍も投降して捕虜になればよかったのである。 一定期間が来れば釈放されて再度日本軍に加入される。 しかし日本軍は撤退を転進と呼び、全滅を玉砕と言い換えて投降を許さなかった。 愛国心の強い著者はなぜ捕虜の道を選んだのか。 捕虜になれば白眼視され故郷にも帰れない差別が待っている。 捕虜になることは戦時国際法の兵士の基本的人権である。 これを無視した旧軍とは国際法を無視した国立暴力団であった。 兵士の生殺与奪を握り捕虜になって生き延びることを禁止する。 これが近代的な国軍と言えるのか。 捕虜を許容しておればあれだけの膨大な死傷者を出さずに済んだはずである。 戦地の司令官も殉死する必要はなかった。飢餓で兵士が生死の境界をさまよわずに済んだ。 人肉という異常事態も避けられた。 戦争の指導者たちは自分の命乞いはするが兵士の命は路傍の石と同じで顧みない。 兵士にとっても自分の命を大切に守るという概念はなかった。 どこに死に場所を選ぶかだけであった。 南太平洋での戦闘が悲惨を極めたのも決して降伏しない日本軍のせいである。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この書は「事実の記録」として読まれるべきではない。語りが独断的過ぎるのである。一方これを小説だとすれば、トーマス・マンが言うように「語り」は小説の原材料に過ぎない。では本書は何を言いたいのだろうか。 本書を一編の小説として読む時に先ず感じるのは、構成が極めて奇妙なことである。物語のクライマックスとなるはずの米兵との遭遇が冒頭に出てきて、彼を撃たなかったのは「神の啓示」によるものかと強く仄めかしながら、その想念は、捕虜として収用された病院で従軍牧師から借用した聖書を読みふけったこと、収容所での一夜、「背中に光を負った一人の俘虜」を見た、とする曖昧な記述の後はまったく姿を消してしまう。そうなると物語には別の何か一貫したものが、あるいは作者の意図を越えた何かが隠されているのではないかと疑いたくなる。 そう考えながら読み進めると、提示ははやくも米兵との遭遇場面からあることに気付く。三十六歳の主人公大岡は、米兵を撃たなかった理由に神を求めたがっているが、一人称の大岡の語りはこれに反して、十代とも見える米兵の「著しい若さ」を二度にわたって記述する。本当のところは米兵の若さにあふれる肉体、若さから来る無防備が、大岡に引き金を引くことをためらわせたと読める。理由は至極簡単である。大岡の「ホモセクシャリズム」である。 このことに注意しながら、この後はとりとめない収容所生活譚に「堕して」いってしまう書を読み進めて行くと、例は枚挙に暇がない。大岡が親しむのは、彼自身が認めているように、決まって若い兵士だし、演芸大会では女装に興味を示す一方で、捕虜たちの素人演劇を見物にやってきた二十代の日本人従軍看護婦たちに「がっがり」し、敗戦後に収容された旧知の富永に対して「可愛い」を連発する。 大岡は中年職業兵士たちの狡猾さと比較させて若い兵士の無垢さを描く。これは知識人の大岡が、兵隊生活にすれていない若者こそが再出発する日本を担うべきだとする暗黙の鼓舞である。若い人たちが背負う日本に必要なのは、子孫を増やす男女間の愛で、ホモセクシャルはむしろ背徳になるとする思いから、大岡の語りは、収容所における捕虜たちの生活を先輩−後輩の関係に置き換えようと努力する。だがその語りを通じて、大岡の若くしなやかな男の肉体に対する性的嗜好が暴露されていることを指摘せずに、この書を終わらせることは出来ない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 米軍に捕まり俘虜(捕虜)となり収容所に送られるところから始まり、残りの大部分は収容所での生活について書かれていて、最後に日本に帰還するところで終わる。 戦争小説というよりは、収容所の生活の記録という感じで、特に周りの人の戦歴・性格などを細かく書いている部分が多かった。 読んでみて、筆者は人のことを見抜く洞察力と記憶力が抜群に良いなぁ、と感心した。 もともと三冊だった本を一冊にまとめたものらしく、たまに被っている描写があり、何よりページ数が多くやや冗長とも感じたが、最後まで読みきると、あたかも自分もそこで生活していたかのような気分にもなった。 当時の空気を感じることができて、そういう意味では、とても面白い本だと思う。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!