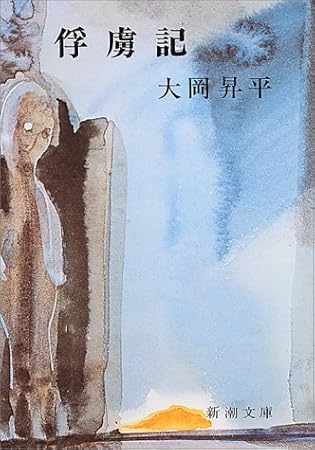■スポンサードリンク
俘虜記
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
俘虜記の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.24pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全34件 21~34 2/2ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| これが小説ということなのだが、どこまでが小説で、どの程度実際の体験に基づいているのか、判断がつかない。 本書はフィリピン敗残兵の捕虜としての生活を描くことで、近代化の後に敗戦した日本の国民がどの様に振る舞い、どの様に生きていくかを描いた著作である。 これを読むと、近代日本陸軍に蔓延っていた悪弊も、日本という国が生産力において到底勝ち得ない国家を相手に戦争を始めたことにしても、さらにいえば現代の労働環境に今も引き継がれている追蹤と卑屈と嫉妬と派閥主義と手段が目的化する非合理性や何もかも、日本という国が貧しかったためであるように思えてならない。 貧しかったから特定の氏族を神格化すると同時に家格の序列の順に負担を強いることで貧弱な地域経済を成り立たせざるをえず、貧しかったから特権に比した社会的責任を果たさせる余裕が社会になく、貧しかったから最貧層の反抗を許さない倫理を導入し、貧しかったから他人のおこぼれに預かろうと追蹤に勤しむ行為を否定できない。 貧しかったから侵略を志し、貧しかったから暴行を慎むだけの機知を得ることができず、貧しかったから近代稀に見る非戦闘員の大量虐殺を敵味方共に引き起こし、貧しかったから民族滅亡の危機になお面子に拘り戦後経済に必要不可欠な資本と労働力を失う愚を侵した。 現代日本も何も変わっていないのではないだろうか。 貧しいからこそ私たちは何が私たちに必要なのかわからず、政治的に大きな声の出せる詐欺師じみた連中に騙されているにすぎないのではないないだろうか。 私が本書を読んだ感想が正しいか、間違っているか、私にはわからない。 ただ、日本人には著者が描いた側面が確かに認められることを確認するのみである。 日本国民であるのなら、是非とも一度読むべき一冊だろう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 自分の行動を説明するための理屈を延々と語っているとしか思えないこの物語が小説だとは全く思えない。 ものすごく説明的な描写の連続で、最後は厭きた・・・ | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 『俘虜記』の受けとめ方はいろいろあるだろうが、私にとっては、323ページ(新潮文庫の場合)につきる。アメリカにいたころ、セントルイスの図書館で、終戦前後のアメリカの新聞を調べてみたことがある。『Japs Surrender』 というバカデカイ見出しで日本の降伏を告げる新聞があったが、それは、いいとしても、その日付が1945年8月11日になっていた。『あれっ、日本の終戦記念日は、8月15日だから、降伏は、15日ではなかったのか?』と思った。 『俘虜記』でも、同じような状況が描かれる。レイテ島タクロバンの捕虜収容所に収監されていた大岡昇平は、10日の夜、アメリカ兵たちが、喜びを爆発させて騒ぎ回っているのを見て、戦争の終結を察知する。アメリカが、本国でも戦争現場でも、この時点で、戦争は終わったといったん解釈したことは間違いないだろう。それでは、なぜ、戦争はなお続いたのか。記録によれば、8月14日から8月15日未明にかけてアメリカ軍は日本の都市に対していわゆる「最後の空爆」を敢行したが、それは7市にわたり、少なくとも2,300人以上が死亡したという。 日本は、10日にポッダム宣言を受諾する旨を連合軍側に伝えたが、どうやら、これを日本の降伏受け入れと解釈し、アメリカは、この情報を関係部署に流したようだ。ところが、この受諾には、一つの条件がつけられていて、その条件のほうは、一緒に流されなかったか、流されても重要視されなかったかしたもので、『日本降伏』の情報が先走ってしまった。問題の条件とは、『天皇の身の安全と天皇家の存続を保証する』ということで、それを保証してくれれば、降伏するというものだったらしい(ところで、いろんな本が、この件を述べるにあたって、『国体の護持のため』という言葉を使っているが、言葉の正しい使い方では、『天皇の命乞いのため』と言うべきであろう)。 戦争は終わったと喜んでいたアメリカ軍は、改めて、この条件のことを知り、この期に及んで、まだごねるのかと余計に頭にきて、徹底的な攻撃を加えてきたのだろうか。ただ、確実に言えることは、この条件がなければ、戦争は10日に終わったという一事である。大岡昇平は、323ページに書く。 『8月11日から14日までの4日間に、無意味に死んだ人達の霊にかけても、天皇の存在は有害である』 また、大岡は、芸術院会員を辞退した理由として、『捕虜になった自分が、天皇陛下の前に出て、賞状を貰うのは、あまりにも畏れ多い』と言っていたが、そんなことがあるものか。もし、天皇の前に出て、頭を下げて賞状を貰おうものなら、あの世に行って、戦友たちに顔向けが出来ないと思ったからなのだ。現に、天皇と顔を会わせないで貰える賞は全部もらっている。 大岡昇平は、1988年、12月25日に死亡したが、葬儀、告別式は、本人が絶対に行なってはならぬという遺志を家族に言い渡していたため、行なわれなかった。それからほぼ二週間後の1989年の1月7日に昭和天皇が死去するわけであるが、こっちのほうは、大々的な葬式の準備が、大岡がまだ存命であったころから大ぴらに進められていた。大岡の遺志は、それを意識したものでもあったろうが、何と言っても、レイテ島の山地で、葬式どころか、野ざらしに放置され、朽ち果てていった戦友たちのことが頭にあったのだろう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本書は第二次大戦末期にフィリピン戦線に送られて捕虜になった大岡の捕虜収容所での体験が中心であるが、捕虜になるまでの出兵時から復員後に家になるまでのエピソードは納められていない。こちらは「ある補充兵の戦い」として別の本に纏められており、本書の最初の方が一部重複しているものの、内容的には補完しあう関係にあるので、そちらもオススメである。 彼が過ごした収容所は比較的物資や待遇に恵まれたもので、奇妙に平穏な集団生活の中で、米軍に忠義を尽くし日本兵に冷たく当たり始める元衛生兵、最初に捕虜になったために逆に捕虜のリーダー格となった怪しい人物達、暇つぶしの演芸大会や博打を仕切りだす自然発生的なヤクザ集団、男色の蔓延、など、様々な日本人達の素顔が顕になっていく過程を淡々と描いていて読み応えがある。将校とデキた従軍看護婦長が部下の看護婦を慰安婦化させたエピソードなども生々しい。戦争・平和論としてよりは日本人論として読めるので、説教臭さや人道物語の押し売りを懸念して手に取ってない方にはぜひ読んでほしい。 さて、大岡は高校時代に小林秀雄にフランス語を習っていたことがきっかけで、若い頃に中原中也や河上徹太郎など華麗な文学人脈との交流を体験した人である。そんな彼が収容所の中で戯作作家として評判になったエピソードが面白かったが、僕が泣けたのは仲良くなったドイツ人捕虜に「現代日本最高の詩人」として中原中也の詩を英訳して教えるくだりだ。大岡は大学卒業後、文学者ではなく会社員の道を一旦選んだ人で、メジャーな文学活動を開始するのは復員後である。若き日の華麗な文学的交流を戦場で偲ぶようなことがやっぱりこの人の中にはあったのかもしれない。また、傑作「野火」で描かれる幾つかのエピソードが収容所で出会った兵士達の実体験に取材していることが明らかにされている点も興味深い。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この書は「事実の記録」として読まれるべきではない。語りが独断的過ぎるのである。一方これを小説だとすれば、トーマス・マンが言うように「語り」は小説の原材料に過ぎない。では本書は何を言いたいのだろうか。 本書を一編の小説として読む時に先ず感じるのは、構成が極めて奇妙なことである。物語のクライマックスとなるはずの米兵との遭遇が冒頭に出てきて、彼を撃たなかったのは「神の啓示」によるものかと強く仄めかしながら、その想念は、捕虜として収用された病院で従軍牧師から借用した聖書を読みふけったこと、収容所での一夜、「背中に光を負った一人の俘虜」を見た、とする曖昧な記述の後はまったく姿を消してしまう。そうなると物語には別の何か一貫したものが、あるいは作者の意図を越えた何かが隠されているのではないかと疑いたくなる。 そう考えながら読み進めると、提示ははやくも米兵との遭遇場面からあることに気付く。三十六歳の主人公大岡は、米兵を撃たなかった理由に神を求めたがっているが、一人称の大岡の語りはこれに反して、十代とも見える米兵の「著しい若さ」を二度にわたって記述する。本当のところは米兵の若さにあふれる肉体、若さから来る無防備が、大岡に引き金を引くことをためらわせたと読める。理由は至極簡単である。大岡の「ホモセクシャリズム」である。 このことに注意しながら、この後はとりとめない収容所生活譚に「堕して」いってしまう書を読み進めて行くと、例は枚挙に暇がない。大岡が親しむのは、彼自身が認めているように、決まって若い兵士だし、演芸大会では女装に興味を示す一方で、捕虜たちの素人演劇を見物にやってきた二十代の日本人従軍看護婦たちに「がっがり」し、敗戦後に収容された旧知の富永に対して「可愛い」を連発する。 大岡は中年職業兵士たちの狡猾さと比較させて若い兵士の無垢さを描く。これは知識人の大岡が、兵隊生活にすれていない若者こそが再出発する日本を担うべきだとする暗黙の鼓舞である。若い人たちが背負う日本に必要なのは、子孫を増やす男女間の愛で、ホモセクシャルはむしろ背徳になるとする思いから、大岡の語りは、収容所における捕虜たちの生活を先輩−後輩の関係に置き換えようと努力する。だがその語りを通じて、大岡の若くしなやかな男の肉体に対する性的嗜好が暴露されていることを指摘せずに、この書を終わらせることは出来ない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 戦時中の人々はストイックにいきていたのでしょうか、本作を読むとそんなことないことが解ります。全体主義が行き渡り、画一的な世界や心情が広がっていたか、というとそうではないのですね。当たり前ですね、いろいろな人がいますから当然、いろいろな行動があるはずです。いろいろな人がいるから、当然いろいろな思いがあるはずです。 いままで描かれている戦時中の話よりももっと現実的で、安心しました。ということは現代社会で問題になっている「あの国」もきっと、報道には現れない側面を持っているんだな、と直感的に思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| もうすぐ来る8月が敗戦の月であることを意識して本書を読んだ。 本書の白眉は著者が自分で自分に「お前は今でも俘虜ではないか」と問いかける一文だ。 本作は 舞台設定こそ 俘虜収容所だ。しかし戦後六十余年を過ぎた二十一世紀の現在に 読んでいて迫ってくるものは本作に描かれる人間の姿が少しも古臭くない点にある。いや 読んでいて自分の周囲と自分自身の姿が喝破されている気がして いささか苦しい思い すら感じた。 本作は帰国直前で筆が置かれている。帰国後の著者は描かれていない。但し 本作を 書いているのは 「帰国後の」著者であり その彼自身が「お前は今でも俘虜ではないか」 と書いた点が重い。 本作は戦争を描いたものではない。戦争は 書いた材料に過ぎない。書いた事は 徹底して「人間とはどういうものか」に尽きる。その厳しい目は書いている著者 自身にも突き刺さっている。自分を突き刺す文体が このように冷静で淡々と しているのも初めて見た。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 著者は大戦末期の昭和19年にフィリピン・ミンドロ島の戦地へ送られるが 米軍の俘虜となり、収容所で約一年間過ごすことになる。 本書はその収容所での体験記が大部分を占めるが、 そこでは我々がイメージする収容所の過酷さや悲惨さは殆んど無い。 俘虜達は、十分過ぎる量の食事を与えられたために次第に肥えていき、 喫煙しないものにも配給される煙草を賭博に用いたり、 干しブドウから酒を密造したり、米軍の物資を盗んで貯め込んだりしている。 そういった俘虜達の強かさや堕落した姿がシニカルに描かれており、 これはあとがきによれば俘虜収容所の事実をかりて、占領下の社会を諷刺するという意図もあったようである。 著者はフランス文学翻訳家でもあり(著者翻訳によるスタンダール作品に接した人もいると思う) その語学力を買われて収容所では通訳となり肉体労働を免除されたりしている。 また、著者が春本(チャタレイ夫人の恋人を下敷きにしたりした)を書いて 収容所内での流行作家になったエピソードなども非常に興味深い。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 米軍に捕まり俘虜(捕虜)となり収容所に送られるところから始まり、残りの大部分は収容所での生活について書かれていて、最後に日本に帰還するところで終わる。 戦争小説というよりは、収容所の生活の記録という感じで、特に周りの人の戦歴・性格などを細かく書いている部分が多かった。 読んでみて、筆者は人のことを見抜く洞察力と記憶力が抜群に良いなぁ、と感心した。 もともと三冊だった本を一冊にまとめたものらしく、たまに被っている描写があり、何よりページ数が多くやや冗長とも感じたが、最後まで読みきると、あたかも自分もそこで生活していたかのような気分にもなった。 当時の空気を感じることができて、そういう意味では、とても面白い本だと思う。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「野火」は教科書で知って、アメリカ在住時に全文を読んだ。この「俘虜記」は、いっそうシニカルだ。特に、序盤の俘虜になるまでに、草むらから目の前まで接近した若い米国兵を大岡氏が撃たなかった心理描写は、今なお名作の誉れが高い。私は「俘虜記」は主にヨーロッパ旅行中に読んだが、異国に居る自己を見つめなおす気分が、大岡氏の心理描写に実にぴったり来て、飛行機の中でグングン読み耽ってしまった。 俘虜である自分たち自身についても批判的で、厳しくドライな気分が行間から読み取れるが、日本軍指導部の批判は実に手厳しく、愚弄、と大岡氏に一刀両断されている。対戦国の米国の民主主義には、実に好意的だ。終戦近くに30歳過ぎて参戦した大岡氏は、それほど日本の軍隊に心から失望し、自由の国アメリカの寛容に心酔していたのだろうか? 私は本作に続き、大岡氏の後年の作「ながい旅」を読んで、大岡氏の心情が分かる気がした。「俘虜記」は戦後まもない作品で、解説にもあるが、進駐軍に遠慮もあったらしい。「ながい旅」でも、最高執行部の愚弄さは繰り返しつつも、戦犯裁判で部下をかばい続け毅然として米国の無差別空爆を立証し、誇り高く巣鴨刑務所に散った岡田中将(司令官)に深い共感をもった文章を綴られている。 大岡氏は、愚弄な作戦を痛烈に批判した。その中で、超然とした誇り高い人間性に深い共感をもって後世の私に伝えてくれた。こうした、大岡氏の置かれた時代も知った上で、なおかつ本作のシニカルで鋭い感性に溢れた人間観察の文章は、ときに爽快であり、ときに今の時代にも通じることを言われており、極めて示唆的である。俘虜となってからの文章が長いが、一気に読み進めてしまう、永遠の名著といえる | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 私の父はソ連の収容所に2年間抑留されていましたが、カスピ海沿岸のグラスノボツク(今ではトルクメニスタン国)だったので気候も温暖で、所謂シベリア抑留者の悲惨さは経験しなかったと言っていました。本書はフィリピンの収容所が舞台で、民主主義国家米軍の下だったこともあり俘虜の待遇はソ連軍よりもよかったようです。例えば米軍と同じ服、一日2700カロリーの食糧が与えられ、干し葡萄からワインも密造していました。父もここまで楽はしていなかったでしょう。 そんなこんなで興味深く読めたのですが、読後、著者はいったい何を一番伝えたかったのだろうという気がしてなりません。俘虜生活の実態?戦争の馬鹿馬鹿しさ?それをとめられなかった国民のだらしなさ?軍隊の不条理?米軍の寛大さ(イラクを見る限り今のがひどい)?それとも通訳として米軍と俘虜の間に入った辛さでしょうか。ところどころに顔を出す、著者のシニカルな視線はそれらいずれをも感じさせています。でも、数多ある戦記ものから本書を際立たせているのは、俘虜という状態が彼らに与えたものが、解放後もなお彼らを支配しているのではないかという指摘だと思います。そのものというのは明示されていませんが、次の一節にヒントがあるのかもしれません。 「我々にとって戦場には別に新しいものはなかったが、収容所にはたしかに新しいものがあった。第一周囲には柵があり中にはPXがあった。戦場から我々には何も残らなかったが、俘虜生活からは確かに残ったものがある。そのものは時々私に囁く。「お前は今でも俘虜ではないか」と。」 10年後再読したい本の一冊です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 私はこの作品をノンフィクションと思い込んで読み始め、カバーに記されている解説により、読み終えた後になって初めて、著者の従軍体験に基づく連作小説であると言うことを知ったのである。しかし、今でも私にとってはノンフィクションであり、どこが虚構に当たるのか、全くわからない。少なくともこの作品を小説とするなら、ジャーナリストの書いた記事でも小説に分類されてしまうものが多々存在することになると思う。 部隊から外れ一人戦場を彷徨っていた著者が、林のへりに倒れ込んでいた時に米兵が現れる。米兵は著者に気付かないのだが、著者は銃の安全装置を外すも結局射たないのである。この「なぜ射たなかったか」についての省察に数ページ費やされていることが、唯一のノンフィクションらしからぬ箇所であろうか。 タイトルから察せられるように、書かれていることの大部分は俘虜収容所内のことである。そして「阿諛」と言う言葉が何度も出てくるが、これが日本人の集団秩序の維持に重要な役割を果たしていることもわかる。戦場と言う極限状況下、収容所内で新たな秩序が形成されていく過程、米兵との対比などを通して、日本人と言うものを見つめ直すことの出来る好著である。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 作者の大岡昇平は京大仏文科卒でスタンダールの研究家でもある。その彼が捕虜になって西洋のヒューマニズムを自分自身で認識したという大きなインパクトがこの作品の最重要項目。敵の捕虜を自分たちと同じ扱いをするという、この作品中の出来事を、京大西洋史の卒業生にしてルネッサンス史の研究者でもある会田雄次の捕虜体験記『アーロン収容所』と読み比べてほしい。そこには西洋のヒューマニズムの限界が、衝撃的な事実でもって描かれているから。アメリカ人とイギリス人と、国は違っているが、敵国の捕虜に対してかくも異なった態度が取れるものか。個人的な違いか、状況の違いか、それとも没落に向かう国と繁栄が約束された国の違いか。二つを読み比べて考えてほしい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 思えば「戦争小説」というものをほとんど読んだことはなかった。それは余り興味がなかったのと同時に、戦争という極限状態に参加し、その最前線で描かれるドラマへ、なにも共感を得られないだろうと諦めに近い感情をもってしまうからだった。空襲が背景にあった小説は幾つか読んだし、爆撃に打ちのめされて行き、街にうごめく人間の退廃的な姿への描写へは、深く心を奪われて来た。俘虜記がどうやら「いちれん」の戦争小説とは違うらしい、と言う読書人ならみんな知っているような批評を目にして、読んでみることにした。 冒頭の「捉まるまで」を読み、その余りにも緻密で分析的な文体へ、まったく新鮮な感覚を覚えた(どうやらこれも発売当時からの評判らしいが)。今までに読んだ小説とは明らかに違った文体で、どちらかと言えばノフィクションや思想書的な感じだ。さらにもっと「乾いた」印象を感じさせる文体で、どんどん引き込まれていく。推理小説的な運びなのだろうか。 フィリピンのミンドロ島でアメリカの捕虜となった一日本兵の手記の形式を取ったこの小説は、徹底して記録的である余り、僕にはその冷静さは十分に演出的ですらあった。むしろノンフィクションとはかけ離れたドラマ性を感じた。現実が「フィクション」よりも「ドラマチック」であると言うのとはまた違う、分析的な眼差しが、その微動だにしない姿勢が貫徹された流れに、とても「芸術的」な感動を覚えたのだ。 著者の太平洋戦争「従軍体験」に基づく「連作小説」という構成から、分厚いし文字も小さく、ただでさえ読むスピードが遅くなりがちな文庫本なのだが、文体へ惹かれる余り、どうしても丁寧に拾おうとし、さらに遅くなる。思想書を読む場合に感じる難解さとは違う、慎重な姿勢になるのだ。読み進む内に感じる感激は、十分に疲労を及ぼし、また慣れ親しむ。だから終盤には早く読み終わりたいのと、この文体から離れる寂しさとで、やや複雑な感情すら抱くのだった。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!