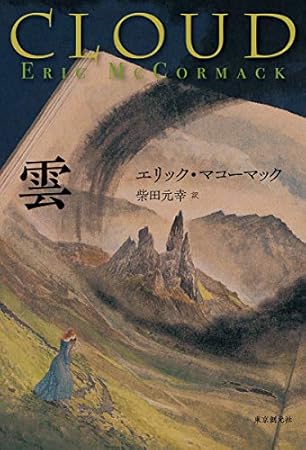■スポンサードリンク
雲
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
雲の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.20pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全7件 1~7 1/1ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 奇妙で時にグロテスクな描写で知られるエリックマコーマックの、ある意味で真っ当な青春小説である。主人公のスティーン・ハリーが、その幼少期から青年期、結婚を経て、息子が成人する時期までの人生を、記憶をもとに一人称で語っていく。 スコットランド出身の文系で現在はカナダに住んでいる主人公は、作者の写し鏡といえそうだ。よくある物語と違い、主人公は主体的に何かを決定し、意欲的に行動するタイプではない。どちらかというと、状況に流され、対応していくうちに、様々な不思議な人々と出会い、様々な不思議な体験をする。 明確なプロットや起承転結のある筋立てではなく、いくつものエピソードが重層的に語られていく。粗筋が要約できないことは、自分の人生を要約することが難しいことと同じであろう。要約はできないのだが、ぼんやりとしてはいるが強い印象がいくつも読者の心に残っていく。 グロテスクで奇異なエピソードも多いのだが、妙な温かさやユーモア、心地よさを感じることのできる作品だ。長編ではあるが、いつの間にか読み終わってしまうことが寂しく、いつまでも「雲」の世界に留まっていたい気持ちになる。 これまで翻訳されている4冊のマコーマック作品の中でも、最高傑作だと思う。一人称の語りは村上春樹氏の一連の作品と同じだが、作品の質は最近の村上作品よりもずっと上だと感じる。お勧めです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| タイトルの「雲」からして、本にまつわる謎解き、または黒曜石雲の事件を巡るストーリーか、と期待に胸踊らすも、主人公にまつわるストーリー展開。本との出会いは閉じられた過去への追憶のきっかけという事か。 ストーリー展開は一筋縄ではいかずバリエーションがあって面白かったが、黒曜石雲のエピソードが謎めいてこちらに期待が膨らんだ分、結末を迎えてなんだか肩透かしをくらった感がある。あの黒曜石雲は一体何だったのだろうか。そういう意味ではこれもリドルストーリー? | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 主人公がメキシコで発見した古書に記された<黒曜石雲>という超常気象をモチーフとした一人称の物語。プロローグで<黒曜石雲>が起きたとされる(真偽不明)ダンケルンというスコットランドの町に主人公が若い頃に居た事からこの事象に興味を持つ事が記される。第一部は主人公の幼少期から"失恋"のためにダンケルンを離れるまでの回想譚が綴られる。淡々とした筆致ながらゴシック・ホラーの風味が濃く、「人にとって(自身を含めた)人は"謎"」というのが主旋律らしい。 第二部はダンケルンを離れてアフリカへの航海を経てカナダの鉱山採掘企業に就職するまで。土地柄のせいか、第一部に比べて幻想味・呪術性に満ちている。幻想味が増した理由は主人公の語り口と旅先で知り合った人々の語り口とが混淆している事にも依る。実際、主人公はマラリアに罹り、熱に浮かされながら見た白昼夢をそのまま綴っているのかも知れない。なお、第二部の冒頭から(プロローグの続きとして)ダンケルンの学芸員と主人公との通信がなされ、きっと、ダンケルンを目指してこの幻想旅は続くのであろう。第三部はそれから25年間程。主人公は企業の令嬢アリシアと結婚し、息子も誕生し、アリシアの父親の死に伴い社長となるが、そのアリシアも死去する。如何にも現実的な内容に映るが、性的倒錯にも多くの筆が割かれ、第二部の登場人物の医者(脳の禁忌の実験中)からダンケルンの衰退を聞かされる。この時点で主人公は古書を入手し、学芸員と主人公とを仲介したのは息子だった事が語られる。第四部とエピローグでは、当然、主人公はダンケルンへと赴き、ある真実を知って<黒曜石雲>に覆われた町の如くに驚愕する。 全編を通じて"猫"が何度も登場するのには意味があるのだろうか ? 性的混迷を中心として上述の主旋律を幻想小説、写実小説、ゴシック・ホラー、魂の遍歴小説という多彩な技巧で描いた秀作だと思った。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 物語の先、というか謎の起源を知りたくて、気持ちが急かされ二日間で読んでしまった。最近読んだものでは、最も面白かった小説だ。エリック・マコーマックを読むのは初めてであり、他の作品を読もうかと考えている。 偶然に眼にした一冊の本をめぐって物語が展開されるところは、最愛の妻子を失い疲弊した存在がたまたま一本の映画(の断片)を自宅のテレビで観ることから物語が始動するポール・オースターの『幻影の書』と似ている。ただし『幻影の書』においては、「私」(『雲』と同じ一人称)が現在地点から述べる叙述で、心を奪われたその映画の監督であり俳優のヘクター・マンについて、すでに一冊の本(《彼の映画をめぐる私の研究書》)を書いたという文章から始まる。「本」が叙述を起動させる点で本書と通じる。さらに『幻影の書』ではヘクター・マンにかかわる女性アルマが書こうとしている大部の彼の伝記が「幻影の書」的に言及され、またヘクター・マンが遺した映画が作品内作品として詳述される。 ポール・オースターの小説のいくつかには、そうした作品内作品、書物内書物、小説内小説といった構造がみられる。マコーマックはオースターより年上だが、彼の小説から影響をうけたのだろうか。それとも元々マコーマック自身にそうした傾向があったのだろうか。 もしかしたらマコーマックは『幻影の書』を読んだのかもしれない。『雲』の主人公が大学生時代に心を寄せる女性の名はディアドリーだが、この名はアルマによって語られるヘクター・マンの人生の変転のなかで、ほんのわずかに登場する。『雲』の主人公の母の名ノーマもやはり『幻影の書』に現われる。これらは偶然というより、マコーマックが『幻影の書』を読んだという合図ではないか。 本書の袖のところに《幻想小説、ミステリ、そしてゴシック小説の魅力を併せ持つ、》と惹句がある。ここにマコーマックとオースターを分かつヒントがある。スコットランド出身のマコーマックはよりゴシック的であり(その意味ではオースターはよりノワール的だ)、イギリスの風土や雰囲気に傾いたところがある。『雲』にはメアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』やH・G・ウェルズ『透明人間』を意識したモチーフがある。この隠し味的部分は小説をいくぶんか分裂させはするものの、妖しい吸引力をこの小説にもたらしている。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「そういう経験をした人は、どんなに純粋な愛もいずれは苦々しく終わる、と思うようになるだろうか」(25頁) 本書のテーマは、人生の愛の遍歴。 父と母の愛により生まれた「私」は、人生の愛の対価を払いながら有料ゲートをいくつも通る。 通るたびに、人生の現実を経験して常識を学ぶ。 愛はいつも天使のように生まれるが、場合によっては悪魔の憎しみに育つこともある。 本書は、主人公が一冊の古書の来歴をめぐって学んだ常識を披露しています。 新婚から五年間も愛する妻を無視して、自分の趣味だけに没頭して、 挙句の果ては妻の持参金までを妻に無断で使えば、妻の憎しみを買って殺される こともありうるよ、と読者に教訓しています。愛は憎しみに変わることも…… 本書のタイトルは『雲』 内容的にも、雲をつかむような、あいまいなイメージのタイトルです。 本書の最初と最後に、『黒曜石雲』というタイトルの古本が登場します。 具体的には、本書は、『黒曜石雲』というタイトルの古本の故事来歴をめぐる小説です。 『黒曜石雲』とは、どんな雲なのでしょう? 真っ黒い、その色と耀きが「黒曜石」という石に似た雲。 その真っ黒な雲が、「磨き込んだ黒曜石」(13頁)のような「空の鏡」(13頁)となって、 地上のダンケアンの町を逆さまに映し出していた。 気象上の出来事に由来している、不気味なお話し。 「あの不気味な鏡雲」(119頁) 真っ黒な、大きなカラス(鴉)のような黒雲。 死人の目玉をくり抜いて食べるという「大鴉(レイヴン)」(436頁) 「大鴉(レイヴン)」を思わせるような黒雲。 「黒曜石雲」という雲のイメージをつかみたくて、 表紙カバーの装画(浅野信二)をしみじみと眺めています。 空で真っ黒に渦を巻く黒雲、黒曜石雲のように。 表紙カバーの左下に描かれた一人の女性の立ち姿。泣いているようです。 この青いドレスの女性は、夫を殺した新婚の妻「イザベル・マクベーン」(430頁) なのでしょうか。 「イザベル・マクベーン」は、自分が起こした夫殺人事件の裁判の中で、 黒曜石雲とは、「私の持参金を使って印刷した五十冊の本です」(434頁) と裁判官に答えています。 「弟と二人で夫の机の上から黒曜石雲も他の文書も皆搔き集め、暖炉に焼(く)べて燃やしました」(434頁) 燃えて灰になった。 だから、『黒曜石雲』というタイトルの古本は現在ほとんど残っていない というわけです。 しかし、この小説で、主人公の「私」は 出張先のメキシコで雨宿りで入った古書店で偶然に 故事来歴の記録がほとんど見つからない珍しい古本『黒曜石雲』と出会います。 その本の調査を専門家に依頼する場面から始まります。 そして、「私」の一生がドラマチックに詳細に語られた後、 専門家の調査で見つかった、驚くべき発見! それを報告する手紙を、主人公が読んで納得する場面で、 この自叙伝のような、古書をめぐる長篇小説は終わります。 この『黒曜石雲』の物語の背景は、 ダンケアンという町で起きた、真っ黒な「大鴉」という名を持つ夫が 妻に殺された事件だったのです。 興味深かったのは、殺された夫の名前「レヴォン」(430頁)です。 この「レヴォン」という名前の意味は、大きなカラス、「大鴉(レイヴン)」です。 真っ黒な不気味な雲と、真っ黒で不気味な大きなカラス。 この不気味な真っ黒さが、この小説の通奏低音のような色彩です。 カア、カア、カア……と読後もいつまでも耳の中で鳴り響いて消えない音。 『黒曜石雲』の原稿を書くことに熱中するあまり、 新婚の妻を「五年間」(431頁)も無視し続けた上、 その原稿を妻の持参金を使って印刷し本を造った夫の話も。 字の読めない妻は、そんな夫についに切れて殺してしまいます。 憎さ余って、 五十冊しか印刷できなかった『黒曜石雲』も燃やして灰にしてしまいます。 なんという事件でしょう。本好きにとっては、胸が痛くなる悲劇です。 妻の持参金を本の印刷代に使ったのがいけなかったのでしょうか。 字の読める図書館の女との姦通がいけなかったのでしょうか。 最後に、小説の人称について。 「本人がだんだん現実を把握する力を失っていくとともに、小説も一人称で書くようになりました」(405頁) 「最初のうちは問題なく、三人称で登場人物について書いています。ところが、しばらくすると、また徐々に、一人称の語り手に戻ってしまうんです。これが躁病状態に戻った確実な徴候です」(405頁) 一人称の小説を読むのが怖くなりました。 《備考》 この本に登場する本のタイトルを列記します。 著者のエリック・マコーマックさんは、五万とある本たちの中から、 これらの本を選び出した理由は何なんでしょう? 気になります。 『黒曜石雲』(11頁、117頁、239頁、322頁、323頁、365頁、367頁、375~384頁、406頁、424頁、427~429頁、436~443頁、445頁) 『往年のグラスゴーの歴史にまつわる真正の人物、情景、出来事の集成』(35頁) 『パブロ・レノフスキー格言集』(45頁) 『若い水夫の為の船旅入門』、『マラッカ海峡の潮流と海流』、『縄結びの手引き』、『メラネシア諸島旅行記』(以上、94頁) 『アップランドの話』(101頁) 『戦争と平和』、『死せる魂』、『魔の山』、『憂鬱の解剖』、『パルムの僧院』、『医師の宗教』、『失われた時を求めて』、『闘士サムソン』、『リヴァイアサン』、『教会政体論』(以上、172頁) 『大草原の甘い情熱』、『ベラドンナの花嫁たち』、『粋な博奕(ばくち)打とじゃじゃ馬娘』、『キッス歓迎』、『星で飾られた愛人』、『誘惑女の舌』、『慈(いつく)しまれた敵』、『ブルームーン・ブロンドレディ』、『アマゾン・エイミー』、『心寂しき我が愛しの人』、『アパッチ・ウーマン』、『真の愛とムース・ジョーから来た牧師』、『妻貸します』、『神経外科医とニンフ』、『野蛮な抱擁』、『熱い耳に愛を囁いて』、『キューピッドのもつれた心』、『愛の炎の島』、『レディを誘惑せよ』、『太古の愛』(以上、172頁) 『断層の査察』、『パラディン・ホテル』、『ウィステリウム』、『コルネットの最後の囁き』、『ダッチ・ライフ』(以上、172頁) 『科学技術全史』、『水圧式深地下揚水機』、『複雑化する世界での明晰な思考』、『ビジネス――戦術的アプローチ』(以上、223頁) 『水圧式深地下揚水機』(231頁) 『図解 スコットランド史』(262頁、321頁) 『四季の書』(278頁) 『マドリード情景集』、『親指トム』、『ヒンドゥークシュ山脈の風習』、『イングランド珠玉のカレンダー 詩的挿絵入り』(以上、280頁) 『カーマスートラ』(281頁) 『島々のベールを剥(は)ぐ』(291頁、297頁) 『麗しき側女』、『鞭打ちを愛するヴィーナス』、『慎み深い性交者』、『叙事詩 張形(はりかた)物語』(以上、280頁) 『Inventio Infortunata(不運な発見)』、『Les Journees de Florbelle(フロルベルの日々)』(以上、310頁) 『My Secret Love(わが秘密の恋)』、『貧しい男と貴婦人』(以上、311頁) 『シェークスピア全集』(313頁) 『ガリヴァー旅行記』(313頁、314頁) 『透明人間』(341頁) 『スコットランド判例集』(429頁、436頁、438頁) 《正誤表》 箇所: 311頁 誤: 革のように見える表紙で閉じた大部の手書き原稿 正: 革のように見える表紙で綴じた大部の手書き原稿 理由: 不統一 「この原稿を綴(と)じている、革と見える表紙は、その猫の皮で作ったものだ」(311頁) 《追記》 <ジョージ・オーウェルの『1984年』を思い出させた表現について> 「自分の部屋の外にいる世界じゅうの人々」は、「人間に変装した巨大な齧歯(げっし)類だと彼女は信じました。ドアの外で、齧歯類たちがヒソヒソ声を上げドアを引っかいて中に入ろうとする音が彼女には聞こえました」(404頁) この文章は、ジョージ・オーウェルの『1984年』を思い出させます。 拷問されている主人公の目の前に空腹のネズミの籠が押し付けられようとする場面です。 ネズミがはじめに狙うのはいちばん柔らかい人間の目玉。 本書『雲』では、「岩場で見つかった母の両目が鳥にえぐり取られていた」(409頁) 『1984年』の「2+2=5」という不合理なプロットも、本書『雲』に登場します。 「たとえば彼らのシャーマンの頭(かしら)は、二足す二は四だという概念を私が説明しようとしても、何の話かまるで呑み込めなかった。逆に私がいかに間違っているかを示そうとしたんだ。糸を二本出してきて、それぞれに二つずつ結び目を作った。そうして私に言うんだ――ほら、これをつなぐにはもうひとつ結び目を作るしかないだろう? そして二本の糸を一緒に縛って、これで五つになったぞ、と来た」(348頁) 女性の顔の<脳手術跡>の記載についても、『1984年』に類似の記載があります。 「顔の左側、長さ七センチくらいの青黒い傷跡が髪の生えぎわから眉に走っている」(332頁) 「鏡を使って額の傷跡を彼女に見せてみたのである」(341頁) 『1984年』では、主人公が愛した女性に<額とこめかみにかけて長い傷痕(きずあと)> があります。拷問で行われた大きな脳手術の傷跡です。 また、『1984年』には「まさかり」が登場しますが、 本書『雲』の最後には「斧」が登場します。 「斧はガレージに戻すつもりだったが、やっぱり枕元に置いておくことにした」(453頁) 『1984年』の「まさかり」は、脅迫の歌の中に登場します。 ♪あんたを寝床に連れてくあかり ♪あんたのお首を切るまさかり 本書『雲』の枕元の斧と、『1984年』の寝床の〈まさかり〉には通ずるところがあります。 本書『雲』では、「事が済んだら、私を八つ裂きにする」(452頁)女という悪夢。 その女から身を守るために、枕元に斧を置いて寝る「私」。 『1984年』では、自分の首を切ろうとするまさかりの〈あかり〉に誘導されて寝床まで連れていかれ、 寝ているうちにそのまさかりで首を切られて殺される、という悪夢。 『1984年』も本書『雲』もどちらも悪夢を描いていると思いました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 奇想満載の短編集『隠し部屋を査察して』で大ファンになった作家です。 スコットランドで起きた謎の気象現象を扱った「黒曜石雲」という本にメキシコの古本屋で出会ったことから回想が始まり、主人公ハリー・スティーンの初老くらいまでの人生がグラスゴーのスラムでの誕生から語られていきます。 マコーマックらしい、奇想、謎めいた話、不気味な話もいろいろ出てきますが、それは本の中だったり、伝聞だったり、彼と関わる他人が行っているなにかだったりと、主人公の周囲にふんわりと存在していることが多かったです。 メインは主人公の愛と家族をめぐる遍歴の物語。 そして冒頭の本の調査が、やがて過去と現代をつなぐことに。 著者の他の長編と比べると、『パラダイス・モーテル』よりは落ち着いていて、『ミステリウム』よりはもやもやしないという印象でした。 作中でそういった過去作のエピソードがひょいと顔を出したりも。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 第四章まで読みましたが、もうすぐ読了してしまうことがとても残念です。ずっとこの世界に浸っていたい。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!