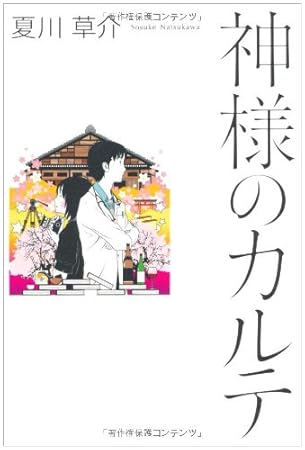■スポンサードリンク
神様のカルテ
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
神様のカルテの評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点3.86pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全164件 141~160 8/9ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 古風な話し方がやけに印象に残る主人公ですが、読んでみると、その古風な話し方ゆえになかなかの魅力を感じる作品になっています。現代医療の現場からの声を小説風に仕上げたものですが、それだけにとどまらない奥行きの深さも心に刻まれます。続編が今夏に刊行されるらしいので、本書を読んでファンになったかたはきっと心待ちにしていることでしょう。医療に関心があるないにかかわりなく多くの人に眺めてほしい一書です。 人は生きているうちは、「生」というものにあまり敏感ではありません。もちろん元気に健やかに暮らせる有難さを感じてはいますが、そもそも「生きるとは何か」という問題を真剣に考えるゆとりはあまりないのではないでしょうか。それはまた「死」についても当てはまるでしょう。「生と死」という人間にとって根源的なものを日常的に直視している職業の1つが医師でありましょうが、「こんな医師もいるんだな」、また「いてほしいな」と思うのです。不器用ながらも要所要所はきちんと締める、そんな医師がここにいます。 本書は地方医療の現状を描くとともに、主人公の医師を取り巻く珍しい人たちとのやり取りも読み応えを増す要因になっています。とくに印象的であるのは、文学者をめざして大学院で研究している通称<学士殿>に対する主人公のセリフ。本当になかなかのセリフです。「学問を行うのに必要なものは、気概であって学歴ではない。熱意であって建て前ではない」。そして「笑う者あらば笑うがいい」と喝破するのです(最後のセリフは、褒めることがほとんどない同僚の女性医師からも「悪くなかったと思うよ」といわれる)。 医師というものが患者に接するときに必要なもの、それは「いたわり」の気持ちでありましょう。医師が患者を支え、救っているのではない。むしろ患者が医師を支え、そして救っているのだと。主人公もこのことに患者の死をもって深く悟ります。どうも余談が過ぎました。記憶に残る作品です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 森見作品に似てると言われてますが、雰囲気が似てるだけで、全く違うと思う。そんな事行ったら探偵モノなや ミステリーなど全く成り立たなくなってしまいます。 恐らく身近な人を癌で亡くした事がある人だと、この作品の主人公や作者の気持ちを本当に理解して読めるし、 いい小説として面白おかしく描かれた小説ではない事もわかるだろう。 一止のようなキャラだからこそこの作品は生きてるし、患者との心の繋がりや、一止が患者からも男からも女 からもモテる設定が成立するし、何より人の死を扱い、末期医療や救急医療といった社会問題を扱っているに もかかわらず話が嫌な重さを持たない。むしろ現場で頑張ってるお医者さんを応援したくなる。 出来のいい小説を読んで読書通を語りたい人は他の作品をどうぞ。 僕の中では本屋大賞1位作品でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 短くて読みやすく、しかし泣かされてしまう良いお話でした。 安曇さんの生き方に非常に感銘を受けました。 彼女はただの患者で、お医者さんのように誰かの命を救うわけ ではないけれど、ただ生きているだけで周りの人を元気づける ことができる。 本当に優れた人間とは、決して頭が良いとか容姿が美しいとか、 何か特別なことができる人ではなくて、ただ丁寧に人に優しく 生きられる人なのだと思いました。 簡単そうで、実はとても難しい。だからこそ価値がある。 彼女のように生きたいです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読後感がこれほどさわやかで、これほど温かい気持ちにしてくれて、これほど 自然に笑わせてくれる本は...何年ぶりでしょうか。 読み始めると、なんだこの文体は、なんだこの会話のぎこちなさは...、と感じる のですが、理由はすぐに告白されます。 患者のことにも、自分が生きていくことにも 真摯に向き合っている主人公。 ...が、これが、まったくハナにつかないのです。きっと、これは、夏川さんが 駆使している、この文体です。 「...いちいちの死に涙を流してはおられぬのだ。」...これは医師としての本音 なのだろうと思います。ところが、この前後の流れの中で捉えると、同じ言葉が 劣悪な環境でのたうちまわる医師の苦悩や忙しさの中でも感じる充実感までを 含んだ言葉に変わるのです。...と書くと、この言葉の前に、苦悩や充実感が、 これでもかというほど強調されていることを想像してしまうかもしれませんね。 ...が、ないんですよ これが。 さらっと、...自然なのです。 医療の現場の問題だけでなく、社会問題を小説の題材に取り込もうとすると、 その部分だけに妙に真実味が出すぎて、浮いてしまうものですが、 ...これを感じさせないのです。 忙殺される医師の日常が、この独特な文体の独白で語られていくためか、 ここだけでなく、語られることのすべてが、素直に、自然に...矛盾することなく、 どれもが真実なのだと、無理なく私の中に入ってきます。 ...だから、きっと構えることもなく、主人公の独白(ひとり語り) と とりまく人たち とのやりとりの場面を想像して、声まで上げて笑ってしまうのです。 ひさしぶりに これは!、という本です。 手ばなしで お薦めします。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| タイトルにある「神様」と宣伝文句の「奇蹟」になんとなく胡散臭さを感じてこれまで敬遠してきたのですが、知人に勧められたので読んでみました。 よかったです。ふいに訪れる涙の瞬間。 温かくて、心地いい、人間の話です。 私は主人公のイチさんが神様だなんて到底思えなかった。 奇蹟も起きてない(と思う)。 けれども、感動するのです。魅力的な登場人物に、すんなりと感情移入できるからでしょうか。 他の方のレビューの指摘にもある通り、現代の医療現場の様々な問題が描かれてもいて、ただ、それについては背景として描かれているだけなので消化不足のように感じる方もいるかもしれません。けれども、現実として医療の現場には問題が山積しているわけなので、これに焦点を絞れという注文は無理でしょうね。 私は、そういう現実の中に生きる医者と患者の、人間同士のかかわりあいを描いた作品であると思いました。 読後は優しい気持ちになれます。ずっと手元に置いておきたいと思える本でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| コンキチ :今回は次男のタクタクとの対談になります。 この本薦めてくれたんだよねっ! 一止さんの患者を診る優しい目がこの作品の メインテーマですよねっ!一人称で語られる つぶやきと365日死を見取るという仕事の徒労と そんな中にも美しく生き、そして逝く瞬間の 荘厳さに圧倒されてしまいました。 タクタク :お父さん好きかなーと思って、自分自身も 主人公の語り口が古風で面白かったし、こんな医者って 実際にはいないかもしれないから、御伽噺みたいにも 感じました、最後の方に患者の逸話が出てきますが コンキチは絶対泣くなと確信しちゃったよ! コンキチ :ハイハイ泣きました 笑 素敵な話です、ウルウル 主人公の細君ハルさんの存在もこの作品に華やかさを 添えていますよね、あっ同じ借家の男爵の最後の絵も 泣けたナー | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 典型的な行動パターンをもつ登場人物と、 明らかに松本市内の実際の場所をモデルとした典型的に心温まる小説。 松本市内に本部がある某国立大学は、作中の大学同様、人文学部はあって文学部はないが、 そんなところが実は物語の伏線だったりするところなんかは、あまりにも露骨である(笑)。 いや、そんな伏線を張ってあっても、気付く人はほとんどいまい。 基本的に登場人物の中に悪人は存在しない。 だから,いささかストーリーが予定調和的すぎるが、安心して読むことができる良書。 作者は実際のお医者様とか。 作中の主人公は、医師の不足により始終忙殺されていて、 自身の結婚記念日にも自宅に帰れないような状況だけど、 作者さんにはせめて今後も小説を書くぐらいの心の余裕があって欲しいと切に願うものである。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 他の多くの医療物と異なり、本作の主人公の専攻が外科や救急ではなく、消化器内科であるのは珍しい。他に消化器内科医が主人公の作品を寡聞にして知らないが、外科や救急に比べて地味だからだろう。 自分も消化器内科医であり興味深く読めたが、地味な領域ゆえに他の医療物と異なり手技描写の印象はERCPくらいしか印象に残らなかった(ERCPも5年目でそれなりにこなすことは珍しくなく、作中の表現は過剰評価と思われる)。 この作品はむしろ日の当りにくい地域医療、老人医療、延命治療、ターミナルケアなどがうまく表現されていて、特に延命治療のくだりはよく共感できた。むやみに命を延ばすことが苦痛を延ばすことにつながりうることに気づかない人はまだまだ多く、現場では苦労する。 ゴッドハンドものの医療作品が多い中(面白いものもあるが、某少年誌で連載されている作品のように稚拙なものもある)、医療の目立たないが大事な部分を取り上げて作品に仕上げたことは素晴らしい。しかし文学としては凡庸と思われたため、星を一つ減らした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 地方の病院に勤務するお医者さんて本当に大変なんだなあとつくづく思いました。真夜中でも早朝でも救急車は走っているし、病院にはちゃんとお医者さんや看護士さんが待っているものなあ。主人公は(作者も)そういう研修医制度や医師不足など社会問題になっている過酷な職場で、奮闘し悩み全力でぶつかっていっている姿が描かれている。だが様々な問題や矛盾にぶつかりながら、個々に深入りせず爽やかな読後感を与えてくれる。それは主人公を取り巻く看護士や医師、患者、アパートの友人そして細君がみんないい人ばかりで、ユーモアの効いた会話や心温まるエピソードをたくさん盛り込んでいるためだと思う。ちなみに、この作者のユーモアのセンスは、森見登美彦氏とは全然違います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 文体がいい。取り巻く人たちが良い。 あたたかさとユーモアのある素敵な小説だと思う。 いわゆる奇跡物語ではない。日常の、尊い人たちの、日々に訪れている奇跡の物語だと思う。 こんな小説を書くお医者さんがいることが喜ばしい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 森見登美彦の語り口をライトにしたような擬古調の文体。適度にコミカルでファンタジックな登場人物たち。「人は死ぬ」ということを、大げさすぎたり斜に構えたりせずに、ありのまま受け止めている。新しい知見はないが、地域医療という現代的課題の一つをしっかりとらえている。 医療現場のゆがみや、否応なく病で死んでゆく高齢者が描かれる一方で、活力にあふれた若者たちは恋をし、夢を語る。だから小説全体が暗くならない。そこがとってもいい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 栗原一止先生や、妻のハルさん、そして同じ「御嶽荘」に住む住人達や、一止先生の同僚の東西看護婦や、患者の安曇さんなど、登場人物達が皆、とても優しく描かれています。 特にハルさんの、「夫があまりの激務に結婚記念日を忘れても、文句ひとつなくおいしいコーヒーを入れつつ夫のそばに寄り添う姿」や、患者の安曇さんと周囲の人々との温かい繋がりなど、読んでいて大変心温まりました。 ただ星を1つ減らしたのは、この本を読んで数日経った今、心に残っているのが「登場人物は温かかった」ということだけだったからです。 読んでいる最中は一止先生の激務ぶりを見て「地域医療の慢性的な人手不足」を感じ、安曇さんの言葉から「大学病院の終末医療の問題」は感じるものの、読み終わり時間が経つと、それらの「現実にある医療問題に対する問題意識」はどこかに消えてなくなってしまいます。 単に「読んでる間、温かい人物像、人間関係に触れることができる小説」と考えれば、文句なく星5つなのですが、「現実にある医療問題」にフォーカスを当てて読む方にとっては、「深みを感じない」とも捉えられるかと思いました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ふるめかしい文体がとてもあったかい。 信州の救急病院で30歳の医者である一止が、不治の病の 患者たちと人生の最後までをともにすごす日々。 死と向き合いながら、時間がゆっくりと流れて行きます。 一止の周りの人々、可愛い細君、同僚の医師や看護師、 アパート「御嶽荘」の面々もとてもあたたかい。 現在の合理性一辺倒の世の中に疲れた人がいたら、この本で癒され て欲しいと思いました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名と本の内容とどう関係してるのかわからない。主人公の若い医師を取り巻く面々は、まさに男なら一度は憧れる理想の人たちだ。細君にしてもしかり。こんなかわいらしいかみさんなんているわけがない。看護師の東西さんも厳しさの中に愛情いっぱい。おばあさんの安曇さんも優しい、優しすぎる。上司も楽しく頼もしい。お仲間の学士どの男爵二人にしてもそうだ。 設定が安易すぎると言われるのかもしれない。しかし、こういう小品もいいのではないかと思う。そんな理想すぎる設定に読者は、どっぷり浸って予定調和のストーリーを楽しむことができる。 それはそれでいいのではないか。私は読んでいて赤い帽子の中のお手紙にすっかり感情移入できた。作者の次作は、期待できないかもしれないが、この作品は好きです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| なかなか良かった。 読後に爽やかさが残った。 私自身、主人公と同様の境遇にあって、この小説を客観視できない。 むしろ、あっと言う間に主人公に成り代わってしまった。 しかも本書は、現実の医療現場から、医師の目線で書かれた小説として、色々な問題が散りばめられている。 地方の地域医療問題。 救急医療問題。 研修医問題。 終末期医療問題。 癌告知の問題。 大学病院・高度医療とは何なのか。 医療現場の内実を知っているほどに、主人公の葛藤はひしひしと伝わってくる。 その葛藤と闘いながら、それでも真面目に生きていこうとする主人公にそれこそ人生のヒントを得たような感慨である。 著者は主人公そのものだと思うが、文語調の言い回しや文体が見事にキャラクターに融合している辺りは、大変な読書家と洞察する。 小説に何を求めるのかで、本作品の評価は変わってくるのかも知れないが、 医療現場のリアリティを理解している読者であるほど、主人公の立ち居振る舞いに敬服せざるを得ないだろう。 次回作を期待せずにはいられない。 でも、著者が本当の臨床家であれば、次回作を期待してはいけないかも知れない(笑)。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本の帯を見て購入したのですが、その帯の通り心温まるストーリーでした。 特に主人公の栗原一止と患者である安曇さんとの交流を描いた個所は、涙が止まりませんでした。 今まで見た小説の中で、これほどまでにストーリーにどっぷり浸れたことはありません。 珠玉の一冊といってもいいでしょう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| まず、沢山笑えます。 主人公のトンチンカン振りというか、妄想というか、登場人物たちとの絡みがおもしろすぎます。 また、多くの文学作品へのオマージュがちりばめられ、渾然一体となっています。 これは、長時間労働の成果とお呼びした方がよろしいのでしょうか??? 読者は我慢せず素直に楽しんだ方が身のためです。 そして、泣けます。 死を前にした患者とそれを看取る周囲の人々、医者、看護師、身寄りの人。 それぞれに物語があり、懸命に生きていることを温かい目線を通して感じさせてくれます。 それを踏まえたエンディングでの独白は、現役のお医者さまだからできるものですね。 人間というのは、病を前にするとどうしても孤独と向き合わないといけない。 そんなときに、不器用だけとちゃんと向かい合ってくれる医者がいてくれたら。 先生、もしお時間があったら、次の作品もお願いします。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 主人公と周りの人たちとのやりとりにユーモアがあり、また暖かさが伝わって来ました。 そして帯の感想にもあるように不意に涙が出てきました。 「末期の患者さんに、神様だったらどんなカルテを書くのだろうか」 主人公にはそんな思いがあるのかも知れない。 それから、きれいな絵のカバーをはずしてびっくり、装丁も良いと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 神様のカルテ 一止先生とハルさんのような夫婦関係っていいですね…♪ 私が年を重ね、病院にお世話になることになったら 一止先生にみてもらいたいです!! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 医者の主人公の一人称によって進行する本作。主人公が夏目漱石をこよなく愛するため、その口調はやや古めかしい。が、なんとなく許せてしまう魅力がある。また主人公の周囲の人間はどれもいい意味で曲者。しかも主人公は心の中で周囲の人間を自分で付けたあだ名で呼んでいるのだけれど、そのあだ名の発想がまた面白い。 しかしストーリー面では医者のドキュメンタリーを感動ドラマ風に仕立てたという印象が強く、折角の設定が生かしきれていないところが。収録されている3話のうちの「門出の桜」はまだ良かったのですが。奥付の作者のプロフィールによると、実際に医療現場に立つ人間とあるので致し方ないかなと。 医療現場の問題も触れるもの、特別ふみこむわけではない。あくまで主人公の多忙の背景として描かれている。なので特別読み込まないといけないとか、ある程度の理解や知識が必要というわけではない。むしろ、非常に読みやすい作品。 (しかし、その読みやすさで文章の意味を上滑りしたのか、それとも読解不足なのか、タイトルである「神様のカルテ」という言葉は一体この作品にとってどういう意味を持つのか分からなかった) 人の優しさに触れたい、そんな時に読むことをオススメします。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!