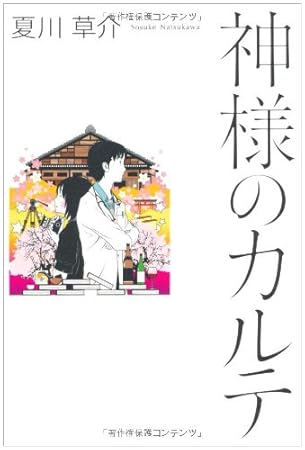■スポンサードリンク
神様のカルテ
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
神様のカルテの評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点3.86pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全164件 101~120 6/9ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 近代小説の影響で、 古い話し言葉を使う主人公を中心に、 長野のとある町の病院を舞台にした作品。 病院の医者や看護師たち、 愛すべき、 アパートの住人たちや、 かわいらしい妻、 それぞれの登場人物の描写が秀逸で、 それが楽しい。 病院の多忙さ、 状況の劣悪さと、 それを淡々とこなす病院スタッフ。 でも、 そこにあるのは、 命を預かること。 そして、最後の、最後の瞬間まで、 そこに思いを寄せ、全力を尽くす人がいるということ。 気負いなく、緩い時間の流れの中で伝わってくる。 それから愛すべき隣人。 学生と、絵描き。 この二人の存在もまた、 主人公を揺さぶる。 そして何より、 愛らしい写真家の妻の存在は、 彼がいわば、日常を戦える理由であり、 背中を支えてくれる柱である。 悲しみが日常から切り離せない職場でありながら、 喜びにあふれている職場でもある。 そんな、ある病院の姿が見えてくる。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 僻地医療に勤務する医師の葛藤を描く本作。 医療の目的とは何か?それを軽やかなタッチと 登場人物で描きます。 小説としても面白いですし、考えさせられるテーマも 多い本でした。 また、奥さんのハルさんがかわいい。 こんな嫁さんほしいなぁなんて思ったりしましたよ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 最初の方は文体に慣れず、ダラダラ読んでた感じだったけど、読んでいくにつれてそれも味に感じ、面白くなってきた。 終わりの方は優しさにあふれていて、軽く涙した。 読んでよかったと思える本。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「仏師」が仏像を大木から削っていくのは、実は仏像の型が初めからあって、その形を掘っているだけである・・・という下りから、最後主人公が自分の進む道の答えを出すときの「猛進するだけが人生ではない、答えは、大切なものはいつもそばにある、足下を掘っていけばそこにある、仏師が仏像の型を掘りだすのと同じように」という考え方に、私も共感し勇気をもらえました。 最先端の技術を学べる環境に飛び込んでいく事ももちろん大切な事です。しかし、今目の前にある事をただ何も考えずに一生懸命にこなしていくと、いつか自然と進むべき道が開けるのではないでしょうか。きっと、今の主人公の頑張りを、見ている人は必ずいて、周りの人が放っておくはずがないと思います。その周りの人たちが、さらなる先の舞台に自然と連れて行ってくれるはずです。受動的な考え方ですが、最近そう思います。 そして何よりよかったのは、細君のかわいらしさ。私もあんなふうにいつも可憐で笑顔の素敵な女性でいたいな、と強く思いました。 またひとつ、自分の理想の女性像が増えました。 本を読むと、素敵な登場人物に巡り合える。これが本の醍醐味ですね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| いいね。語り口調とか、登場人物が、とにかくホッコリさせてくれる。 「迷うた時にこそ立ち止まり、足元に槌をふるえばよい。さすれば、自然そこから大切なものどもが顔を出す。」 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 長野県にある400床ほどの地域中核病院に勤務する若手の消化器内科医が著者。 実際の経験をもとにして、ちょっとそれに肉付けをして書き上げたフィクションのような印象を受けた。 古風な文体で読みにくいかなと思ったが、内容自体には癖がなく、全体を通して読みやすかった。 すごく忙しい地域中核病院に勤務する若手医師。若手なので、なおさら多忙である。 救急当直や外来、入院、検査があり、当直後も通常勤務。 その多忙な中に、職場での友人、『御獄壮』という元旅館をアパートにしてる家で出会った学生と画家の近所仲間、 カメラマンでとても愛らしい妻、終末期の患者さんなどを中心に物語は進行する。 ユーモアも心地よい程度に随所にちりばめられているが、芯にあるのは凄く真面目な内容だ。 地域医療の現状、最先端医療を行う大学病院について、終末期医療について。 私は実際に地域で勤務する内科医だが、これが一般的な地域医療かというと実際はそうではない。 あくまで地域医療の抱える問題の一つを、ちょっとオーバーに表現している印象を受けた。 大学病院にしても、実際にそうかというとそうではない部分もあり、少し誤解を生むかもしれない。 あくまで、『フィクション』として読むのがいいと思う。 上司の勧めであまり期待せずに読んだが、意外にも凄く面白かった。 読んだ後、色々考えさせられるとともに、なんとなく爽やかな気分になれる本です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「なんたる失態だ……私は慨嘆した。」 なかなか評判の良い小説ということで、読もうかどうか迷ってamazon書店の機能、「なか見!検索」を見た私に飛び込んできたのは、「変な文体」。 「釈明の余地のない失態なのである。」と続くが、「慨嘆」「釈明」と、故意に昔ながらの漢語を使っている…。 でも、それは、3ページ目の「私の話しぶりがいささか古風であることに容赦願いたい。」という一文で、「この小説は面白そうだ」という印象に豹変した。 この小説の語り手は、夏目漱石を愛読しており、そのため、日常生活でも、古風な言い回しになっているというのです。 こんな人間、「現実にいる訳がない」。 でも、夏目漱石を愛するあまり、言葉づかいに古めかしいものを使いたくなってしまうという「その気持ちは理解できる」。 まあ、ちょっと奇抜なユーモア小説という気持ちで読んでみれば良いのでは、というのが第一印象でした。 そして、全文を読んだ今、その古風な文体が大成功である、ということを実感。 この小説、地方の大きめの民間病院で、救急医療から、入院患者の主治医、また、通常の外来まで何でもこなすという、目の回るような忙しさの中で職務をこなす、30代の医師の日常を追った物語なのですが、そこには、「明治気質」があふれています。 「明治気質」といっても、もちろん私は明治生まれの人間に接したことはなく、イメージとしての「明治気質」です。 何と言っても、この小説の登場人物達の行動や心理は、「平成」の人間らしくない。 特に第二話のラストなんて、現代の人間では絶対にやらない。 でも、それが、違和感なく物語に溶け込んでいるのは、語り手が、「夏目漱石大好き」で、明治気質に憑依されていることを前提にしているからだと思います。 この小説、映画化されるそうですが、その「文体」はどのように表現されるんだろう?と、変なところに関心を持ってしまいました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| あまりの宣伝っぷりに、天の邪鬼的な半信半疑の心持で手に取ったが、心に沁み渡る且つ大いに勇気づけられる物語だった。 カジュアルな登場人物設定や会話のやりとりに当初は若干のチープさを感じたが、読み慣れるうちに、親しみやすい登場人物に魅力を覚え、また本書の独特のスタイルとして楽しめるようになった。(誤解のないように書いておくと、文章自体はチープでも何でもない。語彙・表現はむしろ豊かだと感じた。) 悩みや迷いがあるなら一歩立ち止まればいいじゃないか。世間の評価に惑わされず、自分の心の声に耳を傾けてみよう。そして、「正解」ではなく、そうやって見つけた「大切なもの」に従おう。そんな主人公の声に勇気づけられる。 印象的だった一節をいくつか。 「だいたい学問をするのに必要なのは、気概であって学歴ではない。こういう当たり前のことが忘れられて久しい世の中である」 「人間にとって心臓が一番大事な臓器だ、などというのはただの幻想だ。そんなものより大事なものは山ほどある−(中略)−人は機械ではないのだ」 「迷うたときこそ立ち止まり、足下に槌をふるえばよい。さすれば、自然そこから大切なものどもが顔を出す」 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 著者自身の経験が反映されているのか、 “想い”が伝わってくる作品。 どこかにも類似話はあるかもしれないけれど、 無理矢理感動を誘ってくる感じはまったくないし、 すっと引き込まれます。 後半になるにつれて感動箇所がどんどん増えてきて 涙→心が温まる→切ない、辛い→・・・ の繰り返しでした。 毎日毎日働いて、くたくたになる。 でもそれ以上にこの仕事が好きで、 相手に感謝されることもあり、 ときにはその逆もあり、 自分も救われるような思いになる。 言葉でうまく説明できないけれど、 そういう人達がこの世の中に存在していることって、 すごくすてきなことだと想う。 癒されました。おすすめです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 久々に清々しい物語を読んだ気がする。地方の医療現場問題と漱石的世界を背景にした一種のファンタジーなのだが、読む者に生きて行く希望と活力そして感動を与えてくれる爽やかな物語である。文体や主人公の個性・台詞を漱石風に仕立てている辺りも微笑ましいが、これは現代におけるファンタジーを小説として成立させるための工夫でもあるのだろう。登場人物をニックネームで呼ぶ辺りは「坊ちゃん」そのものである。他の場所では、漱石や藤村の名前・作品を明示しているのに、こっそりと「夢十夜」中のエピソードを引用している箇所がある辺りも憎い。 主人公の青年医師の一止(合わせて"正")が決してスーパーマンではなく、現実における様々な問題に悩む等身大の人間として描かれている点にも共感が持てる。その上で、自殺未遂後の友人に「生きている。そこに意義がある」とキッパリ語る一方、無為な延命治療に毅然と反対行動を取る点に、作者の思惟が明確に伝わって来る。「気概」を重要視している様も窺える。これらがユーモアに包まれて描かれている点に作者の心遣いが感じられる。一止の他、細君、次郎、男爵、学士殿、東西を初めとする看護師達、大狸、古狐、老患者など全ての登場人物が魅力的で、かつ各人に纏わるエピソードも巧みに構成されている点にも感心した。 「人生、慌てる事はない。懊悩・困難の中でもちょっと立ち止まって(一止)、自分の道を確かめる事で自ずと"正"解が導かれる」というテーマに私も勇気付けられた。多くの方に一読をお薦めしたい素敵な物語である。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この1年で、読んだ中で、「永遠の0」と同等の最高ランクの面白さでした。 量が少ないので、すぐ読めちゃいますが、めちゃくちゃ面白かったです。 続編も、早速、読もうと思ってます。 超おすすめです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 海堂 尊に森見 登美彦、どちらも好きな作家である。 まるでちょっと肩から力を抜いた海堂 尊が森見 登美彦の文体をまねて小説を書くと(決して逆ではなく)こんな作品になるのではないでしょうか? | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| レビューにするの遅くなりましたが、 商品も問題なく、とても早い手配で助かりました(^ ^)☆ ありがとうございました! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 医学部を出た小説家の作品は、いくつか読みました。 安部公房、北杜夫、どちらも個性の強い作家です。安部公房も面白いし、北杜夫も面白いです。 「神様のカルテ」の夏川草介さんは、安部公房や北杜夫よりも、ずっと素直な感じのする方です。作品自体が素直な感じがします。でも、三人に共通するのは、人間に対する愛でしょうか。 神様のカルテは、文章は錬れてないと最初思ったけど、神様のカルテ2になると、ずっと練れてきましたね。さすがです。読み終わると言いたいことはちゃんと伝わって来たなという感じでした。素直で真面目ないい作品です。 北杜夫のドクトルマンボウシリーズのように、冗談が頻繁に混じっているのも好きなのですが、これはこれで愛があって良かったです。 ネットで調べたら、夏川さんの顔写真があって、この作品のとおりのさわやかな優しい感じの方でした。医師として700日間休日のない大変な日々を過ごして来たようです。 そういう中から産まれて来た作品ですね。この神様のカルテとはちょっとおもむきが違うのですがこちらの「般若心経物語」の愛を思い出しました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「人間にとって心臓が一番大切な臓器だ、などというのはただの幻想だ」 という栗原先生の言葉が忘れられません。 どれだけ医学が発達しても結局人を救うのは人であり、何より必要なものは 技術に劣らない優しい心なのだと強く感じられる作品。 学士殿の旅立ちシーン、見たこともないはずの満開の桜が 脳内に鮮明に浮かんで涙が止まりませんでした。 医療のリアルな厳しさと、人と人との目に見えない絆を 同時に教えてくれる一冊。 読み終わった後、御嶽荘に住みたくなりました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「油断していると涙が溢れてしまう。しかもそれはたったの一行で不意に来る。」 帯に書かれた書店員からの推薦の一言。これにつきます。 地域医療の最前線に従事する5年目の内科医・栗原一止、地方病院の一般病棟で医局に所属せず、日々目一杯働いている。 夏目漱石好きが高じて、話しぶりは古風で、同僚や先輩医師にも「山先生」「海先生」「古狸」「大狸」とあだ名をつけてしまうほどの変わり者。 山岳写真家の妻を愛し、患者のことで頭を一杯にする。 「素敵」なんて言葉で片付けたくない医師の物語。 号泣させようと御涙頂戴のストーリーが展開する訳ではありません。 でも、一瞬で泣かされてしまいます。 言葉の選択の美しさを感じる小説です。 「迷うた時にこそ立ち止まり、足下に槌をふるえばよい。さすれば、自然そこから大切なものどもが顔を出す。 そんなわかりきったことを人が忘れてしまったのは、いつのころからであろうか。 足もとの宝に気づきもせず遠く遠くを眺めやり、前へ前へとすすむことだけが正しいことだと吹聴されるような世の中に、いつのまになったのであろう。 そうではあるまい。 惑い苦悩した時にこそ、立ち止まらねばならぬ。」 (P204) | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 地方病院での多忙を極める医師の過酷な日常が愉快に語られます。 夏目漱石の『草枕』を耽溺する語り手の、奇妙な擬古文調の語り口が楽しく読めます。 カワユイ妻とのホホエマシイ夫婦愛や特異な同宿人や 奇っ怪な同僚医師や思慮深い上級医師や看護師、 そして個性的な患者に囲まれた日々が愉快な口調で綴られます。 印象的だったのは、患者の死に立ち会い、しあわせな死が感動的に描かれるところです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読後感のこの軽さ、さわやかさ… 疲れてるときや、なっっっっっっっんにも考えたくない時、本でまで難しいこと見たくないんだよ!って時に、 箸休め的な読み物として読むといいかもしれません。 日々の生活にくたくたに疲れきっているときに、1と2を読みましたが、物凄く癒されました…。 心にしみたな〜。 口調が…とか、言ってる人もいますが、疲れてるとそんなものが全く気になりません。 むしろ、この設定の数々に「あー、なんかいいな、久々に。こういう甘酸っぱい感じ」という、久々にレモンキャンディでも食べたような気分になってきます。 でも、あえて4点。 この軽さが気になる人、ダメな人はいると思う。 ライトノベル読んでるみたいでした。あと、わたし、泣けなかったです…グッとはきましたが。 私はあえてこれを小・中学生に読んで貰いたいな。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 私にはまだ入院経験がないので、一人の医師がこうやって 一人ひとりの患者さんに対して思いを馳せることがあるのかな? というのは疑問になります。 確かに地方病院の医師不足は深刻だし、 高齢化社会の孤独な人たちの問題、 などさまざまな問題が定義されていて考えさせられました。 だけど2も買うか?と言われたらちょっと考える。 何かが…足りないというか、少し軽すぎるような気がする。 著者は日本の古典文学をしっかりと読んできたことは察せられる。 ユーモアもあっていいし…。 でも続きは期待できない感じがする。なんだろうこの感じは… | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| とても感動する話しで、いつの間にか涙が流れていました。 登場人物それぞれがいい人ばかりです。2も発売後すぐに買いに行きました。映画化されるのも楽しみです。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!