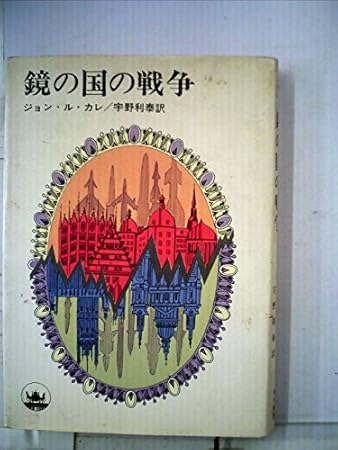鏡の国の戦争
- 映画化 (237)
【この小説が収録されている参考書籍】 |
■報告関係 ※気になる点がありましたらお知らせください。 |
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点7.00pt | ||||||||
■スポンサードリンク
サイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
前作『寒い国から帰ってきたスパイ』は世界的ベストセラーとなり、それがきっかけでル・カレは専業作家となった。その第1作が本書である。 | ||||
| ||||
|
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ジョン・ル・カレの4作目『鏡の国の戦争』(1965年=原題:The Looking-Glass War)を読むことにした。 この作品は、『寒い国から帰って来たスパイ』がベストセラーになり大金を手にし官吏を退職して作家として独立した最初の作品である。 英国の諜報組織は複雑であり、60年代には外務省に所属する「サーカス」と、陸軍省内の部局MI(陸軍情報局)とに分かれていた。 ジョージ・スマイリーが所属するのは「サーカス」であり、本作では陸軍省内の部局の話である。 この部局は戦後縮小され活躍する範囲も限られていた。 部局を率いるルクラークが過去の栄光よ今一度と躍起になってネタ探しをしていたところに東ドイツから重大な情報をもって亡命した男がいた。 それは東ドイツ独自でミサイル基地を設営するというものであった。(評者にはガセネタと思えたが) この亡命者の情報自体がそもそもの発端であるが、ルクラークは、組織の再構築にこれを利用することで大臣に働きかけ、それなりの予算を獲得して東ドイツへ潜行員を送り込む計画を実行する。 しかし部局員のほとんどがロートルばかりで、東ドイツへ送り込む潜行員もポーランド系のロートルである。 「サーカス」から借りた無線機など25年も昔のものである。(サーカスは、わざと旧式を貸し出した) この作戦を失敗させ、ルクラークの組織の凋落を謀る「サーカス」管理官の計画なのを、ジョージ・スマイリーだけは知っていた。 スマイリーの性格から管理官にむかって皮肉を言うが無視されてしまう。 が、管理官の命令でスマイリーが東ドイツに行き、彼らに引導を渡すところでこの物語は終えている。 可哀そうなのは潜行員のライザーと若い部員のエイヴリーだろう。 敵は外ばかりではなく内にも居るという、ル・カレならではの皮肉な小説です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 本書の原著を繙くと、1991年7月付けの序文で著者は、本書は前作の『寒い国から帰ってきたスパイ』(以下『寒い国』)から趣向を変えてよりリアルなスパイ小説を書こうとした、当時の自分のベストを尽くした作品だった、と回想している。その序文を読んだからいうわけではないが、世界的ベストセラー『寒い国』より本書のほうが私には面白かったし、本書の登場人物たちにより共鳴できた。何より、本書には「嫌な奴」が一人も登場しない(イギリス諜報部チーフのコントロールは除く)のだ。 私はなぜそう感じたのだろうか。最大の理由は主人公たちの描き方の違いである。『寒い国』の主人公アレック・リーマスは、リズ・ゴールドと支え合って生きている。50歳のリーマスが、22、3歳のゴールドと年齢差を乗り越えて結ばれるとか、リーマスが病気になったときゴールドが献身的に看病する場面など、2人の恋愛は理想的すぎて“あまりに人間的”(ニーチェ)なのだ。そのため『寒い国』はときに、あの有名な東ドイツでの裁判シーンやベルリンの壁のラストシーンですら、お涙頂戴のメロドラマに転じてしまう。 本書のスパイたちは孤高の人だ。潜行員テイラーは雪に覆われたフィンランドで、潜行員ライザーは東ドイツの寒村で、人知れず消えていく。ライザーは、死んだような町で死んだように生きているアンナにプロポーズまでしながら、捕まりそうになると彼女を人質にした。『寒い国』では、リーマスとゴールドは添い遂げた。寂寥感と隣り合わせの臨場感、緊迫感。読み終わった後の(いい意味での)後味の悪さ。本書にはスパイ小説を読む醍醐味がある。 最後に一言。本書には裏テーマが見え隠れしている。1950年代以降の現代社会(本書の時代設定は1962年のキューバ危機直後)では、諜報組織にもホワイトカラー化が進行中だ。ホワイトカラーの時代にはあらゆる組織が官僚制化されていく。本書の登場人物たちは、自分の勤め先や関連する他部署を「役所」と呼ぶ。本書のラスト、現場で働くスパイたちのもとへ「役所」から派遣されたジョージ・スマイリーがやってきた。彼は古参スパイたちの仕事ぶりにダメだしをして、イギリス政府の意向を忖度し、後始末をして帰っていった。ホワイトカラー化の進行とはまた、事務仕事のルーティン化であり、膨大な書類の整理である。一件落着の後、古参スパイの責任者ルクラークは唐突に、書庫にファイルを保存する方式は時代遅れだと、最新OA機器の導入を宣言した。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| "「どこのひとに通信してるの?」彼女はまたきいた。 「だれでもない。だれも聞いてはいないんだ」" シビレル。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 大昔に読んだきりだったところに映画化作品があると知って映画を見てみました。それがなかなかの出来で(1970年同名映画化作品)、映画が原作に忠実に作られたものかどうか知りたくなり、再読してみましたが、こういう話だったのかと、完全にストーリーを忘れていたことに情けない思いをしました(苦笑)。映画は一部以外はほぼ原作に忠実でした。たとえば、映画では東ドイツに潜入するスパイは密入国してきたばかりのポーランド人青年でしたが、原作ではすでに英国に長年在住している40歳のポーランド系英国人です。映画は時間内におさめるという縛りがあるのでどうしても話が簡略化されがちですが、やはり原作の方が話の流れや人物の心理が詳細にわかるようになっています。 ル・カレの作品は、それでなくても地味ですが、この作品は東西冷戦時代のダイナミックな情報戦を描いたものですらなく、英国に2つ存在した外務省所属、そして軍部所属の2つの諜報組織の縄張りや権力争いを中心に描いているので、スマイリー3部作よりもさらに地味に感じられるかもしれません。弱体化して予算を縮小されていた軍部側が盛り返すために、本来必要かどうかもわからない作戦を企て、しかも最新の機器などの情報も持たず、時代遅れとなった知識と技術で、犠牲者を出しても冷酷にかえりみない、上司の虚栄心のために振り回される末端職員の運命や理不尽さがじっくりと描かれています。派手なアクションも銃撃戦もありませんので、ハラハラドキドキの作品が好きな人にはつまらないと思います。ただ、ル・カレの作品にはいつも、これこそが本当に国際情勢の裏で起こっていることなのかもしれないと思わせる、じわじわとくる怖さがあります。現実に近いことだから、かっきりした起承転結も、ハッピーエンドの読後感のよさもありません。が、渋いいぶし銀の魅力的作品です。重厚なエスピオナージものを読みたい方に、おすすめです。スマイリーの3部作以前の姿が垣間見られるのも興味深いです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 彼が主人公の作品ではないが、いわゆるスマイリー三部作ではスパイの世界での理想的な人物像として描かれるジョージ・スマイリーの性格形成段階にある作品の一つとして興味深く読んだ。 三部作中の「スクールボーイ閣下」でも、彼は結果的に「ジョー」を見捨てるが、そこには、ジョー側の非も認められるし、明示的には描かれないものの、その結果に至るまでの深い苦悩や悔恨の情が読み取れる。しかし、本作における彼はもう少しドライだ。 それは、作者自身がまだ彼の人物像について固め切っていなかったからではあろうが、スマイリーの精神成熟過程とも読めるところが面白い。 一方で、本作では、スマイリー属する外務省系情報機関(サーカス)に対し国防省系の機関の話がメインになる(この辺の組織論については訳者あとがきに詳しい)のだが、「作戦」が始まるまでのこの機関の描き方がまるでコメディーで、「ここまで国防省系機関をおちょくってしまっついいの?」という感じだったが、流石にオペレーションが始まると、第二次大戦中はそれなりに鳴らした機関だけあって、単に戦後の波に乗れなかった、ということなんだな、という感じもしてくる。最初の方にあったように、平時にはダメ男でも、実際の戦争が始まると、決断力が別人のように上がる、ということはあるのかもしれない。ま、結局はその「戦争」もイリュージョンなんだけれど。 しかし、本作でのスマイリーの判断も、冷戦時代の非情な国際関係の中では正しい(やむを得ない)とは考えるのだが、やはり、最後までジョーを庇おうとするエイブリーには共感を持ってしまう。その辺に関しては、作者の視点は少し意地悪いのだけど。 考えるに、本作は、「北の国から…」で大ブレイクした作者が、「いい気になっていた」(本人の自伝に基づく)時に書かれたもの。その辺も、本作のスマイリーの人格に影響を与えているのかもしれない。 いずれにせよ、三部作でスマイリー・ファンになった人には、処女作「死者から…」、次作「高貴なる…」とともに必読の書と考える。できれば発刊年順で、この二作を読んでから本書を読むのがいいと思う。 | ||||
| ||||
|
その他、Amazon書評・レビューが 9件あります。
Amazon書評・レビューを見る
■スポンサードリンク
|
|
|