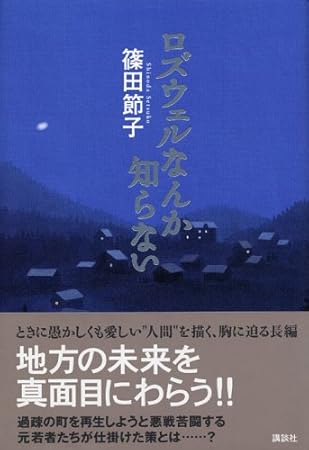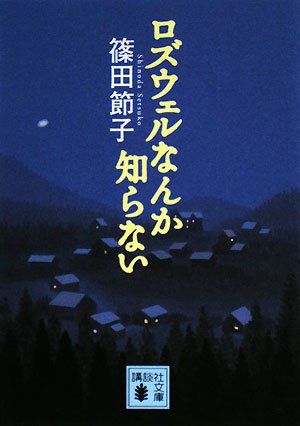■スポンサードリンク
ロズウェルなんか知らない
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
ロズウェルなんか知らないの評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.56pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全39件 21~39 2/2ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| かなり分厚い本なのですが、読み終えるまでホントに眠れない。読み終えたあと、もう一度めくりたくなる本です。 中心になっているのは、東京の大学をでたものの、何だかんだの理由で、また田舎に戻ってしまい、「こんなはずじゃなかったのに」とぼやいている田舎の青年団(というにはトウのたってる独身男たち)です。 地方に住んでいる方は、舞台になっている地方の空気やそこに住んでいる人間の閉塞感が、ありありと感じられるのではないでしょうか。 この本の凄さは、村おこしの難しさをリアルに描いている点でしょう。 地方で金と実権を握っているのは高齢者で、かれらの出来上がってしまった固定観念を覆すのは行政のお題目では不可能で、それでもまだお題目を振りかざす小役人と、崖っぷちにいるのに動かない年寄りの現実には、ため息がでます。 青年団の個々がていねいに描かれ、なおかつセンチにならない突き放し方が気持ちいいです。 頭の固い爺婆もリスペクトをもって描かれてます。 日本人全員に読んでほしい本です。文章も読みやすくて◎ | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 最初は本のタイトルが妙に引っ掛かった。「ロズウェル」ってアメリカの有名なUFO事件「ロズウェル事件」が起こった所だよなぁ・・と。てことはUFOとか宇宙人とか出て来る、そういう小説か!?と思ったんですが、それにしちゃタイトル自体はそういうのを突き放してて、装丁画の雰囲気もそんな感じではない。帯に書かれたコピー文は『過疎の故郷を救え!』だ。ペラペラと巻末の皆神龍太郎氏の解説を読んで「あ、なるほど!そういう話ね」と思いましたが、その時は購入までは考えてませんでした。購入のきっかけは最近話題になった「釧路川に迷い込んだ一匹のラッコ」のニュース。街中に姿を現す事などないラッコが、一匹だけとはいえ、人間が住む街中の川に現れ、突然降って湧いたようなラッコフィーバーに、このご時世町にちょっとした活気をもたらし、それなりの経済効果もあったようで・・。これは同じ北海道といえども、内陸の町にいる者としては結構羨ましいニュースでした。何をきっかけとして町が元気になるか・・・ってのは、今日本の地方の小さな町や村が求めてやまないモノなんじゃないか。何ら売りの無い所なら、必死になって、どんなきっかけからでも売りを作りだそうとするでしょう。この本のお話がまさにそれです。様々な魅力に事欠かない都会と違って、観光事業も撤退するような寂れた町をいかに甦らすか・・読み進めて行く内に、どんどん彼等の奮闘する姿に、応援する気持ちが芽生えてきます。現実に存在する団体名や個人名なども出て来て、それなりのお遊びもありますが、話自体も個々の思惑とかリアルで考えさせるようなところもあり、楽しめました。頁数は多いですが非常に読みやすいです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 他の篠田節子の作品と一風違った小説でした。 え?コレ本当に篠田節子?と思ったくらい。 なんか読んでいてニヤニヤというかニコニコしてしまう話。 途中で「あー面白い」読み終わって「あー面白かった」と思える話。 篠田節子というだけであまり中身も知らずに買ってしまったのですが読んでよかったです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 町おこしという題材の小説は初めて読みました。 普段、何気なく観光へ行く立場としては、 裏側でこんな思惑があったりするんだ…感じました。 観光客の観光に対する価値を考えて企画を練ることは マーケティングの勉強になるなぁと思いました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読み応え十分。村おこしに励む青年たちを描いた小説はいろいろあるけれど、 これは実に登場人物も展開も面白く、そして緻密に描かれていてぐんぐん引き込まれて読んだ。ほんとに面白かった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 死に体の民宿村をなんとかしようと立ち上がる青年クラブ 地域と行政 良識と創意 村おこしの切実さと文化祭のりのイベント開催の楽しさにひっぱられ 一息で読み終えました。 あ〜、面白かった。 安定した語り口で読み手をどんどんと篠田ワールドに誘っていき 気がついたときには、違う地平に立つ気分に どの作品も読んで損をしたということのない大好きな作家さんです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| スキー場,遊園地といった外部の観光資源だけを当てにして,これらが潰れてしまうと何も残らず,ただ滅びるのを待つだけ・・・そんな中,何とか観光客を呼び込もうとイベントを企画する靖夫らの努力は,読んでいて胃が痛くなるように辛い。 そこに沸いた四次元世界騒動。靖夫らのグループが一部を演出して作り出しただけなのに,勝手に神秘世界を「発見」する霊能者や,悪乗りする村人,アブダクション騒ぎまで起こってしまい,当事者の意図を超えて大きな騒ぎになってしまう。 そんなコミカルな騒ぎの中でも,靖夫らの日常生活が淡々と描かれていて,実際の騒動のドキュメントを読んでいるようだった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| なんにもない村がUFOで村おこし!? 「ロズウェル〜」というタイトルからして、UFOネタ好きの私をくすぐる! 娯楽作品として大いに楽しみながら一気に読んでしまいました。 後半の展開がわかりやすかったのが星4つというところですが、 最近ワクワクしてないなぁという方にはかなりオススメです。 かくいう私も久しぶりにワクワクしました。 その反面、作品の奥底に流れる「観光」「地域復興」に対する問題点もちりばめられ、 人ごととは思えない切実な感覚も見え隠れしていたように思います。 フィクションではあるけれど、あながち嘘でもない(つまり現実)のではないでしょうか。 お金をかけて立派な建物をつくる=観光地として復興できる、という図式は もう時代遅れなのかもしれません。観光に求めているのはどんな感覚であれ、 ファンタジー(幻想)であるということを、我ながら改めて感じた作品でした。 私が観光に行ったとき、あーあ、こんな立派な建物なのになんで中身がないんだろう?と 地方の立派な建物に行くたびに感じるあの退屈感。 自分の中の疑問と退屈感が、この本によって展開し進化していった気がします。 ふと我が身を振り返る・・・ 私達は常にファンタジーを作りながら生きているんですね。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 西暦2030年には人口がゼロになってしまう。 このままでは過疎が進んで村そのものが無くなってしまう。 何十年も前からの古い考え方から抜け出せず、 何もできないままおざなりに時間が過ぎていくことに 業を煮やした、そろそろ中年の声も近づいてきた元若者たち。 彼らが打った一世一代の仕掛けは!? 偶然に偶然が重なって ワクワクと物語を欲する生き物である様々な人たちが入り乱れ 事態はすごいことになっていく!!いや〜面白かった!! そして久しぶりに本を読んでニンマリしたり、ハラハラしたり、 爽やかな感動を感じました♪ ある意味いろんなヒントを与えてくれる作品かも… | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| UFOを観光まちづくりの目玉にして活性化しようという、さびれた町の青年クラブの奮闘記。ではあるんだけど、どちらかというと巻き込まれ型のコメディと呼んだ方がふさわしいかもしれない。 最初からUFOの町を企画したわけではないが、次々と災厄のように降りかかってくる幸運と中傷の連続。うまく行くときはうまく行くが、つまずけばどこまでも転げ落ちる、かに思われるが、助け舟はまた意外なところから突然にやってくる。 何より住民一人ひとりの描きわけがうまいから、町全体が立体的に感じられる。それぞれの演技が光るオールスターキャストといった趣向。実際に芝居をする場面も用意されているし。 日本中いたるところに、過疎という現実はある。駒木野町みたいにうまく行くところは少ないだろう。それは一概に住民のせいには出来ない。もともとよそ者の鏑木(こいつは、本当に胡散臭いが、憎めない)や牧場主川崎みたいな人間はいつも前向きだ。背負ってるものがないから。主人公靖夫のように、どうすればいいんだ。他にどうしようがあるのかと悩んでいる人たちの方が多いはずだ。 この小説は彼らの起死回生の処方箋になるというマニュアルではない。しかし、ちょっと肩の力を抜くことを教えてくれると思う。それは何のためになるのかわからない小説の立派な効用のひとつだろう。 本文から「観光とは退屈な人生に、劇場を作り出すことだ。これまでの実人生で脇役や通行人に過ぎなかった人々は、離れた土地でもてなされながら主役を演じる。」 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| UFOで町おこしを計画する段階は、コミカルでつい笑ってしまう。人間は本当その気になると、現実と虚像の区別がつかなくなる。オカルト現象もその類なのかも知れない。しかし、冷静に考えると、この計画はでっち上げに満ちているのだから、しっぺ返しを食らう事は必定だ。ところが、その気になってしまった青年グループに、それを悟る理性が無くなってしまった。 理性が無くなったのは、青年グループだけでは無かった。 町民やアイドル司会者まで、簡単に巻き込まれるのは面白い。 人間の心理とは、その程度に、雰囲気に呑まれやすいものなのだ。 本書では、多くの凄味のある作品を発表している著者の、コミカルな面が楽しめる。同時に人間の心理に、楔を打ち込む。また、最終部分は感銘を呼ぶ。青年グループの努力は無駄では無かった。楽しい作品なので、一気に読み上げた。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 過疎の町を舞台にしたドタバタというふれこみに かつてのベストセラー、井上ひさし「吉里吉里人」を 連想してしまいましたが、まったくの別物でした。 かつてはスキー場でなんとか過疎を食い止めていた ある村の若者たちが、役場も敵に回して ひょんなことから異星人伝説やアブダクションをネタに 村おこしをしてしまうという痛快な喜劇です。 日本の地方行政を強烈に皮肉って、 テンポのいい、群像劇に仕上げています。 主人公たちも、傍役たちも丁寧に書き込まれていて 最後まで飽きさせません。 最初はとんでもない村おこしだと馬鹿にしていた人たちが、 ひとたびマスコミに取り上げられると、 仕込んでもいないことをいきいきと語りだすところなんか 実に見事です。 映像化するなら、主人公の青年たちを ユースケ・サンタマリアあたりで配役してもらいたいです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 私自身が観光地の活性化に少しばかり係わっていることもあり、この本の中に描かれた人々の姿からは、北海道のある町で観光にまじめに取り組む方々の顔が浮かんできます。そうやって人物像を明確にすることでかなり現実味を帯びた世界を楽しむことができました。 私に限らず少しでも観光にかかわる方であれば、『そうそう、こんな人いるよなぁ』『おいらの悩んでることと同じだよ』『こんなことできれば面白いよな』など、身近に感じているさまざまな事や足をひっぱる少しばかり(?)問題な人たちの姿が、この本の中にはテンコ盛りです。 実は、この本は過疎の田舎をテーマにしながらも、それは多くの企業や組織にもあてはまる問題なのかも知れません。このまま行けば経営が立ち行かなくなると分かっていながら、何も手を打たずに会社にしがみつく経営者や自治体の長たち。悪いのは全てひ人のせい。それはこの本の中の民宿や商店のお年より達の姿にかぶります。そんな日本の姿も、ここには秘められているように感じます。 しかし、この本はあきらめてはいません。それらの問題を解決してゆくのは、当初のきっかけは余所者の行動であったとしても、やはり地元のみんなの頑張りでしかないのだよ。きっと何とかなるはずだよ。そんな暖かな応援が聞こえてきます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 過疎の町に住む元若者たちが、始めた村おこしとは。ちなみにタイトルのロズウェルとは、宇宙人解剖ビデオ(真偽は定かではありませんが)が撮影された地名です。過疎の村に住んでいて、深刻に考えている人には怒られるかもしれませんが、最大多数を狙うよりも、マニアを狙った村おこしもあっていいかなと(実際にあるのかな)思わせてします。面白いです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| こういういわゆる普通の小説で5回通りも読んでしまうなんて自分でも驚きです。いやー、面白かったです。篠田節子さんの作品は何でも好きですが私の中ではこれが最高傑作。元気のない過疎地の人、必読。心霊あり廃墟ありUFOあり。子供がほとんど出てこないのも意図的?作中の駒木野の今後を応援したい。超おすすめ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「ゴサインタン」で内なる神との交信の思いを壮大に描いた筆者が、一転して正反対の、町おこしに神なるものを使おうとする人々の虚心を描いた。偽者と本物、偽りと真実、正論と実益の交錯と葛藤は、三谷幸喜の「合い言葉は勇気」を想起する。ごく普通の村の若者たちが、規程や形式にとらわれずに、知恵を生み出し成功していくさまは、猪瀬直樹が「日本凡人伝」で描いた等身大の人間像そのままだ。筆者の視点が、だんだんと、ごく普通の市民のレベルに近づいていると思えるのは、筆者がごく親しいという重松清氏の影響だと思うのは、僭越だろうか。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 村おこしがテーマ。田舎者の私には、興味津々でした。話の展開もほどよく、会話部分も不自然さがないので、入り込んでしまいました。結構な厚みの本なので、最初は抵抗があるかもしれませんが、読み進めると止まらなくなります。久々に、テレビも見ずネットもメールもせずに読みました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| UFOで村おこししようとする過疎の村のお話。起承転結がホントに良く出来てて、承の部分はホントにプロジェクトXみたいでした。転の部分のハラハラ感、それを乗り越えてのハッピーエンドは大体の予想通りとは言え、読んでて爽快でした。ちょっと展開が上手くいきすぎかな、という気もしますが、元気出たのでヨシ!やっぱり小説はこうでないと! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 何の観光資源もない宿場村。このままでは2030年には人口ゼロになってしまう。危機感を抱いた村の青年たち(ちと年がいってますが)は、ちょっとした思いつきで村おこしを図るが、当事者の知らない間に話はどんどん大きくなっていき…田舎に住んでると、この主人公たちの気持ちがよく分かります(笑)。観光資源がないとなればハコ物で観光客を呼ぶしかないですが、それも今では頭打ち。ではどうすればいいか…ともすれば暗くなりがちな話題を、徹底的にエンターテイメントに仕上げて読ませてしまうのはさすがですね。ひさしぶりに一気読みした本でした。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!