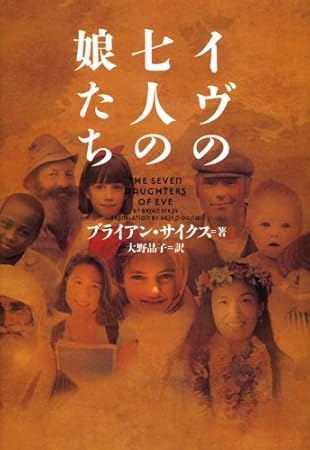■スポンサードリンク
イヴの七人の娘たち
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
イヴの七人の娘たちの評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.37pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全38件 1~20 1/2ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 内容は面白く、興味深いものですが、日本人のルーツには2行ほど。 DNA鑑定やその取材のドラマが単なる科学的なおはなしでなく ロマンを含んでいて読み物になっていて楽しめました。 が、再版もので、最新のおはなしかと勘違いして購入したので残念でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ミトコンドリアに興味を持ち、めぐり逢ったのがこの本です。 後半の「七人の娘」の考察に結び付くまでの研究が、大変興味深かった。 やはり派閥や、好き嫌いがあるんだなぁと。 後半のミトコンドリアDNAから推察される人類の拡散と、 そのころの人類の生活形態は想像力を大いに刺激し 小説のようで一気に読み進めることができました。 出版から年月が経ち、科学的根拠に変化がありかもしれませんが、 読み物としては楽しいものです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ウン十年の昔、大学の教養課程で人類学を取ったが その頃の人類学は頭骨の形(縦長、横長)や歯の形(shovel型かどうか)等々で人間のルーツを求めるーという様なモノで、アホだったとはいえ「こんなアナログ的なもの、測り方一つ、見方一つによってどうにでもなる方法で云々するのは無理があるなあ」と思ったものだった。 今は男のY染色体、女のミトコンドリアDNAの配列によって自分のルーツが「間違いなく」遡れる。本書はEuropaの人間を対象にしているが、彼らが7つの「遺伝学的な群=クラスター(母のイヴ)」に収斂されているーと結論付けるまでの研究成果が素人にも良く分かるように書かれている。 ただーと思うのは(本書の中にも書かれてあるが)、その7人のイヴ(本書ではEuropaの人間)にもたった一人のアフリカの「母=ミトコンドリアイヴ」が居る訳で、さらに遡ればーーと繰り返していくと終いにはバクテリアになってしまう。 そこまで考えるのはきっと馬鹿なのだろう。 わずか5万年前の出アフリカによって現生人類がいつどのようなルートで世界中に散らばったのか?が理論的には全て分かってしまうーという事実に驚く。 嗚呼、自分はアフリカから5万年でどのルートを辿ってこの日本に来ているのだろう? | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 遺伝子とかそういったことに興味を持つきっかけになりました。 私はロマノフ王室マニアなので、著者にその血が流れていることが気になって仕方がありません。 そこをもっと掘り下げて欲しい‼︎続編のアダム〜で自身のy染色体については調べられているのですから是非‼︎ | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 背表紙が日焼けしてましたが、内容はきれいでした。 読み終わる頃には表紙も日焼けしました。 全く問題ありません。 気持よく読むことができました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 変化しにくいミトコンドリアDNAとは何か、その変化を見ることで人間のルーツがわかる、ポリネシア人は南米からではなく台湾などアジアから海流に逆らってやってきた、コンティキ号のヘイエルダールの仮説は残念ながら間違っていたなど、眼からうろこの驚きの連続。 また文章も非常にユーモアに富んでおり一般人に分かりやすくできるだけ平易にかかれてはいるが内容はすごい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 多くのカスタマービュー の通り 「イブの卵」 と 合わせ読み が良い 読み物として 面白いと思う | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| もうずいぶん前に購入した本です。科学書なのですが文章が平易で読みやすく、特に、7人の娘たち一人一人の生活を描いたくだりでは物語の中にぐいぐいと引き込まれていきました。博物館、大学の資料室に眠る人骨にも、生きていた時のはそれぞれの人生のドラマがあったのだと著者は語りかけてくるようです。著者はイギリス人であり、本で語られる内容もヨーロッパ人の起源についてですが、本の最後のほうで、世界の人種、民族のミトコンドリアDNAの比較で分かった分岐ずも掲載されており、私たちアジア人の民族間のつながりにも思いをはせることができます。サハラ以北の人類は、約7万年前(諸説あります)に出アフリカを果たした約150人ほどの集団の子孫と言われます。ミトコンドリアイブという言葉は、この分野に興味のない方も聞いたことがあると思います。今となってはデータが古いかもしれませんが、初めに読む一冊としてはおすすめです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 私たちの生命のあり方や、ホモサピエンスとしての歴史が面白い。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ミトコンドリアDNAから系図が判明することはわかっていたが、アイスマンを想起させるような7人娘の生き様が想像できておもしろかったです。 この本を理解したら、近年の隣国との騒動は本当にあほらしいことですね(親戚間の争い・近親憎悪?) | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| なかなか楽しく読ませていただきました。 ただ、著者の想像する七人の娘(一族の母)達の生き様が現代人の思考回路を基に書かれているのにちょっと違和感がありました。 それから、第四の娘ヴェルダには姉がいるようなので、著者の言う一族の母になるための条件→「娘を二人以上産むこと」を満たしているのはヴェルダの母じゃないですか?翻訳の過程で間違ったのか原文からの間違いなのかはわかりませんが。 あと、DNAの構成要素でいきなり「Aはアデシン」だなんてちょっとびっくり。 Adenineです。 とはいえ、訳者さんの翻訳はとてもお上手だと思います。 大変読みやすかったです。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 「アダム~」と一緒に読むことを、お勧めします 人類とDNAと、太古の時間と・・・ 感じることが、この本の趣旨だと思います | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 難しい事柄をわかりやすく解説し、ウィットとユーモアに富んでいて、読みやすい。 データがやや古いので、「?」となる部分はありますが、良い本です。 こういう本は「俺すごい」が鼻につくことがありますが、そういったこともありません。 福岡伸一著「生物と無生物のあいだ」を先に読んでいたので、”一番に発表した者だけが勝者””研究の前提としている説が覆されるのではないかという怖れ”などの研究者心理に臨場感があって楽しめました。 PCRという高価な機械を購入できず、鍋ややかんやコンロを駆使して同様の機能を持つ装置を自作してしまったくだりは、PCR開発者のマリス博士のことを知っていると爆笑。 アメリカの研究室に比べると、オックスフォードは平和な印象を受けます。 「七人の娘たち」それぞれに物語が付されているのは過剰な気がしますが、ヒーローを求めたがる文化の中では、これが必要だったのかもしれません。 人類の分岐は、必要に迫られたり衝動に突き動かされたりした名もなき一人によって成されたもので、王や英雄が成したものではない、と。 ミトコンドリアの遺伝子を通して見れば、人種も文化も国籍も身分も貧富も関係なく、世界中の人間はつながっている。 母系で考えたなら、つながっているのは父ではなく、言葉の通じない、姿もまったく違う、遠い遠い場所に住んでいる人かもしれない。 壮大すぎてピンとこないところもありますが、読むと少しものの見方が変わる(変わりそうな)本です。 母系を採用すると、嫁姑問題が激減して男性も平穏になるんじゃないかという気はします。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読後感が良い。 アダムの呪いは男性性の自然的本質を批判している。本書は、女性性の性質には何も言及していない。 MT DNAの行方を科学的手法を持って追うだけにとどまっている。 何千年も前の生活を予測している。 万人向けにするためか、ごく簡素に書いてある。中学生から読める。 あたかも古代の人間の方が、文化的性差がなかったような錯覚に陥る。 となれば、身体的な差異はあっても文化的に協調性があった フェミニズムは、文化的・生理的な性差があるのではないかと常に考え続ける姿勢のことだ。 時代によって文化的性別は変化する。搾取がないか、人間社会を長持ちさせるために 男女間の違いは、本当にあるのだろうか。 女性が受け身の性別という概念があるが、遺伝的性質とは関係がない。エストロゲンは外見の変化・生理的機能こそもたらすが、パーソナリティとは関係がない。 幼児期、児童期、思春期、青年期。 知能の発達や言語獲得、社会化は、性別問わず人間が成長する過程の必修科目だと思う。 女性の敵が女性である原因が性にあるとすれば、アフロディテが居るからだ。自分の才覚ではなく、生理的性別に頼ってしまうと、文化的に女性が搾取される風潮が生まれる。 女性も家庭を支えなければならないが、社会的側面、才覚があってこそ、健全な家庭や地域社会ができる。 しかし、人間社会のあらゆるハラスメントの原因は複雑なので性別以外の原因がほとんどだと思う。 性別だけでなく、あらゆる偏りは不健全な社会を生む。不健全な社会では、生きる意味などない。 人間らしさは、絶え間ない努力をしなければ「保てない。」人間がもつネガティブな要素は強い。 ハラスメントは社会病理だ。単なる自己愛をドメスティックに搾取し、搾取されしているだけだ。建設的な人間関係のバリアーすなわち障害になるものだ。 これは社会的とは言えない。 議論とは「相手の意見を変えるものではない。」それは不可能だ。「その場に2つ以上の意見を集める」ものだ。 他者との対話とは、違う意見を発見することだ。 サイクス氏は素晴らしい。 遺伝学は、いわゆる「大衆の理性が眠ると怪物が目を覚ます」原因に 知性の光を灯す 試みでもある。 私は、学問がなくなってしまった世の中には住めない。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 現在の人類は20万年前以降にアフリカに存在した1人の女性を起源としているという「イブ仮説」は1987年発表され、翌年のニューズウィークの特集記事で広く知られるようになった。この説は曲折を経て基本的に正しいことが現在では立証されている。本書は、同じくミトコンドリアDNAの突然変異を通じて、主にヨーロッパの人たちの起源を探るものだが、5千年前や1万2千年前の骨や歯からDNAを抽出するなど分子遺伝学研究の第一人者の立場から実際の研究成果が実証的に解説されている。また、ポリネシアの人たちはアメリカから渡ってきたとする「コンチキ号」で有名な説を明確に否定する研究も解説されている。 表題の「7人の娘たち」というのはヨーロッパの人たちの95%は7つの母系グループに属するという研究成果を表わすもので、著者は、更に想像をめぐらせて、7人の母親に名前をつけて、それぞれの生活環境や暮らしについて語っている。このような物語化には抵抗を感じる読者もあると思われるが、「人類」や「人種」といった見方で人を分類するのではなく、各個人の遺伝子には、何千世代に及ぶ何百万の生命によって届けられたメッセージが込められているという著者の心情を示すものである。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ずいぶん前に話題になった本だった。 この本以降にミトコンドリアに関する本が急に増えたのを覚えている。 文庫本を見かけたので手に取った次第。 アカデミックな部分と考古学的考察、そしてフィクションがうまく配合された読み物というのが読後感。 若干古くなった部分もあるが、十分にミトコンドリアDNAについての理解が得られる秀作です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較的専門的な内容にも関わらず、分子生物学・進化学的な事項をわかり易く記述していると思う。 7人のイヴが発見されるプロセスが詳細に記述されているし、研究の日常的場面の臨場感が活き活きと描かれている印象をうける。 この本を読むと、人種という区別は如何に意味がないものであるかを改めて考えさせられる。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 法律関係なので、ミトコンドリアDNA鑑定を理解するために読みました。 しかしミトコンドリアDNAから読み解けるのは、「個人識別」どころでなく、壮大な人類の歴史であり、これは本当に驚きでした。 終章は「七人の娘」の姿を想像で描きます。 余り科学者らしくないと思いつつも、彼女らの短く苦難に満ちた人生に思わず笑いと共感を覚えます。 突然変異型から先祖を探り出す推論過程は、十分に蓋然性が高いと思いました。 とりわけ、ポリネシア人の物語が面白く感じられました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 遺伝子の話なので理解するのに難しい個所もあるが、第10章あたりから俄然面白くなってくる。現代欧米人の先祖は採集狩猟民の末裔なのか、それとも近東からの農民なのか・・・。 このような具体的なテーマを解明していくための過程がつづられていく。 過去の事は現代からの目で見てこれがその時代の姿である、と言い切れない。そこに実際いたわけでなないので、残されている物からの推測でしかないのだけれど、新しい発見や技術の進歩でいままで言われていたこととは、別の世界が開けることもある。 DNAやミトコンドリアDNAなどもそこに貢献している。今回の7人の母にたどり着くことができたのもDNA採取ができるようになったおかげだし、1万年も前の人の歯の化石からDNAが取れた、と言うのは確かにそこで私たちと同じ人が生きていたと言うこと。一気に時間が縮まる思いだ。 昔3大文明についての話を授業で聞いたけれどあまりピンと来るものがなかった。ところが自分の持っているDNAをだどって行く方法で過去にさかのぼると、そこにも私と変わらない毎日の生活があり、文明にしても急に起こったのではなく、自然の流れの中での選択の結果であったという当たり前の事がすんなり入ってくるし、頭に残る。歴史の勉強もこういうアプローチの仕方があるんだなと思う。 母系名をミドルネームに持つ、と言うアイディアは面白い。全く見ず知らずの人が実は遠い親戚だとわかると親近感を覚えるだろうな。現実にはならないだろうけれど。今住んでいる場所ではない、全く行ったことのない所に自分のスタートがあると考えると楽しい。そんな気分にしてくれる内容だ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この本には、オックスフォード大学で遺伝学の教授を務める著者が、人生と名誉をかけて研究してきた“ミトコンドリアDNA”についての驚くべき発見が世に広まり、反論を掲げていた他の学者達からも認められるに至った経緯と理論が熱く、解り易く書かれています。 DNA核内にある膨大な量の配列を解読し、個人個人の比較データを取るという事は気の遠くなる作業となります。 しかし著者ブライアン・サイクス氏は、母からのみ遺伝されるという“ミトコンドリアDNA”の小規模で組み換えが行われないという特性を持つ配列を解読することにより、人間(ホモ・サピエンス)のルーツがどこで生まれてどう世界に移動していったのかという疑問に対して、遺伝子学の見地から解答の糸口を掴みます。 これまでに発見された人骨化石やミイラなどから採取されたミトコンドリアDNAと現代人のそれとは、ほぼ変わらない配列を持っていたからです。 更には、母方の祖先を辿っていくとピラミッド型に直属の先祖を絞っていくことができ、6億5000万人にものぼるヨーロッパ系人種の母系先祖は七人の女性に帰属するという発表に至りました。 この七人の女性達は同年代に生きていたのではなく、ネアンデルタール人と呼ばれる集団であった4万5千年前に生きた一人から、クロマニョン人時代に突入していた6千年前に生きた一人まで年代には差があります。 もちろんその時代の女性が彼女達だけだったわけではなく、他にも女性はたくさんいたのですが、七人の彼女達だけが先祖で有り得る条件としては、彼女達が二人以上の女児を生んでいたこと、そして各々の女児達が成長して子孫を残し、その子孫がさらに子孫を残し続けている結果なのだとしています。 個人的にはブライアン氏の飽くなき探究心と論理の立て方にとても惹き込まれ勉強にもなりました。 また、科学者達が学会や名誉ある研究誌などで定説を覆し、新論を掲げることの達成感や度を越えたストレスがよく伝わる本でもありました。 全くその分野には素人な私にも解るように書かれていて、とても好奇心が満たされました。 日本人のルーツと母系先祖についても記載されています。 この本の後半には七人の女性達の生活模様が、当時の地理的状況や気候、食料としていたであろう動植物などが加味されて描かれており、遠すぎる過去に確かに生きていた彼女達を、より身近な存在として想像できました。 これまでの遺伝子学的な論調から一転し(読者の気分の柔軟性が求められますが)、動物との命を懸けた駆引きを前にした緊張感や、大自然の中を通り抜ける風を感じるようでした。 読み応えのある一冊です。単行本で出版されたので更にお薦めです。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!