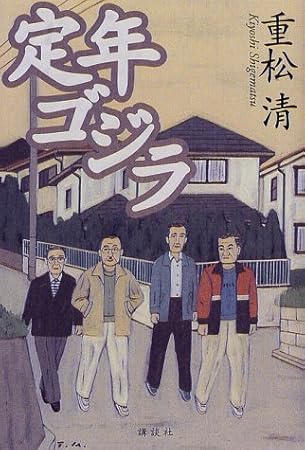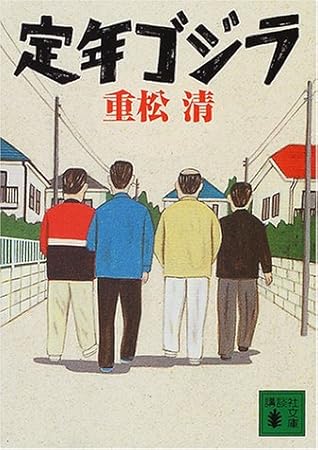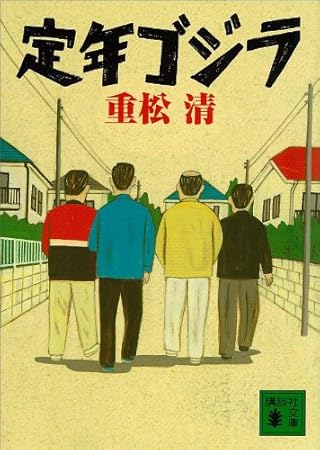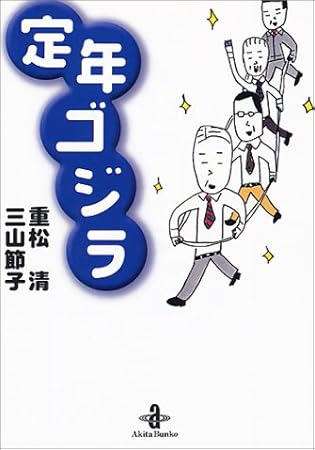■スポンサードリンク
定年ゴジラ
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
定年ゴジラの評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.07pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全52件 41~52 3/3ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| これは定年したお父さんたちに焦点をあて、彼らの気持ちやプライド、 生き甲斐などを深く(でも決して深刻ぶらずに)掘り下げた作品だ。 現実同様、物語の中で起きることもいいことばかりではなく、時に暗く、重いエピソードもある。まして重松さんの作品では、登場人物はたいてい不器用だ。 この作品でも例外ではなく、読んでいて暗澹とした思いになることもゼロではない。ただ、だからこそ、いつも思い悩み、傷つき、時には情けなくも目の前の現実から逃げ出したりもしながら、懸命に生きている人たちを、応援したくなるのだ。 自分も、この本を読んで、そういえば郷里で暮らす父親は元気にしてるかな、とあらためて親孝行したくなりました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ニュータウンに住む定年後のおじ様たちが主人公。就職、結婚、子育て、マイホーム購入、振り返ることもなく走り続けてきた男たちは、肩書きを持たない生活に入ったとき、何を考え、どう行動するのか? 重松氏の文章は本当にうまい!若かりしころ、上京した母につれなく当たってしまったことを定年後思い返すくだり、離婚協定中の娘の彼に「あの子にも家庭を作ってやってくれ」と頭を下げるくだりなど、涙がこぼれました。 人生100歳まで!まだまだ幸せが待ってますよ!とエールを送りたくなる作品でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 重松さんの作品はいくつか読んでますが、本作品は一押しです。私は重松さんと同世代ですが、定年を迎えた人達をこれだけリアルに描けるのは見事な観察力と想像力だと思います。 私も40歳を過ぎたサラリーマンとして会社での責任や生きる事の大変さを感じている今日、定年まで勤め上げることがどれだけ価値あることか、大変なことかを痛感しています。これまで頑張って日本を支えてきたお父さん達なのに、今の日本では定年後の人生のイメージは必ずしも明るいものではありません。この物語の中でも孫娘から、おじいちゃんの仕事は「ぶらぶらしてるの」と言われたり、奥さんの後を付いて回る「濡れ落ち葉」と称されたり。そんな中で、生き方を模索する山崎さんたち定年族を、応援したくなるお話です。 個人的には、第四章の「夢はいまもめぐりて」が大好きです。山崎さんの同級生のチュウさんの「負けた奴やがんばれなかった奴を許してくれる人がいねえから、勝った奴と頑張っている奴しか住めねえ街になっちまうんだ。」という言葉が印象的でした。なんとなく今の日本そのものを表しているように感じました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 郊外にある年老いたニュータウンで定年後の居場所を探している男たちの生活を描いた作品です。ここに、登場する人々は特別な人ではありません。片道2時間の通勤電車を味わってきた人、単身赴任を続けてきた人、熟年離婚をした人、2世帯住宅の人など、身近にいそうな人達です。 終身雇用の崩壊した現代社会で働いている私としては、自分の老後を本書の登場人物に置き換えることはできませんが、涙あり、笑いありの物語は、心に響く重いものを感じました。日頃、見落としている大切なものを発見できます。家族、友人、コミュニティー、故郷、夢、人生について大切なことを教えてくれます。 私と同じ世代の著者が、世代の違う先輩方の気持ちを、ここまで繊細に描写できることに感服しました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 重松さんの小説はどれも一般的な家庭を描いたものが多く、時には寂しく厳しく 感じられる結末のものも多くあります。ただこの定年ゴジラは定年後、新宿から 電車で片道2時間かかるニュータウンに住んでいる山崎さんが主人公です。 電車で2時間以上、往復4時間以上かかる生活は東京など大都市の近郊に住んでいる 方からするとそれほど特異なものではないかもしれませんが、私にはそういう経験が なく、大変だろうな・・・というか想像以上のものがあります。 また定年後の老夫婦と、同じニュータウンに住んでいる人たちの話が中心で、 現在の自分からはまだ何十年も先の話・・・身近に感じるのが難しいくらいなのですが、 彼らの日々の生活を頭の中に鮮明に描くことができたのは、重松さんの文章表現の 巧みさのおかげではないかと思います。 言葉が固くなく、また広島、岡山、福岡など様々な地方の言葉を操る野村さんの 存在があり、様々な世代の人たちがそれぞれの世代に合った言葉を使っていることが、 作品が読者の生活に近いものとなっているのではないでしょうか。 ところどころに「あぁそうだなぁ」と共感してしまうところや、くすっと笑ってしまうところ、 また涙ぐんでしまうところがあり非常に楽しい作品です。 肩を張らずにねっころがって読むくらいがちょうど良いかもしれません。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 重松清の人を観察する目とそれを描写する力には唸ってしまう。 定年後のオジサンの話だし、それほど期待して読まなかったのだけれど、 最初は笑え、途中何度か泣き、最後はすがすがしく読了。 読後、街を歩くオジサンを見ると、この人もゴジラかな?と想像してしまうのでした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 働いている人なら誰でも迎える定年。決して他人事ではありません。ある時は父の世代の人たちを思いながら、ある時は自分たちの未来の姿を思いながら読みました。 定年を迎えたとき、自分の生きがいを見失ってしまう人がたくさんいます。「粗大ごみ」「濡れ落ち葉」「わしも族」などなど、定年後の男性をさす言葉は、残酷なまでにひどいものです。定年は人生の一つの通過点です。決してそこで終わりではありません。その後も人生という道はずっと先まで続いているのです。 くぬぎ台ニュータウンで繰り広げられる人間ドラマは、私にほのぼのとした温もりを与えてくれました。作者の温かい思いも伝わってきます。心に残る1冊です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 主人公の山崎さんは元銀行員。娘二人は独立し、奥さんと二人暮し。山崎さんが住むのは新宿から急行電車で2時間かかるところにある開発後30年たつニュータウン。題名のとおり、定年を迎えた元サラリーマンたちの物語。とはいっても心機一転第二の人生をやりなおそうとか、力をあわせて新たに何かをしよう(例えばロケットを飛ばす・・・)といった物語では全然ない。運動不足解消を口実に無聊を慰めるために始めた散歩の仲間とその周辺で起こる日常的な出来事を扱う。定年離婚、2世帯住宅、墓、故郷、単身赴任、濡れ落ち葉亭主・・・。次女の結婚によるひとつの家庭の崩壊から自分の家族の歴史を思い、因縁の幼馴染の訪問から故郷を思う。 可笑しくてどこかしら哀しいストーリーがつづられていく。一貫しているのは、著者が彼らを見つめる視線が常に暖かいこと。中流のサラリーマンが一生懸命働いて、家族を養い、老いていく・・・多くの普通の人たちが通っていくだろう人生を描いている。それだけに作品中の登場人物たちにどこか重ね合わせられるところを見つけ、他人事ではないと思ってしまう。普通の人を描くことにかけて重松清は本当、うまい作家だとおもう。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| オヤジ小説と思って、引いて読んでいると、急に心のピントがあって、鼻の奥に熱いものがせりあがってくる。 主人公に不意に自分の父親の姿がダブリ、どうしようもなく泣きたい気分になる。僕は、まだ三十歳にもならない小僧だけれど、それでも親の世代が見た夢や傷みがもう理解できてしまう年代になったのだなと思うと、うれしいような、でも寂しいような気になる。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この本は父に勧められて読みました。古くなったニュータウンといっしょに、定年を迎えたおじさんを中心とするホームドラマのようでした。社会学者などはニュータウンというのは当時の理想を描いたものだが、人間の高齢化を全く考慮していなかったと評価しています。しかし、そんなニュータウンの中でも、仲間を思いやり、あるいは新しいことにチャレンジしたり、様々な人たちがいて、その日常は、一言でばっさり評価できるものではないのだな、という感想を持ちました。定年後、妻に離婚された隣人、妻子ある男性と婚約した娘、など、そのへんにいそうで、なかなか辛い現実を向き合う登場人物がたくさん出てきますが、それらの人を温かく見守る作者の視線を感じました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この作品の第2章に「ふうまん」という挿話がある。全国物産めぐりが趣味の野村さんが大切な家族との絆を確かめるために買う「今川焼き」である。このふうまんを重松清は岡山の名物として取り上げてくれた。それが嬉しい。もっとも私はこれを「フーまん」と呼んでいた。(いい方が微妙に違えば、想い出も微妙に変わる)今は亡き母親が倉敷の街に買い物に行く度に「みやげ」として買ってきてくれた思い出である。バスに乗る直前に買い、懐に包んで帰ったためか、家に着いた頃でもいつも暖かいままだった。どうしてあんなにおいしかったのか、今では信じられないほどだ。私が遅く家に帰ったときにはコタツの中から出てきたこともあった。思えば小さい頃、家族はそれほどに暖かく甘かったのである。岡山出身の重松清、自分の経験も踏まえながら、家族の絆を上手く描きだしている。「大手まんじゅう」の美味しさにも言及しているところも、にやっとする。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 定年を迎えた「おじいちゃん」にはまだなりきれない「おじさん」のお話。退職して第二の人生をどうやって生きるのか。答えは簡単には出ないかもしれない。でも、ぜひこの本を読んでみて欲しい。ほのぼのとした前向きなメッセージがこめられているから。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!