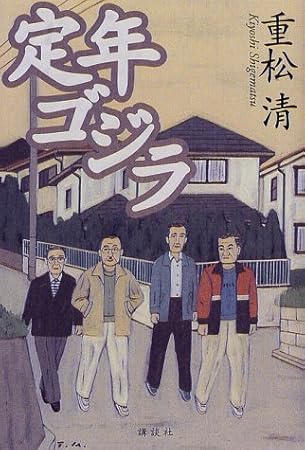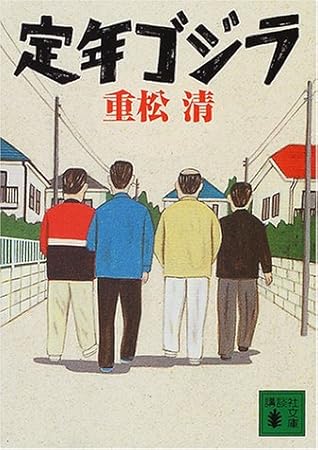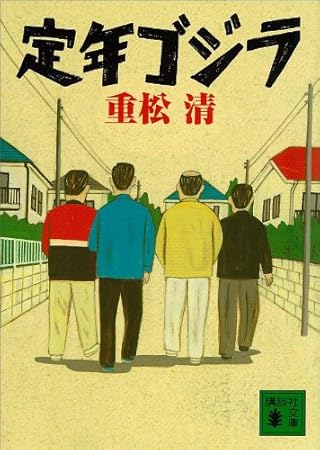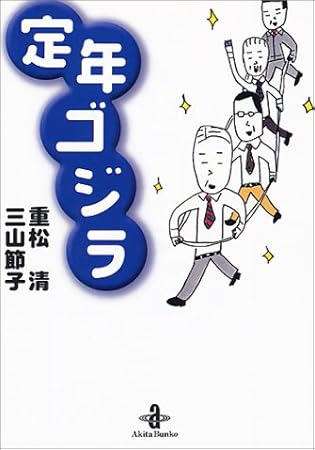■スポンサードリンク
定年ゴジラ
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
定年ゴジラの評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.07pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全69件 41~60 3/4ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| あー。考えちゃったな。定年後の自分どうなんだろうか。再雇用で5年延びるけれど、役職を外れて終わりを待つ今を思い返されています。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 同年代の物語として共感出来る。重松作品恐らくこれが3冊目。これからもっとよみたい。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 私も同じ年代のものです。同じ目線で読むことができました。 淡々とゆったり読むことができる作品だと思います。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 大手銀行を勤め上げ定年退職して、今までは仕事の基地としか見てこなかった山崎さんの目からみた「わが町」と「われら仲間」のペーソスに富んだ小説です。 章立てが独立しており、しかもつながりがあって、個性豊かな3人のキャラと合わせて十分に楽しめました。 あとがきを見ると、この小説の書かれたおよそ15年前は、このように無事に定年まで同じ会社で勤め上げた人が多かったことに大きな衝撃を受けました。自分の少し年上の世代を考えるに、リストラがあり、子供の難事があり、このように引退後は悠々と町内を散歩という方をおよそ見かけないからです。その意味で、この小説をあたかもファンタジーのように受け取けとりました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| これから、定年を迎える私には、未来予想図的な小説で、興味深く読むことが出来ました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 男はこんなもんだ 俺も真っ只中 せつないな なんで?11文字に解らん | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この小説は読む人を引っ張り込む。この本は、起こりえないような絵空事ではなくて、実際の生活に息吹いている部分を感じさせる。登場人物がそれぞれの「勝ち負け」や「良し悪し」の価値観を持ち、それが時を経て死に向かってゆく人生のあり方を考えさせる。例えばのんびりしてそうで、写真を破りさく激しさを持った「奥さん」。もしくは、ひとつの生き方としての「チュウ」。黒澤明の「生きる」に通じる部分があるのでは無いだろうか。 好きな小説だ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 6章「くぬぎ台ツアー」が気に入らなかった。 なんで野村さんは、学生を殴ったあと謝らなかったのだろう? なんで山崎さんは、殴られた学生に対して、「君もいずれわかるようになる」などと説教めいたことを言えたのだろう? なんというか、読んでいてむかついた。これが定年を迎えた老人のとる態度かと思った。 自分はまだ20代なので、ここのレビューにあるようには共感できなかった。 年を取ると共感できるようになってしまうのだろうか。 6章以外の全体的な流れとしては、寂しさと哀愁漂う老人たちの日常が描かれている。 「濡れ落ち葉」という言葉を始めて目にしたが、うまい言葉だ。こう言われる老人にはなりたくないものだと思った。 登場した老人の中では、くぬぎ台を飛び立って新天地で新たな生活に挑戦するフーさんに一番共感できた。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 主人公は定年を迎えた山崎さん。(下の名前も後半になってようやく出てきます) 相変わらず、重松さんの文体は読みやすくて、どんどん読み進められました。 同じ定年仲間・先輩の死、旅立ち。 長年連れ添った奥さんとの雰囲気も良く出ています。 山崎さんはある日、奥さんの枝豆にケチをつけ、会社員時代に行っていた店の前まで行きますが、その時、店の中から聞こえた笑い声と、「課長」の声に、店に入るのをためらいます。 でも、あと数年経ったら、会社員のOBとして、定年の先輩として店に入れるだろう、そう思うところの描写も上手いと思いました。 2年後の定年ゴジラも収録されていて、たった2年なのに大きく変わっていることに、驚きながらも、「そうだよなあ」と思い、楽しく読めました。 定年を迎えたおじさん達には、「まさにそうなんだよ!」と思えるのではないでしょうか。 重松さんは、当然ながらまだ60才ではありませんが、まだ体験してないことを自然と書けるのは凄い。 私の家は会社勤めをしている人がいないので、会社に勤めていることの大変さや、通勤の辛さも知ることができて良かったです。 旦那さんを批判・避難してる奥さん(はこの本、読まないんだろうな…)や父親を嫌ってる娘世代が読んだら、優しくしてあげよう、と温かく、優しい気持ちになれる気がしました。 ニュータウンと呼ばれた街の現状や、娘とは別居、夫婦二人暮らしで、「もし介護されることになったら」を考える山崎さんと奥さんのことも、時には鋭く描かれていて、日本の課題も見えてきます。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 自分自身の未来と 両親の現在を重ね合わせてしまいました。 2001年、 今から8年前に出版された文庫ですが、 ここまで現状と合致していると空恐ろしいものがあります。 一戸建てにかぎらず、 ニュータウンと、その昔もてはやされた物件は、 今では定年をしたものだらけになり、街の衰退はもとより、 “孤独死”なんていう切ない響きが、ニュースの題材で取り上げられたりする。 同作では 定年後のサラリーマンの悲哀が描かれている。 当時は悲劇の極地にあったかもしれないお話が、 むしろ幸せに思えるような時代が来るとは、このときに誰が想像できただろうか。 フィクションでありながら、 定年を迎えたばかりのご夫婦にも目から鱗のはず。 特にお父さん(親父)、 優しさ・気遣いの方向、間違えちゃダメだよ。 お母さん(お袋)の気分、余計に害するだけだからさ。 自分が定年を迎えたとき、 もう一度、読んでみたい書物です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 読了直後に、ウルフルズの「泣けてくる」を聴きたい感じでした。 今から数年前、40を前にして何だか人生折り返しだなぁと思い始めた頃に読みました。 一生懸命働いてきた後の、何となく充実感のない日々。 定年退職した父親の心境なぞ、考えた事もありませんでしたが こんなことなんだろうなぁと思いました。 それと同時に、俺もこういう感じになるのかなぁという気持ちでした。 泣けたシーンをいちいち全部書きたいですが、それはネタバレになりますので 読んでのお楽しみということで。 オススメ作品の多い重松さんの本ですが、その中でもこれはイチオシ!です。 30代後半以上の「オジさん」、是非ご一読を!! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 家庭も顧みず仕事一筋に生きてきたオヤジたちが、定年を迎え、さてどう生きるか。 これまでの人生、今現在、これから・・・。 全体を通して、コミカルな味に彩られているが、登場人物それぞれにさまざまな、 けれどおそらく多くの人が共感できる思いを抱えて生きる。 主役のオヤジたちはみんな魅力的で、彼らの人生の深みや、積み重ねてきた時間ゆえの 悲哀がところどころで胸に迫る。 ・・・・泣いた。 特別にドラマチックでなくても、順風満帆でなくても、(そうでないからこそ、か) 真摯に生きていくことが素晴らしいと思える。 いつまでも心に引っかかる苦い思い出があっても、それを抱えて生きていくしかないし、 あるいはそういうことがあるから頑張れるのかも、と自分の父親の人生に思いを馳せ、 父親になった自分のこれからを考えた。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 何気なく海外出張に行く時に空港で買った本ですが、面白かったです。自分はまだ30半ばで、定年後はほとんど想像した事すらなかったですが、なぜか非常に感情移入出来ました。後、読んだ方には分ると思いますが、嫁さんは大事にしようと(笑)。思わず出張先で妻にみやげを買ってしまい不思議がられました。いずれにせよサラリーマンの方なら読んで絶対損しないと思いますよ! | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 定年後の男が,年老いたニュータウンで過ごす余生。重いテーマを軽くさばいて,気楽に読める作品に仕上がっているのだが……。 『家族写真』にはやられた。昔子供を遊園地に連れて行ったことがある中年男性の方が本書を読むときは,気をつけていただきたい。私の場合,本書を気楽に喫茶店で読んでいて,思わずボロボロと涙を流して泣いてしまった。 《メリーゴーランドが,さっきの家族連れを乗せて回りはじめる。カボチャの馬車に,母親と赤ん坊。男の子は馬車を牽く白馬に一人でまたがって,柵の外でビデオカメラをかまえる父親に手を振っていた。 幸せそのものの家族の姿だ。けれど,今日の遊園地を最後に,あの夫婦は離婚してしまうのかもしれない。家族の歴史が閉じる前にせめてもの楽しい思い出を子供に残してやっているのかもしれない。今朝,出掛けに夫婦喧嘩をしていたのかもしれないし,遊び尽くして帰宅してから,ささいなことで夫婦喧嘩が始まるのかもしれない。 誰にもわからない。 確かなことは,ここにいま幸せいっぱいの家族がいる,それだけだった。》(361頁) 田舎から出てきた母親が,お土産を買うために虎屋に行きたいと言う『夢はいまもめぐりて』も泣かせる話だった。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 重松さんは35歳頃に「定年ゴジラ」を書いている。 会社員の定年退職後の生活を実にうまく書いているが、何かわびしさを感じる。 定年離婚の話、二世帯住宅の嫁と姑のもめ事の話、娘の交際相手が家族持ちの 話、かわいい孫からおじいちゃんの仕事は「ぶらぶらしている」といわれ ショックを受ける話などなど、わびしくなる。 しかし、今の言葉で言うと「くぬぎ台」で生活している人たちは、人生での 勝ち組の人たちである。 主人公の山崎隆幸さんの中学時代の同級生の岸本忠義さんが、突然訪ねてくる。 岸本は仕事を転々としている人生の負け犬である。 その岸本が感じるニュータウン「くぬぎ台」のイメージは、人生に勝った人間 だけがここに住める場所で、途中で負けた奴は出ていかなければならない。 ここはいい街だけどつらい街であると素直に感想を述べる。 この言葉を読んだとき、厳しい現実を感じた。 人は、自分の生きている場所で、前向きに努力しながら、死んでいくしか できないのであろうと思う。 趣味や自分の楽しみのために悠々自適の第二の人生を過ごせる人は、ほんの 一握りの人たちだけであろう。 定年退職によって、それまで仕事に追われ、時間に追われ続け、ただ時間だけ がむなしく過ぎ去る生活からは解放される。 まずは、それだけでも十分幸せであると感謝しなければならないと改めて 感じたのが、この本を読んだ私の素直な感想である。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| この本と出会っていたら、たくさん普通の親孝行ができたかもしれない。そんなふうに思わせてくれる優しい小説です。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 重い話もあるし、自分の心のざらざらした部分をさらに刺激するような話もある。 でも、作品全体から発せられるあたたかさがちょうど肩の凝りをほぐしてくれるようで なんとも心地いい。 作者の人間性が伺える作品と思います。 重松清、いまさらですが要チェックですね。 昔ドラマ化されたそうですが、ぜひ見たかったなぁ。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| これは定年したお父さんたちに焦点をあて、彼らの気持ちやプライド、 生き甲斐などを深く(でも決して深刻ぶらずに)掘り下げた作品だ。 現実同様、物語の中で起きることもいいことばかりではなく、時に暗く、重いエピソードもある。まして重松さんの作品では、登場人物はたいてい不器用だ。 この作品でも例外ではなく、読んでいて暗澹とした思いになることもゼロではない。ただ、だからこそ、いつも思い悩み、傷つき、時には情けなくも目の前の現実から逃げ出したりもしながら、懸命に生きている人たちを、応援したくなるのだ。 自分も、この本を読んで、そういえば郷里で暮らす父親は元気にしてるかな、とあらためて親孝行したくなりました。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ニュータウンに住む定年後のおじ様たちが主人公。就職、結婚、子育て、マイホーム購入、振り返ることもなく走り続けてきた男たちは、肩書きを持たない生活に入ったとき、何を考え、どう行動するのか? 重松氏の文章は本当にうまい!若かりしころ、上京した母につれなく当たってしまったことを定年後思い返すくだり、離婚協定中の娘の彼に「あの子にも家庭を作ってやってくれ」と頭を下げるくだりなど、涙がこぼれました。 人生100歳まで!まだまだ幸せが待ってますよ!とエールを送りたくなる作品でした。 | ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 重松さんの作品はいくつか読んでますが、本作品は一押しです。私は重松さんと同世代ですが、定年を迎えた人達をこれだけリアルに描けるのは見事な観察力と想像力だと思います。 私も40歳を過ぎたサラリーマンとして会社での責任や生きる事の大変さを感じている今日、定年まで勤め上げることがどれだけ価値あることか、大変なことかを痛感しています。これまで頑張って日本を支えてきたお父さん達なのに、今の日本では定年後の人生のイメージは必ずしも明るいものではありません。この物語の中でも孫娘から、おじいちゃんの仕事は「ぶらぶらしてるの」と言われたり、奥さんの後を付いて回る「濡れ落ち葉」と称されたり。そんな中で、生き方を模索する山崎さんたち定年族を、応援したくなるお話です。 個人的には、第四章の「夢はいまもめぐりて」が大好きです。山崎さんの同級生のチュウさんの「負けた奴やがんばれなかった奴を許してくれる人がいねえから、勝った奴と頑張っている奴しか住めねえ街になっちまうんだ。」という言葉が印象的でした。なんとなく今の日本そのものを表しているように感じました。 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!