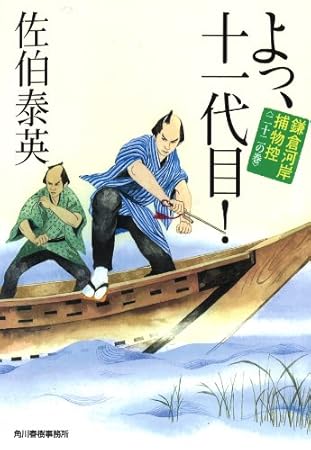■スポンサードリンク
よっ、十一代目!
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!
よっ、十一代目!の評価:
| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.12pt | ||||||||
■スポンサードリンク
Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です
※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。
未読の方はご注意ください
全1件 1~1 1/1ページ
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 鎌倉河岸捕物控』シリーズ(21)『春の椿事』から続く、 いくら、主な読者層が中高生くらいの低年齢の皆さんたちだからって、読者ってのを小馬鹿にしているんじゃないかい、こちらの作家先生。 この稿は、『鎌倉河岸捕物控』シリーズの時代考証上での失敗を指摘するのが狙いなので、原則的としてストーリーの出来、不出来には触れなかったが、それにしても本書のプロットって、お粗末もお粗末、酷いもんだねぇ、「子供騙し」にもなってやしないじゃないか。このシリーズの「時代考証軽視」という病気が、いよいよ身体の奥深くに食い込んで、そう遠くない時期まで死期が迫って来たとでも解釈しておくか。 シリーズ22作めの本書のうち、第4話ぶんはホームドラマなんで指摘を省くが、この第2話から3話に掛けての恐喝・営利誘拐事件っての、なんで悪ものたちが、お産婆さんを殺さなければならなかったのか、ぜんぜん話の辻褄が合ってなくて、まるで理解不能なのよ。 品川宿で、もと女郎をしていたという女性が生んだ男の子を、日本橋本町の老舗薬種問屋「いわし屋(『江戸名所図会』にある)」のご主人に、確かに実子であると認めさせたいのなら、死産したんでもなければ、他人の子供と入れ替わっているんでもない事実を立証するのに、出産に立ち会ったという産婆の証言は絶好の証拠となるはず。加えて、男の子だって相応な年頃になれば、どこかしら父親に面ざしが似てくるもの。ご主人の若いころを見知っている番頭さんと対面させたら、この20歳前という男の父親が「いわし屋」のご主人かどうかなんて一発で解るはずだし、この小説中でも、宗五郎親分や政次若親分が、この若者の姿かたちが、「ご主人にそっくり」だという印象を持ったとしているのに。 つまり、ご主人の実子というストーリー設定なんでしょ、この若者。 どうして、その実の子を、赤の他人の子供であるかのように捻じ曲げ犯罪者にしてしまうという、こんな馬鹿げた筋書きにしてしまったのか? おそらく、こちらの作家先生が、いまの民法・家族法と異なっていた江戸時代の家族制度というものをご存知ないんで、現代日本の民法上の決まりを、そのまんま江戸時代に敷衍して、このような恐喝事件を拵えたってチョンボから来てんだろうと思うな。 相続や遺産分轄にあたって、実子なら、被相続人の財産のうちから、「遺留分」というのを分けてもらえる権利があるという制度は、フランスの「ナポレオン民法」に倣った明治時代の民法典から始まるルールであり、この『鎌倉河岸捕物控』の舞台となった江戸時代に、そんな決まりはなく、一家の主人の「家父長権」が絶対ってもんだったのよ。 だれに、どれだけ家の財産を分けようと、だれを後継者に決めて家督を譲ろうと、嫡子、庶子、養子、娘婿、孫、兄弟、甥その他の遠縁、奉公人(使用人)を問わず、すべて、その家のご当主様の一存で決められることになっていたのが江戸時代。 お武家の場合だと、婚姻と同じく、ご主君のお許しが要るため、そうそう廃嫡は簡単ではないが、百姓・町人の相続や財産分けに、お上のお許しなんてのは必要なく、こちらの男の子が、「実子だから」、「年長者だから」という理由で、なにがしかのお金を強請り取ろうとしても、家産の分け前を要求しても、また、お奉行所に「おおそれながら」と訴え出ても、門前払いを喰らうばかり、てんで相手にされなかったのがこの時代のルール。 時代小説の中なんかでも、歴史上の事実においても、若い側室や後妻に鼻毛を抜かれたお殿様や大店のご主人が、惣領息子をさしおいて側室や後妻の産んだ幼い子供を後継者に据えようかと迷ったため、息子たちや取巻き連中が二派に分かれて争うといった構図の「御家騒動」って、幾らでもゴロゴロ転がってるじゃないか。 こういう事件が起こるってのも、すべてが、ご当主の考え一つで決まっちゃうって仕組みだったんで争いになっちゃうってわけだね。 したがって、このストーリーの場合だと、この女性が産んだ子供を実子と認めさせることが出来ても、最初から「いわし屋」のご主人には、この息子に財産を分けてあげたり、家督に据えようという気持ちがないため、当然ながら恐喝は成立せず、鐚(ビタ)一文だって取れっこないわけよ。まぁ、せいぜい、親子の情に訴えて袖にお縋りするくらいしか出来ることがないってところ。 まして、『長年泥水に浸かってきた雰囲気を二十歳前の男はすでに漂わしていた……』というなら、こちら実の父親である薬種問屋のご主人が、名主・五人組同道で町奉行所に出向き、「親不孝なせがれを帳外にするお届け(いわゆる『勘当』処分)」を提出すると、家族の籍から削ることができるようになっていたんで(=息子は無宿者になる)、たかが岡っ引き風情が、あたかも悪い奴らの企みから老舗「いわし屋」の財産や家督を救ってあげたかのように、恩着せがましく、『余計な差し出口』を挟むような余地なんて、もともと有り得なかったってのが江戸時代の仕組み。 小説でも、映画でも、お芝居でも、TVドラマでも、落語でも、講談でも、出来の悪い息子が、お店のお金をくすねて女郎買いに行ったりすると、父親から、「おまえなんか勘当だ。この家から出て行け!」なんて叱られる場面って、結構ありふれているじゃないか。そういうのって、こちらの作家先生って目にしたことないのかしら。それとも、「勘当」って言葉の意味するところを知らないのかしら。 このプロットって、さしづめ、江戸時代の日本橋通りに、「チンチン電車」でも走らせてしまったってたぐいの大チョンボと言うほかないね。 こちら作家先生のお勉強不足のせいで、まるで的外れな理由のために殺される目に遭っちゃうお産婆さんって、ほんとうにお気の毒だわ。 それと、江戸時代には「営利誘拐」ってのも、まず無かった事件だよ。 徳川幕府というのは、強硬な武断主義の政権だったんで、このあいだ「アルジェリア」で起きた人質事件のように、人質にされた人間の生命なんかに構わず、犯人の姿を見たら、お上のお役人が犯人逮捕に向け斬り込んで来るんで、人質をエサに身代金の強奪を企てたって、まず取れなかったってのが実際なのね。むろん、お上に知られない隠された誘拐事件なら絶対になかったとは言えないが、もし後で身代金を支払っていたことが発覚すると、身代金を払ったほうだって、ただでは済まないのが江戸時代。お上を謀った「不埒」を責められて、追放刑(家財没収が付加される)くらいに処せられることになる。 何かのことで追われて追い詰められた被疑者が人質を盾に立籠もった事件とか、頑是ない子供を攫らって遠くの土地へ売り飛ばすとかいうような事件なら、江戸時代にもなくはなかったが、このプロットのような身代金目的の「営利誘拐」って、いかにも現代風な事件と言うしかないね。 あんまり不出来な筋書きのストーリーなんで、およそレビューなんか書く気になれず、放っぽっておいたが、ようやく気力を奮い起こして書いたのが、このレビューって次第。 『鎌倉河岸捕物控』シリーズファンの皆さん、御免なさいね。 それから、第5話のところ。 こちらの作家先生、「寺侍」というのを、どういうお侍だと理解しているんだろうか、ものすごく疑問。 率直に言って、お江戸には「寺侍」というのは居なかったってのが本当だよ。 なるほど、芝の「増上寺」や上野の「寛永寺」には、将軍家の御廟所があったんで、警護のため「山同心」というお侍が居たが、彼らはご直参の御家人であって、お寺さんに所属する「寺侍」ではない。しいていえば、築地、浅草の両本願寺には僧侶姿でない俗人の事務方もいたが、キリシタンや法華宗不授不施派みたいに徳川幕府から弾圧されたというわけではないんだけれど、でも、御公儀(幕府)は、僧侶が妻帯するのを是とした「一向宗(明治以後は浄土真宗)」を、公式には仏教教団の数には入れていなかったんで、彼らは「寺侍」にあたる者たちではないしする。 また、旗本千四百三十石お使番を勤めるお武家が、小女(こおんな)1人を置くだけという、しょぼくれた仕舞屋(しもたや)に妾宅を構えているってストーリーの設定には大笑いしてしまったね。 お武家さまは子孫を儲けることが、ご主君に対する忠義の証しとなるんで堂々たるもんだったから、どうやらお子様のいないらしい奥様に隠れて、こそこそと側妾を囲う必要なんてなく、例外なく、お旗本はお屋敷に「妻・妾同居」だったって言うね。このケースだと、正妻さんの管理のもと(※側室は、正妻さんにお仕えする使用人の扱いになる)、旗本屋敷内に居室を提供されるかたちになるってもんなのよ。江戸時代を通じて、お屋敷の外に妾宅を設け、側妾を囲っていたお旗本なんて、只の1人もいなかったって考証学者の先生方なら仰るだろうね。 『先代の和尚がまだ幼かった兄妹を気の毒に思い、佐久間様(=寺侍)とおいと様(=旗本の側室)を五、六年、真光寺の宿坊に住まわせ……中略……(旗本が)美貌に惚れこんで、側室、平たくいえば妾にしたのでございますよ。今から十年も前のことでおいと様が十七、八の頃のことです』ってよ。呆れけえって言葉もない。門前の茶屋あたりなら知らず、尼寺でもないお寺さんの宿坊に若い女性を住まわせるなんてことが許されるはずもなく、寺社奉行のお役人の目に止まったら、こちらの和尚さん、まず、日本橋で「三日曝し」の刑罰に処されたうえ、僧籍剥奪、宗門追放になること、確実だね。それとも、こちらのお旗本を色仕掛けで買収したってこと? それから、この、『正妻様が病弱なこともあり、亡くなった折は後釜にする……』ってのも駄目なんだわ。 ご公儀は、大名旗本を問わず、側室だった女性を正妻に直すことを(徳川8代将軍吉宗公が法文化し)禁止していたんで、もしも「妻が亡くなったら後妻に迎える」なんて甘っちょろい空約束を真に受けてお旗本の側室に入ったとすると、こちらの兄妹さん、可哀そうに相当な世間知らずってことになるね。 おまけに、「もと寺侍」なる浪人が、旗本屋敷に斬り込むっていう事件が起きたというのに、政次若親分ときたら、『なんともしようがありませんね』とへらへら拱手しているのって、まるで支離滅裂。江戸市中で浪人ものが刑事事件を引き起こしたら、まず南北両町奉行所が取締りにあたるのが江戸時代の決まり。こんなときこそ、町奉行所の手先を勤めているという設定の「岡っ引き」さんの出番。何はさておいても、ここは大急ぎで事件現場に駆け付けるべき場面ではなかったのと違う? あれも、これも、こちらの作家先生って、まるで解ってないんだよね。 この第5話、お妾さんの旦那さんが町人身分の者で、兄さんの浪人者も、長屋住まいの素浪人だったら通用した話なんだけれど、こちらの作家先生、たぶん、それでは、どこにでも転がっている在り来たりなストーリーだと思ったんじゃないかな。ひと捻りしたつもり。だが、あたまっから武家社会のお約束事ってのに疎いため、こちらの作家先生みずから豆腐の角に頭をぶつけて頓死しちゃうような始末になってしまったってわけだね。 第一話、『房州の薬売り』ってのが、またまたのチョンボ。 『いわし屋に出入りする薬売りの中でさ、安房国の出で木更津近辺を縄張りにする房州と仲間内で呼ばれる父っつあんがいる……』ってんで、この薬売りの父っつあん、てっきり生国が房州で、いまは木更津に在住なのかと思ったら、その先を読み進むと、「いわし屋」のご主人が、『分家と称しておりますが、確かにうちの先祖は房州の出にございましてな、未だ木更津近郊で漁師をしている縁戚もございます。その一軒につながりのあるのが朝次(=房州とっつあん)にございまして、系図をよほどしっかり辿らねば朝次の祖先に辿りつかない程度の縁……』云々と。 こちらの作家先生、どうやら「木更津」って町が、「安房の国」の内にあると勘違いしているらしいようね。 でも、「木更津」市って、同じ千葉県内でも、「上総(かづさ)の国」の内にあって、房総半島の先っぽのほうのあたる「安房(=房州)」には入らないよ。 お手許の時刻表にある鉄道地図、その「内房線」のところを見てもらうと、「木更津」駅のずっと先に「上総湊」って駅が見付かるでしょ。そのさき「東京湾フェリー」の発着港「浜金谷」駅までが「上総の国」の内であり、「安房の国」に入るのは、鋸山を越えた向こう側の「保田」駅、お隣に「安房勝山」駅ってのがあるところからだよ。 こちらの作家先生って、なんせ、「摂津国河内郡(せっつのくにかわちごおり)」とやらかすくらいなんで、今更この程度のチョンボに驚きはしないが、ほんとうに、まるっきり日本の地理や歴史に弱いんだねぇ。 もしやと思い、『江戸名所図会』を開いてみたら、日本橋川河口の江戸橋ぎわ「木更津河岸」の説明に、「房州木更津渡海往還の船ここに集ふ…」とあった。おそらく、房総半島の地理を知らず、句読点のない昔の文章を誤読したんだろう。この伝で行くと、東京駅の新幹線ホームに「大阪名古屋方面のりば」とあったりすると、「名古屋市は大阪府内にある」と誤解しちゃうってたぐいの日本地理感覚ってなるね、ハ、ハ、ハ。 もうひとつ、『品川大木戸』ってのも、初お目見得もんだ。 寡聞にして今まで筆者が読んだ書き物や耳にした話は、すべて、「高輪大木戸」とあったけどね。 どなたか、「品川大木戸」と書いたものを見掛けたら、ぜひ、教えてもらいたいもの。 「京浜急行電鉄」をご利用の方は好くご承知だと思うが、「品川駅」を発車した電車が横浜・横須賀方面、つまり南の方角に向かうと、「北品川」という駅がある。「品川駅の南に北品川駅とは、これいかに?」って東京の七不思議に数えられるくらいの話なんだが、じつは「品川駅」ってのが「品川区品川」になく、「港区高輪(正確には高輪の前浜で江戸時代は海の中だったところ)」にあるためで、「品川」という地名の地域は、お江戸から見て、京浜急行がJR東海道線を跨ぐ「八つ山」の向こう側にあたることになる。それで、「品川駅の南に北品川駅がある」って言うような次第。こんど品川駅の東京駅寄り、田町駅とのあいだ、この旧東海道「高輪大木戸」があった場所に、山手線・京浜東北線ともに新しく駅が出来るとのことだが、「高輪」と名付けるのか、「芝浦」とするのか、はたまた地下鉄の駅名に倣って「泉岳寺」とするのか、さてね? 最後に、この表紙裏の地図にある「龍閑川」ってのも間違いだよね、編集部さん。 『江戸名所図会』、「今川橋」の項、よく確かめて御覧なさい。こちらの掘割は「神田掘」とあるよ。 北側に江戸城外濠の「神田川」があって、そして、こっちは「神田掘」と紛らわしい名称の堀割だが、今回、これまで間違っていた北町奉行所の所在地を訂正した点は評価するに吝かではないが、だったら、こっちの間違いってのも、このさい、ちゃんと直して欲しいと思うな。 まだまだ、じゃかじゃか、この手のチョンボだらけなんだけれど、いささか草臥れたんで、今回は、このくらいにしておくわ。 『鎌倉河岸捕物控』シリーズ(23)『うぶすな参り』に続く、 | ||||
| ||||
|
■スポンサードリンク
|
|
|
新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!